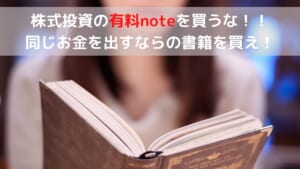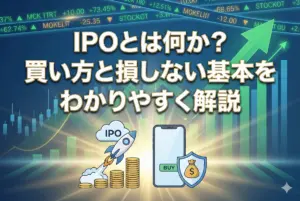金融庁の2026年税制改正要望の概要が判明しました。
注目はNISAの対象をこどもを含めた全世代へと拡大するというものです。
ジュニアNISAは廃止されましたが、それ以上に使い勝手が良いNISAが子供用に使えるとなるとかなり利便性は高そうです。
そこで今回は子供用のNISAで生涯投資枠1,800万円を“早埋め”した場合の将来価値をシュミレーションしてみました。
現状のNISAのルール確認と最新動向
現行の新NISAは年間投資枠はつみたて120万円/成長240万円です。
また、生涯投資枠が設けられており1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円)です。
18歳未満は現在NISA口座を開設できません。(ジュニアNISAは2023年末に終了し、既存資産は18歳まで非課税で保有可。
2025年8月26日付の報道で、金融庁が2026年度税制改正要望に「NISAの全世代化(高齢者・子どもを含む)」を盛り込む方向が伝えられました。
まだ確定していない話なので開始時期は当然未定。
生涯枠1,800万円を“早埋め”した場合のシュミレーション
今回はその他のルールはそのままに「子どもがNISAを使える」という仮定で、現行と整合する以下の2案を設定します。
- 案A(フル枠仮定):年360万円(つみたて+成長)で最短5年・合計1,800万円を子ども名義で拠出
- 案B(年120万円):年120万円で15年・合計1,800万円を拠出
※今の時点では実際に未成年が使える枠の範囲(つみたてのみか/成長枠も可か)は未確定です。上記は比較用のあくまで仮定です。
また下記のルールでシュミレーションいたしました。
- 円建て・年率3%/5%/7%の3ケース(税・手数料・為替は考慮外)
- 積立は年末拠出(保守的)とし、目標の1,800万円に到達後は追加拠出なしで保有
- 評価時点は子どもの年齢:15・18・22・30・40・60歳
※拠出のタイミングや複利の計算タイミングで計算結果に差はでます。
年率3〜7%は無理な数字ではない
年率3%〜7%っていうと絵に書いた餅みたいな利率だろ!って思われる方もみえるかと思いますが、そこまで無理なある数字ではありません。
例えばアメリカの株価指数のS&P500は過去65年の平均が年率10%くらいなんですよ。(ここ10年でみても年率10%程度)
また、日本の年金などを運用するGPIFも債券を半分いれた固い投資ながら年率4%を超えています。ですから年率3%〜7%はそこまで無理な数字ではないんですよ。(あくまで過去はそうだったというだけですが)
ちなみにNISAでS&P500に投資をすることも、GPIFの運用を真似をすることも容易です。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

案A(年360万円×5年)で満額(合計1,800万円)
まずは案Aのシュミレーションです。
年360万円を積みたてて5年(5歳)で上限を突破するケースですね。(後述する贈与税には注意)
5年目の拠出終了時点での残高:3% 約1,911万円/5% 約1,989万円/7% 約2,070万円。
その後は寝かせるだけです。
| 年齢 | 3% | 5% | 7% |
|---|---|---|---|
| 15歳 | 約2,569万円 | 約3,240万円 | 約4,073万円 |
| 18歳 | 約2,807万円 | 約3,751万円 | 約4,989万円 |
| 30歳 | 約4,002万円 | 約6,736万円 | 約1.1億円 |
| 40歳 | 約5,378万円 | 約1億円 | 約2.2億円 |
| 60歳 | 約9,713万円 | 約2.9億円 | 約8.5億円 |
とんでもない結果となりました。複利の力はすごいですね。
成人する18歳時点で7%だと4,989万円、3%でも2,807万円の資産を手にしていることになります。
7%だと30歳で億り人、5%でも40歳で億り人なんですよ。
さらにそのまま放置しておくと60歳で7%8.5億円、5%2.9億円、3%9,713万円となります。
複利のパワーを感じるシュミレーションですね。
案B(年120万円×15年)で満額(合計1,800万円)
次は年120万円ずつ積み立てるケースです。
15年目の拠出終了時点(15歳)での残高:3% 約2,232万円/5% 約2,589万円/7% 約3,015万円です。
| 年齢 | 3% | 5% | 7% |
|---|---|---|---|
| 15歳 | 約2,232万円 | 約2,589万円 | 約3,015万円 |
| 18歳 | 約2,439万円 | 約2,998万円 | 約3,694万円 |
| 22歳 | 約2,745万円 | 約3,644万円 | 約4,842万円 |
| 30歳 | 約3,477万円 | 約5,383万円 | 約8,320万円 |
| 40歳 | 約4,673万円 | 約8,769万円 | 約1.6億円 |
| 60歳 | 約8,440万円 | 約2.3億円 | 約6.3億円 |
こちらでもかなり高水準な金額となっています。
18歳時点で7%だと4,842万円、3%でも2,239万円の資産を手にしていることになります。
億り人になるのは7%で40歳(シュミレーションは10歳単位なので実際はもう少し早い)
60歳で7%6.3億円、5%2.3億円、3%8,440万円となります。
A案と比べると少し伸びは少なく、早期に“枠を埋めて”放置するほど、長期複利の恩恵が大きい——という結果が見えます。
それでも金額としては充分な水準ですね。
必ず押さえるべき「贈与税・名義」論点
今回はお遊び的な簡単なシュミレーションですが、複利の力がすごくかなり良い結果になることがわかっていただけたと思います。
ただし、実際にこれをやろうとすると他の問題が生じます。
贈与税の問題です。
年110万円を超えると贈与税
子ども名義のNISAに親や祖父母が資金を入れるのは贈与に当たり、原則受贈者(=子ども)側で年間110万円の基礎控除を超える部分は贈与税の対象です。
110万円は“誰から”ではなく“子が一年にもらった合計額”で判定します。
ですから父、母それぞれ半額ずつとか、祖父母から・・・とか分けても意味はありません。
また、証拠書類(贈与契約書や振込記録)も残しておきましょう。
定期贈与に注意
また、長期にわたって同じ金額を贈与すると年110万円以下であっても定期贈与として課税対象となる可能性があります。
今回のNISAの話はこの部分も要注意です。
定期贈与とは「今後20年間、毎年110万円を贈与する」等の包括的な長期約束や、自動積立・定期送金契約で“毎年贈与を行う権利”を事前に設定する形。
税務上は「定期金に関する権利の贈与」に該当し、権利の現在価値に対して最初の年にまとめて贈与税課税となるリスクがあります。
国税庁は、実際に「定期的な贈与を前提とするサービス」を定期金給付契約に関する権利の贈与として取り扱う見解を公表していますね。
セーフに近づく実務
定期贈与は以下の点に気をつけるとよいでしょう。
- 毎年ごとに贈与契約を結ぶ(前年の約束に縛られない)
- 金額や日付、方法を各年に確定し、双方の意思表示(贈与・受諾)を残す
- 原則振込で資金移動の客観的証拠を残す
- 通帳・印鑑等は受贈者側が管理(親が自由に出し入れしない)
- 「今後◯年にわたり贈与する」等の包括条項は書かない(自動振替契約も避ける)
つまり、「毎年110万円ずつ20年」自体は、“各年の独立した贈与”として積み上げるなら原則OKですが、最初に長期の約束を交わす=定期贈与は一括課税の火種になります。
契約書・資金移動・管理の実務を“毎年完結”で積み上げましょう。
その他贈与税のポイント
- 暦年贈与の基礎控除:年間110万円(受贈者基準)
- 相続時精算課税の緩和:この制度にも年110万円の基礎控除が追加(2024年改正)。2,500万円の特別控除も活用可(最終的に相続で精算)。大量資金を短期に移す場合の選択肢になります。
- 教育資金一括贈与(信託型)は期限・用途制限つき(例:最大1,500万円、期限延長の経緯あり)。NISA拠出そのものには使えない点に注意
- 名義預金の否認リスク:口座の管理権限が誰にあるか、贈与契約の合意・受諾の事実、資金移動の痕跡が重要。親が一方的に管理していると名義預金と認定されやすく、相続時に親の財産へ組み戻されるおそれ
相続時精算課税について詳しくはこちらの記事で解説しております。

実際行う場合の設計を考えてみた
実際行うとすれば贈与税の兼ね合いを考える必要があります。
その点を踏まえてポイントをまとめてみました。
拠出計画
贈与税を考えると案B(年120万円×15年)が制度整合的で現実的。
110万円基礎控除との兼ね合いで、それまでに抑えるのもよいでしょう。
10万円分は親本人の課税余力・相続時精算課税の採否を要検討
枠の“早埋め”は期待値ベースで有利だが、家計の流動性(教育費の大口支出、中高大の学費カーブ)を必ず確保したうえで検討する必要があります。
商品設計
つみたて投資枠のみなら全世界株式インデックス等の低コスト・分散を中心に考えるのがおすすめ。
年齢に応じて債券比率調整するのもあり(教育費取り崩し期の下振れリスク抑制)。
成長枠が使えるなら、枠内の株式・ETFを選ぶのもありだが、複利の力を考えるなら高配当等は避けるべし。
どちらにしても“長期で持てる”広範インデックス中心にしましょう。

運用管理
非課税×無期限の強みを生かし、売買回転を避ける(監督指針も回転売買の勧誘防止を強化)。
再投資徹底とリバランス年1回くらいがちょうど良いと思います。
証憑・名義
贈与契約書/通帳間振替履歴/進呈メモを年次で保管。
名義預金の否認リスクを避ける運用をしましょう。
代替シナリオ(家計制約がある場合)
月10万円はさすがに厳しい場合のシュミレーションも見ておきましょう。
月5万円(年60万円)×30年=総額1,800万円を子が30歳までに積み上げ→その後も非課税で複利運用
- 30歳時点:3% 約2,855万円/5% 約3,986万円/7% 約5,668万円
- 60歳時点:3% 約6,929万円/5% 約1.723億円/7% 約4.314億円
“早埋め”に劣りますが、それでもかなりの水準まで増えますね。
このパターンでも60歳時点では5%、7%なら億り人です。
家計とのバランスを取るならこれもありでしょう
よくある質問
出てきそうな質問もみておきましょう。
「NISA 全世代対象」はいつから?
2025年8月時点では税制改正要望の段階。
まだ金融庁が要望しているだけなんですよ。
年末の税制改正大綱→国会審議→施行という流れで決まってきます。
また、開始時期は未確定です。
現在は与党が衆参とも過半数を満たしていないのですぐには決まらない可能性があります。
報道は要望段階の概要で、具体の年齢・枠設計は今後示されていくと思われます。
ジュニアNISAの代わりになるの?
現行の新NISAは18歳以上のみ。
未成年の非課税投資制度は2023年末で終了(ジュニアNISA)。「子ども支援(こども)NISA」等の報道はあるものの、正式制度は未確定です
まとめ
今回は「NISAが全世代対象に?|生涯投資枠1,800万円を“早埋め”した場合の将来価値をシュミレーションしてみた」と題して子供がNISAを利用できる様になった場合のシュミレーションをみてきました。
制度が「全世代対象」に広がれば、子どものうちから“非課税×無期限×生涯枠1,800万円”を活用でき、時間の複利で将来価値は桁違いに。
ただし、開始時期・未成年が使える枠の設計は未確定。
実務では110万円基礎控除/相続時精算課税/証憑管理を前提に、家計キャッシュフローと両立する拠出設計をしましょう。
NISAをやるならSBI証券がおすすめですよ。