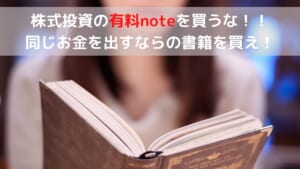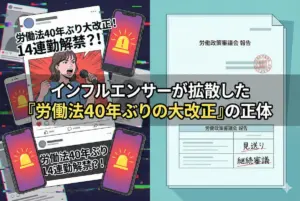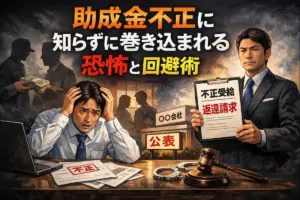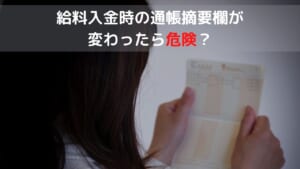最近、SNSで「銀行預金の残高が1000万円超えたら銀行から電話が来た」という話がまわっていました。
おそらく1,000万円という数字は、日本の預金保険制度(いわゆるペイオフ)の区切りとしても有名ですが、その銀行のルールとして一応ペイオフの案内とそのついでにセールスをしているのでしょう。
今回は銀行から電話について考えてみましょう。
銀行から電話が「かかってくる」主な理由
それでは銀行からかかってくる電話の主な理由について見ていきます。
AML/CFT(マネロン・テロ資金供与対策)上の確認
まず考えられるのがマネーロンダリングやテロ資金供与対策の確認です。
これは日本の金融機関は、犯罪収益移転防止法等に基づき、疑わしい取引の届出(STR)や追加の本人確認を行う義務があるためです。
取引の動きや属性に不自然さがあれば、質問や確認のお願いが来るということ。
これは“勧誘”ではなく法令対応なのです。
海外からの入金があるとかなりの確率でかかってきますね。
銀行によって電話での確認だけだったり、書類を送ってきて、入金内容を書かせて送り返すなどのパターンはあります。
どこかは書きませんが某ネット銀行などはその両方をクリアしないと口座に入金してくれないんですよ・・・
2025年もFATF基準の改訂や有効性重視の流れが続き、各行はリスクベース・アプローチ(RBA)を強化しています。
運用残高や入出金パターンが大きく動くと、「念のための確認」が増えるのは自然です
>>金融庁 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について
預かり資産に応じての「お金持ち向け提案」
また、預かり資産が一定水準に達すると、優遇プログラムや資産運用のご提案を目的に連絡が来ることもあります。
例えば、世帯合計1,000万円以上等を目安に優遇サービスを案内するケースや、外貨・投信・保険などの面談打診が代表例です。
一部の銀行・信託・外資系チャネルでは「1,000万円」「5,000万円」「1億円」など預金残高区分で担当者アサインやステータスが変わるのが一般的。
電話=勧誘と決めつけるのではなく、“法律対応の確認”と“営業提案”を切り分けて考えるのがポイントです。
信用金庫などでは500万円くらいから担当が付くケースもあります。
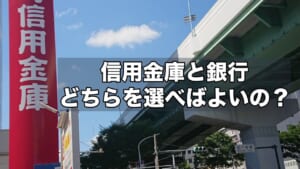
金利・商品環境の変化に合わせたアナウンス
金利や商品ラインナップが変わる局面では、情報提供や乗換提案の連絡が増えます。
メガ・地銀の定期金利変更や各社キャンペーンがきっかけになることも。
入金のお礼
一定額を超える入金があるとお礼がかかってくるケースもあります。
その御礼は口実でセールスがメインだと思われすが・・・
私のケースだと100万円くらいでお礼の電話がかかってきたこともありましたね。
高額商品を買ったために、クレジットカード引き落とし用の残高を他の口座から移しただけなんですけど笑
勧誘電話
純粋な勧誘電話がくることもあります。
多くは銀行が直接というよりも営業代行みたいなところを使っている感じですね。
基本的に銀行に限らず電話での営業はろくな商品でないケースが多いので聞くだけ無駄だと思われます。
「1,000万円」を超えたら必ず電話が来る?
今回のテーマの預金残高1,000万円も入金のお礼などと同様に電話が来るトリガーになる可能性はあります。
1,000万円はペイオフの線引きであって電話しないといけないというルールは金融庁が定めているわけではないんですよ。
銀行の内部ルール次第といったところですね。
私も某ネット銀行の残高が1,000万円を超えることはありますが、電話連絡がきたことはありません。
詐欺電話
また詐欺も増えているのでご注意ください。
銀行や公的機関を装う詐欺は年々巧妙化しているんですよ。
キャッシュカード預かりや口座情報の聴取を電話で求めるのは詐欺の典型です。
リンクを踏ませるフィッシングにも注意。
正規の銀行・当局は電話で暗証番号等を聞きません。
1,000万円以上になったらやるべき“守りの設計”
預金残高が1,000万円以上になったら考えておきたい話をみていきましょう。
ペイオフを踏まえた口座の分散設計
ペイオフでは金融機関“ごと”に1,000万円+利息が保護対象(決済用預金は全額)となります。
つまり、そこまでは補償されるけど、それを超えた分は返ってこない可能性があるってこと。
万一の銀行破綻に備え、金融機関分散を基本設計にするべきです。
同一行の複数支店に分けても合算(名寄せ)されます。
つまり、1,000万円までしか同一金融機関に預けないということが重要ってことです。
絶対倒産しないとは限らないですからね。
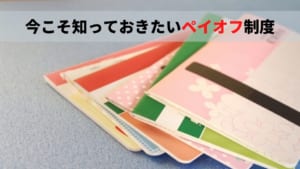
銀行からの商品勧誘は慎重に
多くの金融機関からの勧誘する商品は手数料が高かったり、あまり良い商品でないことがほとんどです。
これは金融庁が問題視していましたが、自社の儲けを重要視しちゃっている結果なんですよ。
友人も下記のように嘘ばかり教えられるケースもありましたね。

電話で商品を勧められたら基本的に断るのがおすすめ。
どうしても断りきれないなら一旦保留して、手数料や為替コスト、途中解約時の不利を必ず確認しましょう。
同じような商品がネット証券会社なら手数料激安で買えるケースもあります。
銀行やFPが自社の儲けばかりでまともなアドバイスをしないため、金融庁ではJ-FLEC認定アドバイザーなる制度まで作ったようです。

セキュリティの原則
電話で暗証番号・認証コードは絶対に伝えないことも意識しましょう、
聞いてくる時点で詐欺です。
また、カード預かり・交換も詐欺の定番。
宅配・警察・銀行協会名乗りも同様に無視しましょう。
SMS/メールのリンクは踏まないことも重要。
多くの口座乗っ取り事件はフィッシングが原因なんですよ。
必要なら自分で公式サイト直接行きましょう。

まとめ
今回は「「銀行に1000万円以上預けると電話が来る」って本当?資産運用の勧誘か法令確認か——安全に見分けるチェックリスト」と題して銀行からの電話についてみてきました。
「銀行預金の残高が1000万円超えたら銀行から電話が来た」というのはその人がそうだっただけで、残高が1000万円超えたら電話必至ではありません。
銀行のルールでそうしているだけだと思われます。
法令対応の確認電話と営業提案の電話を分けて考えましょう。
ただし、残高が1000万円超えたらペイオフのルールは真剣に考える時期に来ていますので、預金残高を金融機関を分けて分散することを意識すると良いでしょう。