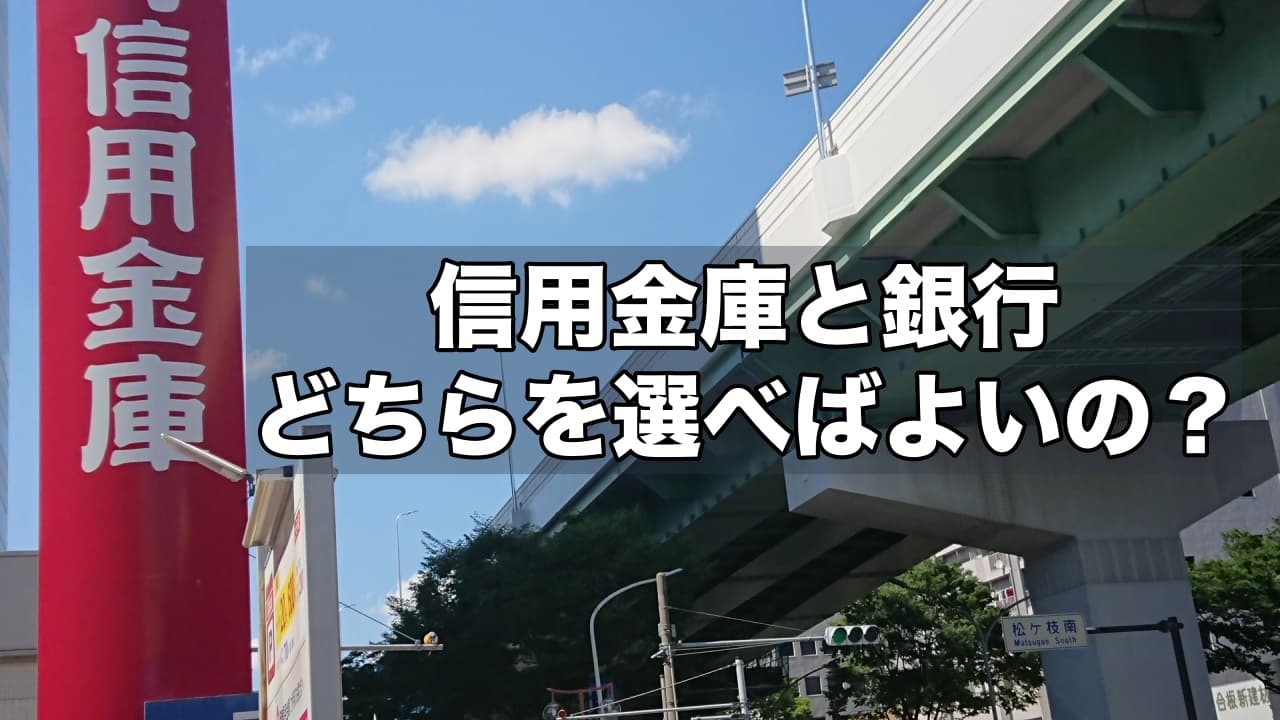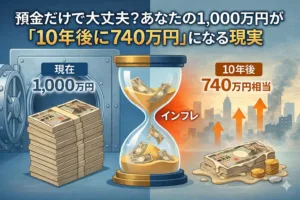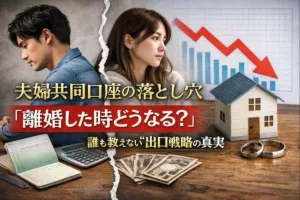信用金庫と銀行の違いってご存知でしょうか?
基本的に同じようなサービスを提供しているのですが、いくつかの点で違う点があるんですよ。
人によっては信用金庫をメインで利用したほうが良いという場合も。
今回は信用金庫と銀行どちらを選べばよいの?という観点から信用金庫と銀行の違い、それぞれのメリット・デメリットについて見ていきましょう。
信用金庫と銀行は何が違うのか?
信用金庫と銀行。
預金口座を作ったり、お金を借りたり、投資信託を買ったり、提供しているサービスは重なっているところがほとんどです。
そのため、あまり近いを認識している方は多くないと思いますが、いくつかの点で違う点があるんですよ。
そもそもの根拠法が違う
信用金庫と銀行はそもそもの根拠方が違います。
銀行は銀行法ですが、信用金庫は信用金庫法なんですよ。
それによりいくつかの違いが生じてくるのです。
商工会議所と商工会の違いみたいなもんですね。

信用金庫は非営利法人
まず信用金庫は非営利法人である点が銀行と大きな違いでしょう。
信用金庫は会員の出資で成り立った共同組織なんですよ。
つまり、地域の会員同士の助けあい(相互補助)が大きな目的となっているのです。
そのため、信用金庫は利用するために出資が必要となります。
このあたりは銀行と大きく違いますね。
出資の金額は信用金庫によって異なりますが、5千円からとか1万円からとなっているようです。
商工会議所などと似ていますね。
出資金は株式会社の株のようなもので、信用金庫は非営利団体であるため、出資割合に応じて利益は配当されます。
また、信用金庫の会員を辞める場合は返金ありです。
ただし、出資した信用金庫が破綻すれば戻って来ない可能性もあります。
利用者は基本的に地域の方限定
また、目的がその地域の会員同士の助けあいですから利用者(会員資格)にも制限があります。
基本的にその地区で居住をしていたり、その地区で勤務していたり、その地区で事業をしているという必要があります。
- その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者
- その信用金庫の地区内に事業所を有する者
- その信用金庫の地区内において勤労に従事する者
出典:信用金庫法 第二章第十条 会員たる資格
また、事業者の場合には従業員数300人以下または資本金9億円以下と決められています。
信用金庫のメリット
それでは信用金庫を利用するメリットはどんな点にあるのでしょう?
あまり知られていないメリットがいくつかあるんですよ。
担当が付くハードルが低い
まずひとつ挙げられるメリットは信用金庫は担当がつくハードルが低いことです。
大きな銀行で担当が付くのはかなりハードルが高いです。
よほどたくさんの預金をしているとか借り入れをしているとかでない限り相手にされません。
しかし、信用金庫はかなりそのハードルが低いんですよ。
知り合いの中小企業診断士(元信用金庫勤務)の方から聞いた話だと500万円くらいの預金から付くとのこと。
※その信用金庫や支店によっても条件異なると思います。
銀行だとそれくらいで担当がつくことはまずないでしょう。
ですから担当者にいろいろ相談したいと考えている方には信用金庫はメリットが有るのです。
担当が付けば、お得な情報が教えてもらえたり、相談が出来ますからね。
例えば地域の建築業者や弁護士や税理士、司法書士などの士業を紹介してもらったりなんてこともできます。
また、銀行で資産運用の相談するとノルマを達成するためなのか自社の儲け優先の酷い商品を勧められることも多いです。

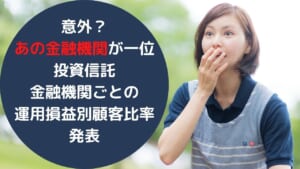
小さな取引でも親切に対応
銀行は営利目的の団体です。
そのため、規模が小さい相談(銀行が儲からない話)にはどうしても冷たい対応されるのは避けられません。
しかし、信用金庫は非営利団体ですから小さい相談でも親切に対応してくれるケースが多いんですよ。
例えば開業したばかりの方が銀行から融資を受けようとしてもなかなかハードルは高いですが、信用金庫なら親身になって相談を受けてくれるケースも多いのです。
私も開業したばかりの方が融資を受けたいという話があれば日本政策金融公庫か信用金庫をおすすめしますね。
出資金の利回りが結構良い
利用していない方はご存じないでしょうが、信用金庫の出資金の利回りはかなり良いです。
その信用金庫によっても異なりますし、その年によっても異なりますが、高いところだと年10%のところもあります。
私が使っている信用金庫は5%ですね。
かなり高利回りの投資先となっています笑
非営利法人で利益は配当に回していますから当然といえば当然なんですけどね。
ただし、前述のように出資した信用金庫が破綻すれば戻って来ない可能性もありますのでご注意ください。
信用金庫のデメリット
それでは信用金庫にデメリットはあるのでしょうか?
当然あります。
利便性が銀行に劣る
最大のデメリットは銀行と比べて利便性が劣る点でしょう。
例えばATM。
銀行と比較してATMの数が多くありません。
信用金庫同士のネットワークがありますので地域外でも利用は可能ですがそもそもの絶対数が少なめなんですよ。
コンビニATMでも手数料が取られる信用金庫が多いですしね。
また、銀行への振込などが高い手数料となっていたりします。
信用金庫をメインで使うにしても、ネット銀行などと使い分けが必要かもしれません。
地域外に店舗がほとんどない
当然といえば当然ですが、信用金庫は地域密着です。
その地域を離れてしまえばほとんどその信用金庫は見かけなくなります。
前述のようにATMの利用は他の信用金庫があれば問題ありませんが、それ以外の取引がやりにくくなってしまうんですよ。
まとめ
今回は「信用金庫と銀行どちらを選べばよいの?違い、メリット、デメリットなどを解説」と題して信用金庫と銀行の違い、それぞれのメリット・デメリットについてみてきました。
信用金庫は銀行と似ていますが、かなり毛色が違うことがわかっていただけたと思います。
担当者が付くハードルが低いことなどに魅力を感じる方は利用を検討しても良いかもしれませんね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。