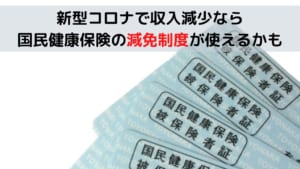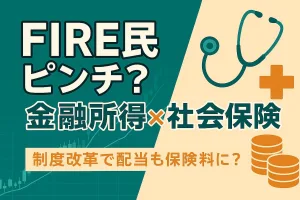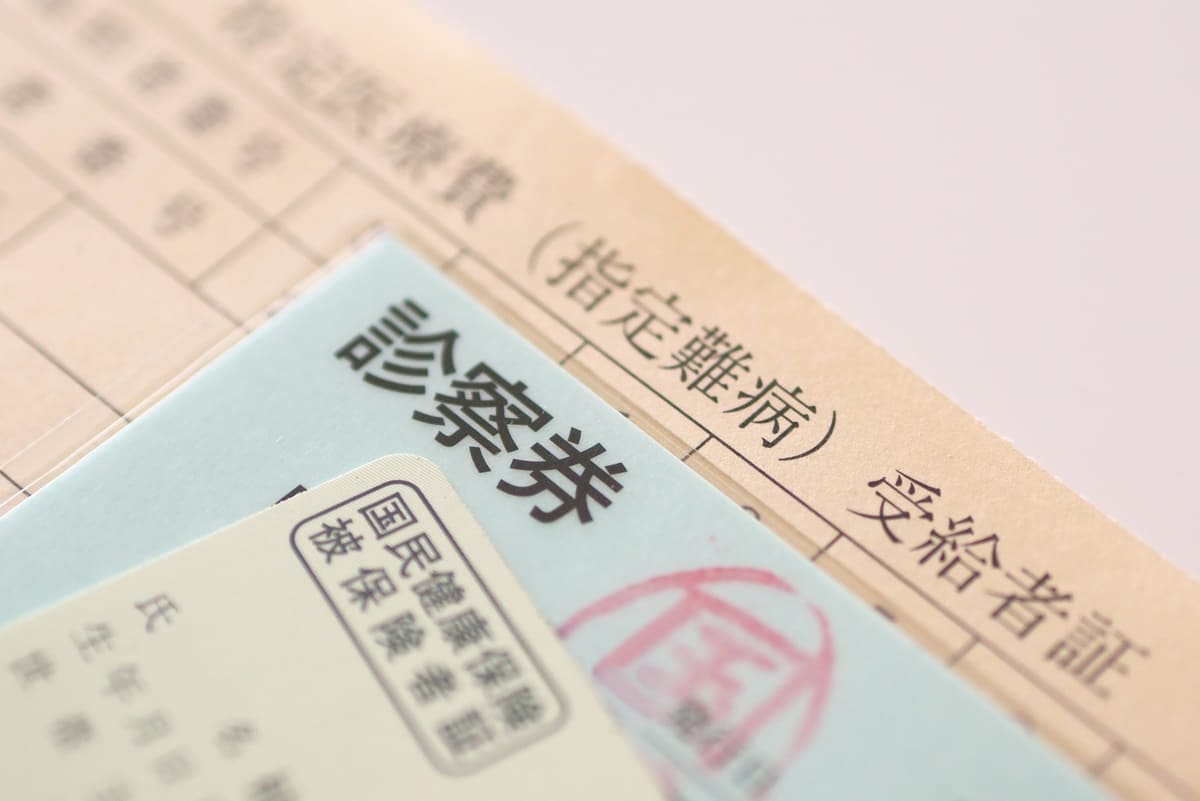国民健康保険は自営業者などが加入する健康保険ですが、サラリーマンの方が入る健康保険と比較して会社負担もありませんから割高なんですね。
そのため払うのがかなりきついという方も多いと言います。
そんな国民健康保険ですが、実はあまり知られていない全額免除されたり、一部免除(減免)される制度があるのです。
これらは基本的には自分から言い出さないと適用されない場合が多いんですよ。
今回はそんな国民健康保険の全額免除や減免について条件や基準を解説していきます。
国民健康保険の全額免除・一部減免の種類
国民健康保険には、免除や減免される制度がいくつか用意されています。
その種類によって対象となる条件や基準が違います。同じように国民年金にも免除制度がありますが、少しルールが違いますのでお気をつけください。
また、国民健康保険の減免は市町村ごとに条例で定められた制度となります。そのため管轄の市町村によってルールが違う点がありますので注意が必要です。
市町村によってはそもそもWEB上にすら記載がなく問い合わせてようやく教えてくれるような運営をしているところもあったりするんですね・・・
国民健康保険の全額免除
まずは国民健康保険の全額を免除される全額免除です。
こちらはその名前の通り国民健康保険の全額が免除を受けることができます。
国民年金の免除などと違い将来の年金が減らされるということもありません。
ただし、条件はかなり厳しくなります。
基本的に全額免除となるのは特別な場合に限られます。
具体的な免除の条件は市町村ごとにより異なりますが多いのが以下のパターンです。
このパターンに該当していても免除とはならずに減免となる市町村もあります。
生活保護を受けている場合
障害基礎年金、障害厚生年金の1級・2級を受給している場合
刑務所に服役している場合
天災その他特別な事情で収入が激減した場合
倒産や解雇により所得がなくなってしまった場合
生活保護を受けている場合
生活保護を受けている場合は、国民保険の加入者とみなされず国が医療費を負担する形となります。そのため保険料は全額免除となります。
障害者年金の1級・2級
障害基礎年金、障害厚生年金の1級・2級を受給している場合にも基本的に全額免除の対象となります。ただし、自治体によって障害者の基準が異なる場合がありますので詳しくはお住まいの自治体にお尋ねください。
生活が困窮している場合
生活が困窮している場合にも全額減免の可能性があります。例えば横須賀市の場合には以下の取扱となります。(自治体により異なりますのでご確認ください)
世帯主及び被保険者が貧困により生活のため、公の扶助またはこれに準ずる扶助を受け、または受けるに相当するとき。
この場合には所得割額の全部が減免されます。
自治体によっては住民税が非課税か否かはで判定しているところもありますね。
刑務所に服役している場合
こちらもすべての自治体ではありませんが、給付制限ということで基本的に全額免除の対象となります。刑務所に入っている間に健康保険を使うことはありませんからね。
刑務所等に入っているため、月初めから月末を通して医療の給付が受けられない方
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」
この場合にはその間の保険料額全額免除になります。
国民健康保険の減免
次は国民健康保険の一部を免除される減免です。
ちなみに国民健康保険は所得により金額が変わる「所得割」と平等にかかってくる「均等割」の二つがあります。
減免される際も所得割が減る場合もあれば均等割が減る場合、全体が減る場合など様々ありちょっとややこしいですね。
こちらも市町村により条件が違います。
例えば愛知県名古屋市の場合を例に減免の条件を見ると以下がその条件となっています。
○所得が一定未満
○所得が激減
○事業を休止・廃止したことにより、世帯の今年の見込所得が赤字となる世帯
○災害により、居住する家屋に全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水の被害を受けた世帯(全額免除の場合もあり)他
それぞれの具体的な部分をもう少し見ておきましょう。
所得が一定未満
まずは所得が一定未満の場合です。名古屋市の場合には以下のルールとなっています。
詳しい内容は各市町村毎により規定されています。お住まいの市町村役場にお尋ねください。
「保険料の減額」が適用されていない世帯で、平成29年中の所得の合計が「66万円+(35万円×被保険者数)」以下の世帯
例;1人世帯:66万円+(35万円×1人)=101万円以下
この場合に受けられる減免は均等割額の2割です。
所得が激減
次は所得が激減した場合です。以下の条件をすべて満たす世帯が対象となります。
・前年中の所得が1,000万円以下の世帯
・今年(申請時点の年)の見込所得が264万円以下の世帯
・今年(申請時点の年)の見込所得が前年中の所得の10分の8以下に減少する世帯
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」
この場合に受けられる減免額は激減の程度により所得割額の3割〜7割です。
事業の休止・廃止
次に自営業者などが事業を休止や廃止をしたケースです。
事業を休止・廃止したことにより、世帯の今年の見込所得が赤字となる世帯
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」
この場合に受けられる減免額は保険料額の7割です。
災害減免
次は災害の被害者となったケースです。
災害により、居住する家屋に全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水の被害を受けた世帯
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」
この場合に受けられる減免額は被害の程度により災害発生月から6か月以内の保険料額の全額または5割です。
障害・寡婦・寡夫
次は障害、寡婦、寡夫です。
平成29年12月31日現在、障害者の方(障害者手帳・愛護手帳の交付を受けている方等)または寡婦・寡夫の方のうち、次のいずれかに該当する方
・当該被保険者の平成29年中の所得が125万円以下である。
・「保険料の減額」のうち、「均等割額の2割の減額」が適用されている世帯に属している。
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」
この場合に受けられる減免額は均等割額の3割(「均等割額の2割の減額」が適用されている場合は差額の1割)
高齢者
次は高齢者です。
平成29年12月31日現在、65歳以上の方のうち、次のいずれかに該当する方
・当該被保険者の平成29年中の所得が35万円以下である。
・「保険料の減額」のうち、「均等割額の2割の減額」が適用されている世帯に属している
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」
この場合に受けられる減免額は均等割額の3割(「均等割額の2割の減額」が適用されている場合は差額の1割)
旧被保険者
最後は旧被保険者です。
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けることに伴い、その被扶養者が国民健康保険の被保険者資格を取得する場合で、国民健康保険の資格取得時に65歳以上である方
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」
この場合に受けられる減免額は当該被保険者の均等割額の5割及び所得割額の全額
国民健康保険の減額(軽減)
次は国民健康保険の減額について見ていきましょう。
こちらは前年の所得が一定額以下の世帯の場合に減額してくれる仕組みです。
こちらも基本的には同じルールですが、微妙に自治体により違っているところがあります。
詳しい内容は各市町村毎により規定されていますのでお住まいの市町村役場にお尋ねください。
ここでは名古屋市と大阪市の例を見ておきましょう。
名古屋市の例
| 減額の割合 | 平成29年中の世帯の所得 | 減額される額 |
|---|---|---|
| 7割 | 33万円以下のとき | 世帯の均等割額の7割 |
| 5割 | 33万円+(27万5千円×被保険者数)以下のとき | 世帯の均等割額の5割 |
| 2割 | 33万円+(50万円×被保険者数)以下のとき | 世帯の均等割額の2割 |
名古屋市は上記の式に当てはまると世帯の均等割額が7割、5割、2割減額されます。
大阪市の例
| 世帯人数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 3割軽減 |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 330,000 | 605,000 (600,000) | 830,000 (820,000) | 610,000 |
| 2人 | 330,000 | 880,000 (870,000) | 1,330,000 (1,310,000) | 890,000 |
| 3人 | 330,000 | 1,155,000 (1,140,000) | 1,830,000 (1,800,000) | 1,170,000 |
| 4人 | 330,000 | 1,430,000 (1,410,000) | 2,330,000 (2,290,000) | 1,450,000 |
大阪市は上記の式に当てはまると世帯の医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割が軽減されます。
会社都合等で退職した場合
会社都合で会社を退職した方も保険料が軽減される場合があります。
こちらも自治体によりルールが異なっていますので詳しくはお住まいの自治体でご確認ください。
こちらも名古屋市と大阪市の例を見てみましょう。
名古屋市の例
雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の番号が「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」の方
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」
この場合には給与所得金額を100分の30として保険料額の算定されます。
特定受給資格者や特定理由離職者については下記記事を御覧ください。実は該当しているケースが結構あるんですよ。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//24140"]
大阪市の例
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下のいずれかに該当する方(離職時に65歳以上の方を除く)
11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)
23・33・34(特定理由離職者)
出典:大阪市「保険料の軽減・減免」
該当する対象者のルールは基本的に同じですね。軽減内容は多少違います。所得割について、給与所得を100分の30にして計算します。平等割、均等割について、7、5、2割軽減及び3割軽減の判定の際は、給与所得を100分の30にして判定
全額免除・減額は基本的に申請が必要
上記のような全額免除や減額に該当する場合には基本的に自分から申請をする必要があります。(一部は自動的に適用)
ですからもし該当するかもしれないと感じた方は住んでいる自治体の窓口で相談しましょう。
相談する際には健康保険証、世帯の所得がわかるもの(給料明細や源泉徴収票)などをご用意しておくとスムーズに運ぶでしょう。
また、自治体によって必要な書類も違いますので無駄足にならないように事前に必要書類を確認しておくとよいかもしれませんね。
全額免除・減額のデメリットはあるのか?
国民年金にも免除制度がありますが、こちらの場合は将来もらえる年金が減ってしまうというデメリットがありました。
しかし、国民健康保険の全額免除・減額は基本的にデメリットはありません。
全額負担している方と同様に医療費の軽減などを受けることができます。
もちろんそれ以外の葬祭費などの給付も受けることができます。
ですから該当するならば申請したほうが良いものと言えるでしょう。
国民年金の免除制度についてはこちらの記事を御覧ください。

さかのぼって減免はできない。
また、国民健康保険は多くの市町村で「減免を受けようとする国民健康保険の納期限の7日前までに、あるいは納期限までに必要書類を添付して申請しなければならない」とされています。
つまり、さかのぼって申請したり、減免を受けることはできないのです。
ですから該当するかもしれないと思った方は早めに市町村の窓口に相談にいきましょうね。
まとめ
今回は「国民健康保険を全額免除されたり一部免除(減免)される条件や基準を解説」と題して国民健康保険を全額免除されたり一部免除されたりする場合の条件についてみてきました。
まとめると以下のとおりです。
国民健康保険は会社等の健康保険に加入していないかに加入義務がある制度です。
一定期間滞納すると保険証が使えなくなり、被保険者資格証明書というものになり、一旦医療機関の窓口で全額負担をして手続き後7割が戻ってくる制度になっていまいます。かなり面倒ですよね。
さらに延滞すれば延滞金もついてしまいますし、7割戻ってくるはずのものが延滞額と相殺されたりもします。そうなる前にどうしても払えないなら自治体の窓口に相談に行ってみてください。
上記の免除が減免、減額に該当しているかもしれませんよ。
国民健康保険とはなんぞや?って方や国民健康保険ってなぜ高いの?という疑問がある方は下記の記事を御覧ください。

また、国民年金の免除については下記記事を御覧ください。

なお、新型コロナウィルスのときには収入が減った方用の減免制度なんかもありましたね。