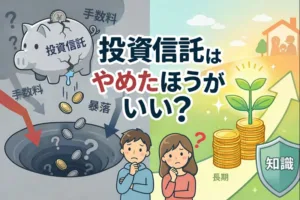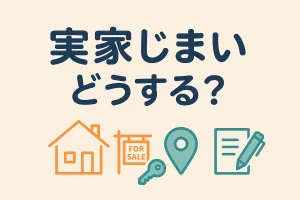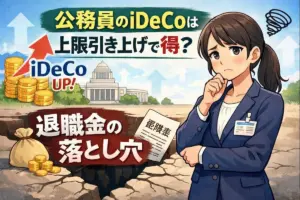つみたてNISA(積立NISA)はどこの金融機関で始めても同じだとおもっていませんか?
実はかなり違いがあります。
非課税期間が20年と長いためどこの金融機関(銀行・証券会社)で始めるのかはかなり重要になってくるのです。
今回は2022年3月時点でつみたてNISAをどこで始めればよりお得なのかを考えてみたいと思います。
なお、そもそもつみたてNISAってなに?どうやって始めたらいいの?って方はこちらの記事も合わせて御覧ください。
つみたてNISAを始める金融機関を選ぶ際のポイントは2つ
まずはつみたてNISAの金融機関(銀行、証券会社)を選ぶ際のポイントを見ていきましょう。
ポイントがどれだけ貯まるか
商品のラインナップ
- インデックスファンドである
- 信託報酬が低い
- ノーロードであること(購入時手数料無料)
- 純資産額が多いこと
- ベンチマークとの乖離が少ないこと
ちなみにつみたてNISAの場合にはほとんどの商品がインデックスファンドですし、すべてノーロードです。
ですから差がでてくるのは信託報酬と純資産額、ベンチマークとの乖離の部分になります。
商品ラインアップを比較してのおすすめの金融機関
それでは商品ラインナップで比較をするとどこの金融機関がよいのでしょうか?
これはずば抜けて下記6社が良いですね。
そもそも取り扱い商品数が多いのです。
SBI証券
松井証券
auカブコム証券
SMBC日興証券
マネックス証券
※取り扱い本数が多い順
商品数比較(3月8日現在)
具体的には以下の本数がラインナップされています。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
| 楽天 | SBI証券 | 松井証券 | auカブコム証券 | SMBC日興証券 | マネックス証券 | |
| インデックス | 160本 | 160本 | 156本 | 149本 | 143本 | 137本 |
| アクテイブ | 20本 | 18本 | 17本 | 15本 | 15本 | 15本 |
| 合計 | 180本 | 178本 | 173本 | 164本 | 158本 | 152本 |
ちなみに銀行のつみたてNISAのラインナップは自社商品を中心に数本しかないケースが多くなっています。
例えばメガバンクは三菱UFJ銀行は12本、みずほ銀行5本、りそな銀行4本、三井住友銀行3本となんとも寂しいものとなっていますね・・・
また、野村證券も7本しか扱っていません。
ただし、この投資信託を買うと決まっている人はその投資信託の扱いがあれば商品ラインナップに特に拘る必要はありません。
例えば野村證券は前述のように本数は少ないですが「野村スリーゼロ先進国株式投信」を取り扱いしています。
「野村スリーゼロ先進国株式投信」は野村證券、LINE証券(LINEと野村證券が組んで作られた会社)が囲い込んでいますので他で取り扱いが無いんですよ。
この投資信託が買いたいというものがある方はその商品の取り扱いがあるところで決めればよいでしょう。
ポイント制度
もう一つがポイントがどれだけ貯まるかということです。
ここはかなりどこを選ぶかで差がついてきていますね。
その点を勘案するとおすすめは
- マネックス証券
- SBI証券
- auカブコム証券
- 楽天証券
この4つに絞られます。
クレジットカードでのポイント
まず最も注目したいのはクレジットカードでつみたてNISAができるのかという部分です。
クレジットカードでつみたてNISAを利用してもポイントが付与されるんですよ。
ただし、クレジットカードでのつみたてNISAを提供している金融機関はそれほどなく、選択肢となりえるのは上記4社となります。
それぞれの還元率は以下の通り。(SBI証券は利用するクレジットカードにより還元率が異なる)
・SBI証券+三井住友カード プラチナ:2.0%
・マネックス証券+マネックスカード:1.1%
・SBI証券+三井住友カード ゴールド(NL)
:1.0%
・SBI証券+三井住友カード(NL)
:0.5%
三井住友カード プラチナは例えば三井住友カード プラチナプリファードで年会費33,000円掛かるなど高めとなっています。
ですから普段クレジットカードをたくさん使うなどつみたてNISA以外でのメリットがある方にはおすすめできるカードです。
しかし、それ以外の方には年会費分で負担が大きくなってしまいます。
ですからクレジットカード還元では現実的には1.1%付与のマネックス証券+マネックスカードが有力候補となってくるでしょう。
マネックスカードは初年度の年会費無料 。
次年度以降は550 円(税込)掛かりますが、年間 1 回以上のご利用で翌年度無料となっています。
なお、年間1回以上の利用のカウントにつみたてNISAも含まれるとのことです。
私も作っておりますのでこちらで解説しております。合わせて御覧ください。
投資信託保有でのポイント
もう一つが投資信託保有でのポイントです。
つみたてNISAは掛けられる金額が年間40万円。
20年間と決まっていますのでそこまで重要視しなくても良いかと思いますが、もらえるならもらっておいた方が良いですからね。
この点でも上記の4社が有力です。
それぞれも投資信託保有でのポイントは以下の通り。
なお、どこの証券会社が得なのかはその投資信託によって異なっています。
マネックス証券の投信プログラム
マネックス証券は保有している投資信託によって付与率が異なってきます。
月内の平均投資信託残高で最大0.08%が付与されます。
- 通常:0.08%
- 指定銘柄:0.03%
- 指定銘柄:0%
保有でポイントが付かないのはSBI・全世界株式インデックス・ファンドなどSBI系の一部のファンドとかですね。
SBI証券の投信マイレージサービス
SBI証券は保有金額と保有している投資信託によって付与率が異なってきます。
|
||||||||||||
auカブコム証券の資産形成プログラム
auカブコム証券も保有金額と保有している投資信託によって付与率が異なってきます。
| 月間保有残高 | 100万円未満 | 100万円以上〜3,000万円未満 | 3,000万円以上 |
| 通常銘柄 | 0.05% | 0.12% | 0.24% |
| 指定銘柄 | 0.005% | ||
楽天証券+楽天銀行のハッピープログラム
楽天証券は他と違い残高に達したときに1回だけの付与となります。(4月から)

出典:楽天証券 【楽天銀行・ハッピープログラム】ポイント進呈条件の変更に関するお知らせ より
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
まとめ
今回は「【2022年3月版】つみたてNISA(積立NISA)はどこの金融機関で始めるべきか?」と題してつみたてNISAをどこで始めるのが良いのかを考えてみました。
まとめると以下の通り。
- 商品面では、楽天証券、SBI証券、松井証券、auカブコム証券、SMBC日興証券、マネックス証券
- ポイント面ではマネックス証券
がおすすめでした。
なお、マネックスカードの申込みはマネックス証券のログイン後に専用ページから行うことができます。
ですからまだマネックス証券の口座を持っていない方は口座を作るところからですね。
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです