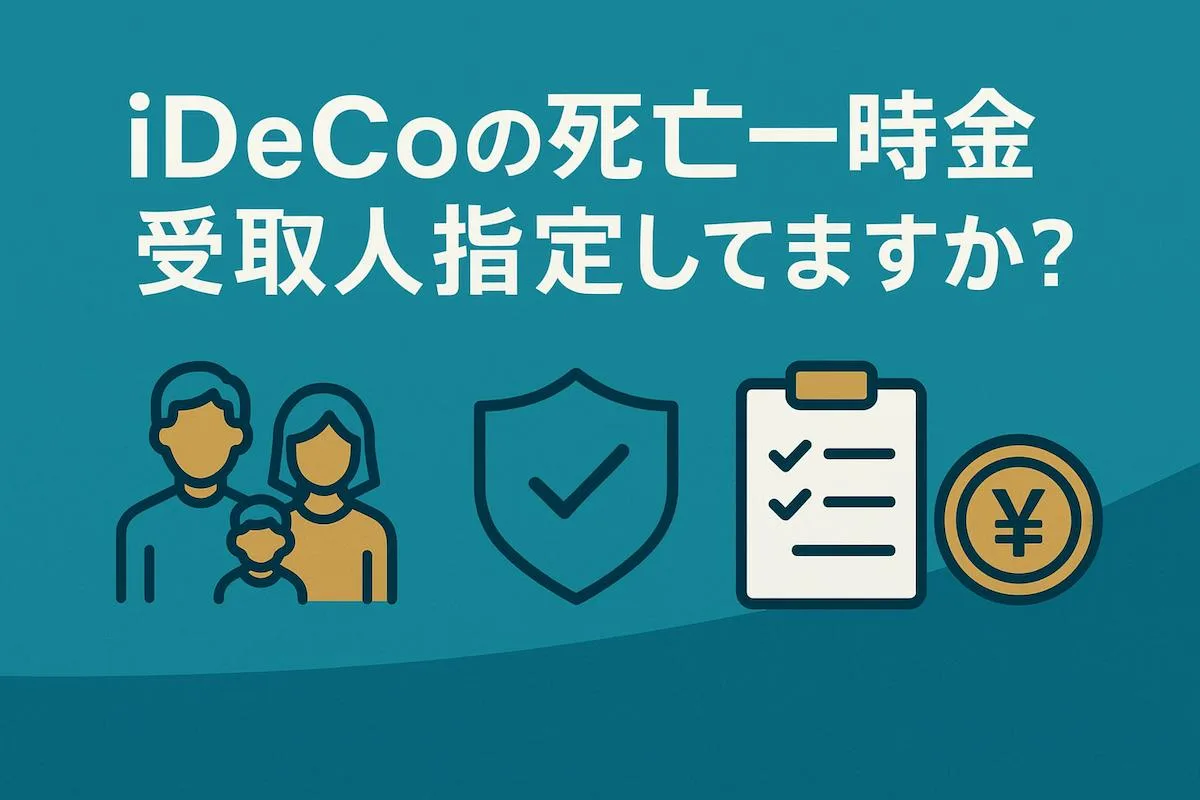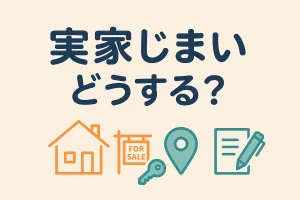iDeCoは加入者が亡くなると「死亡一時金」を遺族が受け取れます。
あまりアナウンスされていませんが、事前に死亡一時金の受取人を指定しておくとスムーズに遺族が受けとれるように。
今回は死亡一時金の受取人指定及びそれに関係する話を見ていきます。
なぜ「死亡一時金の受取人指定」が大事か
iDeCoは私的年金制度で、原則60歳以降から受け取れます。
しかし、加入者が亡くなった場合には年齢に関係なく口座残高は遺族に「死亡一時金」として支払われます。
その際に死亡一次金の受取人の事前指定があると、最優先でその人が受け取り、手続きも簡略化されやすく、ご家族の負担軽減につながるのです。
受け取る人が決まっている方は事前に手続きをおすすめします。
加入時に指定できるようにしてくれても良い気もしますが笑
iDeCo制度の詳細についてはこちらを御覧ください。

iDeCoの死亡一時金:誰が、いくら受け取れる?
まずは今回の話の前提となる死亡一時金について解説しておきましょう。
受取人の範囲と受取順位(民法と異なる点に注意)
iDeCoの死亡一時金は、確定拠出年金法に基づく独自の順位で受取人が決まります。
民法の法定相続順位とは異なる点に注意が必要です。
- 指定受取人(生前に加入者が指定)
- 配偶者(内縁を含む)
- 子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、亡くなった方の収入で生計を維持していた人
- 上記以外で、亡くなった方の収入で生計を維持していた親族
- 子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、生計維持に該当しない人
同順位が複数いる場合は等分となります。
実務上は代表者に一括振込→内部で按分する運用です。
受け取れる金額(いくら?)
受け取れる金額は原則、口座の個人別管理資産相当額(評価額)が支払われます。
つまり、iDeCoの口座に貯まったお金がそのまま支給されるってことですね。
受取の期限(時効あり)
死亡日から5年を過ぎると死亡一時金としては請求できず、相続財産として供託の扱いになる可能性があります。
残された遺族がiDeCoに加入をしていることを知らないと当然請求もできないので、エンディングノート等を作っておくのがおすすめ。
死亡一時金の税金:3つのタイミングで扱いが変わる
次に死亡一時金の税金について見ておきましょう。
実は受け取るタイミングによってルールが変わるんですよ。
死亡後3年以内に支給確定 → 相続税
死亡後3年以内に支給が確定した場合には死亡退職金等として相続税の対象となります。
なお、相続税には非課税枠があります。
死亡後3年超~5年以内に受け取り → 一時所得
3年を超えると遺族(受取人)の一時所得扱いに変わります。
一時所得は「収入-経費-特別控除50万円」の1/2が課税対象です。
死亡後5年超
死亡後5年を超えると死亡一時金としては請求できず、相続財産として法務局に供託の扱いとなる可能性があります。
※税制は適用条件により異なる場合があります。具体的な確定申告の可否などは、国税庁、税務署、税理士にご確認ください。
SBI証券での「死亡一時金受取人 指定・確認・変更」手順
参考までに私がiDeCoの加入しているSBI証券で受取人指定をする場合の手続きを見ておきましょう。
おそらく他の証券会社でも大きくは変わらないと思われます。
死亡一時金受取人指定に関する申請書を記入・提出
SBI証券の場合はiDeCoサイトにログイン後に「死亡一時金受取人指定に関する申請書」のPDFをダウンロードできるようになっています。
「死亡一時金受取人指定に関する申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証等)を同封のうえ、郵送するだけです。
ラベルも印刷できますのでかなり簡単ですね。
PDF等でダウンロードや印刷ができない方は郵送で書類を受け取ることもできるとのこと。
提出前に亡くなった場合
ちなみに「死亡一時金受取人指定に関する申請書」を提出せず亡くなった場合には、
お亡くなりになった方の加入者コード(ID)または基礎年金番号をお手元にご用意の上、ご遺族より弊社(SBIベネフィット・システムズ)のコールセンターへご連絡ください。確定拠出年金の資産の受取人となられるご遺族に死亡一時金としてご請求いただくための書類一式をお送りいたします。
出典:SBIベネフィット・システムズ 加入者が死亡したときはどのような手続きが必要ですか?
とのことです。
必要に応じて戸籍・住民票、続柄や生計維持の確認書類を添付する必要があるとのこと。
iDeCo公式にも請求時に必要な書類等は状況により異なると明記されています。
個別事情は運営管理機関へ確認をしましょう。
指定しない場合のリスクと、よくある誤解
それでは指定しない場合のリスクをみておきましょう。
民法の相続順位とは違うのは知っておきたい
iDeCoの死亡一時金は民法の法定相続ではなく、確定拠出年金法上の受取順位で決まります。
「配偶者が1/2、子が残りの1/2を等分」といった民法の配分ルールは適用されません。
ですから揉めないためにも指定しておくのが無難ですね。
死亡一時金の受取人は、通常の遺産相続と同じですか?
いいえ。 民法の法定相続人の順位とは異なります。
死亡一時金の受取人となる遺族の範囲、請求順位は、確定拠出年金法で以下のように定められています。【遺族の範囲と請求順位】
出典:JIS&T お手続きポータル
1.指定受取人
2.配偶者(内縁関係含む)
3.子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、死亡された方の収入によって生計を維持していた方
4.上記「3」の方以外で、死亡された方の収入によって生計を維持していた親族
5.子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、「3」の方に該当しない方
なお、指定受取人が先に死亡していた場合、代襲相続が発生しない扱いになるため、次順位の規定に沿って判定されます。
ちなみにiDeCoは離婚時や自己破産でも通常と違うルールだったりするんですよ。

複数受取人が同順位にいるとき
等分が原則。
支払いは代表者に一括で振り込まれる運用です。
時効に注意(5年)
請求しないまま5年が経過すると、死亡一時金としては受け取れない扱いになります。
ケースで理解:指定している場合・していない場合
ちょっとややこしいのでケースでみてみましょう。
ケースA:配偶者に指定していた
- 指定受取人が最優先で受け取る。配偶者の有無や子の有無は不問。
ケースB:指定なし、配偶者あり
- 配偶者が全額受け取る(民法のように子と按分ではない)。
ケースC:指定なし、配偶者なし、子が2人
- 子は同順位なので等分(代表者口座に振込→内部按分)。
ケースD:事実婚(内縁)
- 内縁の配偶者も配偶者に含まれ、第2順位で受け取り得る。指定しておくと確実
まとめ
今回は「iDeCoの死亡一時金受取人指定してますか?|受取順位・SBIでの指定方法・税金まで完全解説」と題してiDeCoの死亡一時金受取人指定制度についてみてきました。
iDeCoの死亡一時金は、指定受取人が最優先です。
受取順位は民法と異なるため、必ず事前指定を。
受取額は残高相当額、請求期限は5年。
税金は3年以内は相続税(非課税枠あり)、3年超~5年以内は一時所得
家族の負担を減らすため、今日から指定・確認を進めましょう。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの3社から選ぼう
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。
しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。
簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。
私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券の3択の中から決めます。
(※私が加入しているのはSBI証券です)
この3つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。
また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。
順番に見ていきましょう。
SBI証券
まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。
SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式といった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。
選択の楽しさがありますよね。
また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。
マネックス証券
次点はマネックス証券 iDeCoです。
こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。
iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。
松井証券
松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。
その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。
こちらも有力候補の一つですね。
さらに2024年8月1日(木)より投資信託の保有でポイントが貯まるようになり、現在の条件なら本命といっても良いでしょう。
総合して考えるとこの3つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。
他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・
最後まで読んでいただきありがとうございました。