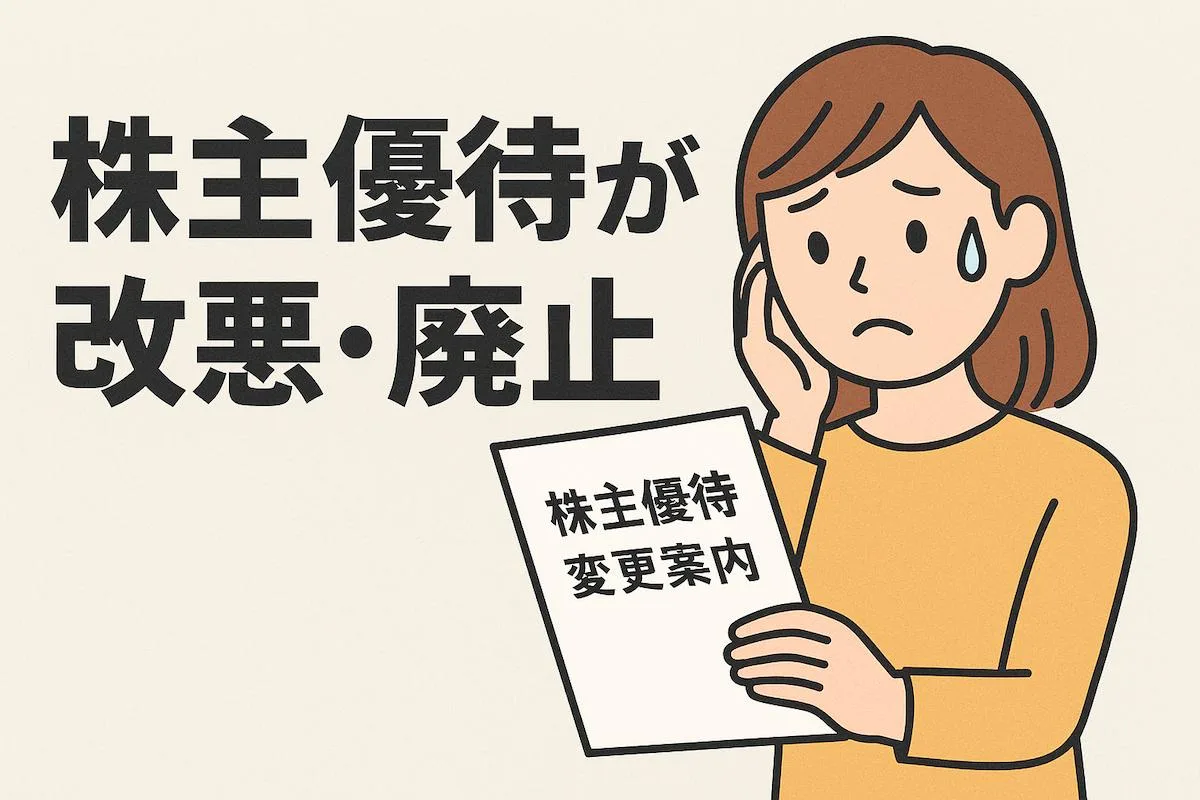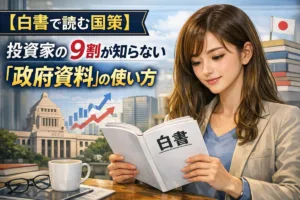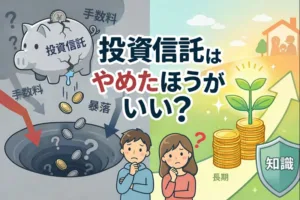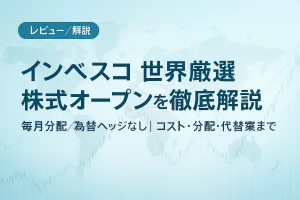ここ数年、株主優待を廃止する企業増えてきています。
また、廃止しないまでも改悪する企業が後を絶たないんですよ。
REVOLUTIONなど発表した株主優待を一度も実施せず終了する会社まで・・・
今回は株主優待目当てで買った株の株主優待が改悪・廃止されたらどうすればよいのかを考えて見ましょう。
なぜ株主優待が改悪・廃止傾向にあるのか?
まずは前提となる株主優待を改悪・廃止の傾向にあるのかを考えてみましょう。
公平な利益還元=配当・自己株取得へ“集約”の流れ
まず大きいのが、日本だけの制度である株主優待から配当への集約の流れがあります。
海外に住む投資家には株主優待は送られませんしね・・・
そのため、多くの企業が「株主の公平性」を理由に、優待から配当や自己株取得へ還元手段を集約しています。
たとえば日本取引所グループ(JPX)が、2025年3月末をもって優待を終了し、配当等に集約すると公表したのはこの流れですね。
取引所のガバナンス要請・資本効率圧力
東証はPBR1倍割れ企業に改善要請を続け、資本効率を意識した株主還元が重視されています。
優待よりも配当や自社株買いが資本政策として説明しやすいため、制度見直しが進みやすいのです
コスト上昇・制度運営負担・電子化
優待コスト(送料・発行・運営)や、電子化対応への移行負担も要因です。
四季報オンラインは優待の新設・廃止・電子化の動向を継続的に伝えています。
GMOの株主優待変更の事例:即売却
個人的にはGMOインターネットグループの株主優待改悪がかなりショックでした。
GMOは持株会社体制移行に合わせて、優待方針を配当・自己株取得中心へ再設計したとのこと。
GMOクリック証券の株式手数料完全無料化の影響もありかなり大きく改悪されました。
GMOの株主優待変更内容
今までGMOインターネットグループの株主優待は以下の内容だったんですよ。
・ビットコイン2,100円分付与(各株主に一度限り)
・GMOクリック証券の当社株式買付手数料(上限なし)
・GMOクリック証券の売買手数料キャッシュバック
・GMOインターネットグループの提供する各種サービスご利用券(5,000円)
真ん中の2つは全く利用したことはありませんが、「GMOインターネットグループの提供する各種サービスご利用券(5,000円)」が年二回もらえるのがかなりありがたかったですね。
下記のような記事を書いたくらいです笑

それが廃止になり下記の株主優待だけに変更になったのです。
GMOクリック証券の当社株式買付代金×0.03%に相当するビットコイン(上限1万円)
当社株式買付代金×0.03のみって・・・
SNSなどでみるとGMOクリック証券は手数料無料なので何度もGMOの株を売り買いしたらよいでは?って意見もありましたが、そのようなことをしない多くの方にとってあまり意味がない株主優待に改悪されたんですよ。
ビットコインでくれるのはありがたいんですけどね。

株主優待目当てで持っていたので売却
ちなみに私はGMOインターネットグループの株を株主優待目的で、かなり長い事保有していました。
実は今回の株主優待変更の方針は2025年2月に発表されていたのですが、気づいていなかったんですよ。
9月に入り、GMOインターネットグループから株主優待の手続き案内が届いてようやく知ったという。
そしてすぐ売却しました。
GMOインターネットグループの保有目的が株主優待であり、その理由がなくなったためです。
ちなみにGMOインターネットグループの株はかなり長いことマイナスでしたが、ここ数ヶ月で大きく上がり、最終的には10万円ほどのプラスに転じてくれていましたので、株主優待の変更を知らなかったのはある意味ラッキーでしたけどね笑
株主優待が「廃止・変更」になったらやること
それでは株主優待の廃止・変更になったらどうすればよいのでしょう?
やっておきたいことを見てみましょう。
会社の適時開示(TDnet/IR)で一次情報を読む
まずは適時開示を一次情報でしっかり読みましょう。
私はGMOの適時開示を完全に見落としていて、結果プラスになりましたがラッキーなだけです。
まずはしっかり情報を確認するのが大事です。
とくにチェックしたいのは以下の項目。
・何が「いつから」「なぜ」変わるのか(理由と代替策)
・保有期間要件・基準日・経過措置の有無(継続保有条件や申請期限)
GMOの変更の際はちゃんと理由・施行時期・移行措置が明記されていましたね。
還元の付け替えを数値で把握(配当・自社株買い)
次に株主優待の代替えとして配当や自社株買いを増やすというならそれをチェックしましょう。
・直近の配当予想(増配有無)
・自己株取得の規模と頻度
・合算の総還元性向イメージ
昨今は「公平な利益還元」を掲げ、優待廃止と配当強化をセットで示すケースが多いです。
GMOの場合は「自己株取得や配当による利益還元に集約することが適切」との案内でしたが、株主優待が変更となるも残るからか配当は大きく変わってはいませんでしたが・・・
トータル利回りを再計算
そのうえで以下のチェックしましょう
・旧来:配当利回り+優待価値(実勢ベース)
・新:配当利回りのみ(+将来の自社株買い期待)
優待価値はオークション相場・自家消費価値などでブレます。
実務上は保守的評価で試算するのが良いでしょう。
業績・バリュエーションを再点検
あとは本業の質のチェックです。
・収益性(営業CF、ROE/ROIC)
・PBR(東証1倍未満解消要請との整合)
・競合比較・長期戦略との合理性
優待が消えても本業の質が優れていれば、長期保有の根拠は残ります。
「売る・持つ・乗り換える」意思決定のフレームワーク
それでは実際に株主優待目当てで持っていた銘柄の「売る・そのまま持つ・乗り換える」の選択の意思決定はどうすればよいのかをまとめてみましょう。
優待依存で投資していた(クロス・優待利回り重視)
まずは株主優待依存で投資をしていた場合です。
私のGMOインターネットグループのケースですね。
基本的に売るというのが基本路線となります。
株主優待価値が消え、期待収益率(IRR)が低下。
他の“優待継続銘柄”へ乗り換えを検討しましょう。
ただし、売るタイミングは気をつけましょう。
権利落ち後の需給悪化に注意。
板と出来高、需給イベント(指数入替、決算)を確認も必要かも。
特に株主優待廃止や変更発表時は必要以上に売られるケースが多いです。
株主優待+配当+長期成長で保有していた
次は株主優待だけでなく、会社の将来性や配当目的で保有していたケースです。
この場合は、優待廃止でも配当・自社株買い強化で総還元は維持・改善の可能性を検討しましょう。
増配方針や自己株取得の継続性、資本政策の一貫性などを確認し問題なければそのまま保有というのも選択肢となります。
株主優待の変更
株主優待の変更はその変更内容を確認して判断する形となります。
最近多いのが長期保有などが株主優待の条件となるケースです。
このあたりはプラスの変更と捉えるのが良いでしょう。
長期保有条件の導入は“短期の優待狙い”を抑制する意味があり、企業も長期保有株主もプラスになる可能性があります。
また、電子化も利用のしやすさは向上、転売価値は低下の意味があり効果はありそうです。
まとめ
今回は「株主優待が「改悪・廃止」されたらどうするべきか?GMOの事例で考える」と題して株主優待の廃止や改悪について考えてみました。
優待の改悪・廃止は配当・自社株への“付け替え”で説明可能なことが多いです。
総還元(配当+自己株)と本業の質で、売る・持つ・乗り換えるを決めましょう。
保有目的が株主優待のみである場合は売却というのが最善手となりそう。