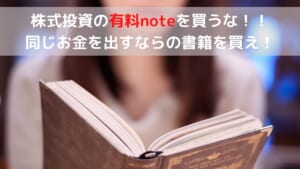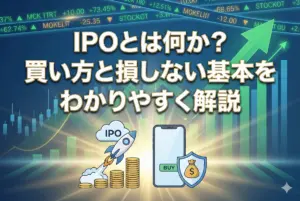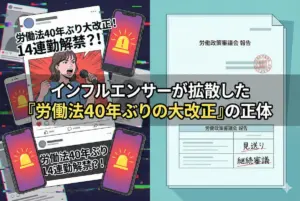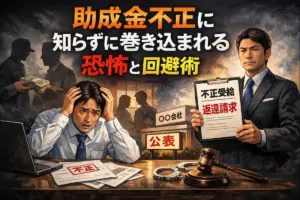自民党の総裁選でも一部候補が言及したり、立憲民主党が給付金の財源に名指しするなど再び金融所得課税の話がでてきました。
それに伴い、その原因は一部有名投資家がテレビなどで儲かったと発言するからだ!!という意見が出て本人が反論する事態にまで発展しています。
今回は投資家が目立つリスクと守り方を解説していきます。
投資家が目立つことのリスク:テスタ氏の投稿を手がかりに
投資界隈では、金融所得課税の増税が話題になるたびに「誰々が表に出たせいだ」という言説が繰り返されます。
テスタ氏はこの“風物詩”を俯瞰し、「靴磨きの少年」的な後付け相場観と同列の現象だと指摘しています。
リツィートやコメントでもテスタ氏に批判的なものもかなり見受けられますね。
ここで重要なのは、噂と制度、世論とデータ、実害と対処を切り分けて考えることです。
金融所得課税の“現在地”を一次情報で確認する
まずは金融所得課税の議論の現在地を確認しておきましょう。
いまの基本税率
上場株式等の配当・譲渡益の申告分離課税は、20.315%(所得税等15.315%+住民税5%)が基準です。
NISAやiDeCoなどの税優遇枠も以前よりは充実してきています。
ちなみに平成25年12月31日までは軽減税率があり、10%(所得税等7%+住民税3%)だったんですよ。
金融所得課税の議論
金融所得課税をあげることは数年前から何度も議論されてきました。
継続的な件というテーマなんですよ。
具体的にはなにも決まっていません。
ただし、自民党の総裁選でも一部候補が言及していることから現実味を帯びて来た感じですね。
理屈としては1億円の壁がよく議論のテーマとなっています。
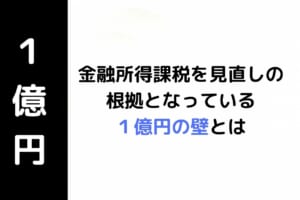
社会保険の計算に反映?
一方で、社会保険の保険料計算に金融所得を反映させる方向性は、2025年6月閣議決定の「骨太方針2025」に明記されました。
これは“税率アップ”とは別ルートで負担が増える可能性がある論点で、「増税の風潮」の実体化に近い動きと言えます。
制度設計はこれからですが、家計にはジワリ効く可能性があるため注意が必要です。
目立つことによる「実害リスク」を検証する
目立つことによる実害リスクについて考えてみましょう。
逆恨みをかいやすい
今回のテスタさんでもそうですが、逆恨みをかいやすいのは事実でしょう。
テスタさんがテレビ等で発信をしたことが、金融所得課税や社会保険の計算に反映されることが直接繋がっているとは思いません。
しかし、そう思われて逆恨みをされてしまうリスクというのはあるでしょう。
SNS由来の空き巣・強盗の実例
実例として、旅行中のリアルタイム投稿を見て空き巣に入られたケースも報じられています。
防犯の専門家は「すべての犯罪者が見ている」と警鐘。
所在地・不在情報・高額品の露出は危険です。
また、2022~23年の「ルフィ」広域強盗事件では、闇バイト型の組織的犯行が全国で起こり、資産情報の“事前聴取(アポ電)”や下見などが指摘されています。
目立つ=標的化の確率が上がる、という現実は無視できません。
「金満アピール」が招いたとされる事件
いわゆる青梅強盗殺人では、被害者の“資産家ぶり・札束ケース”が広く報じられ、「見せびらかし」行為の危険性が社会的に再確認されました。
高額当選・大金露出の古典的リスク
宝くじ高額当選者の殺害事件など、大金の露出や関係者への伝達が引き金となった痛ましい事件は過去にも複数報じられています。
人間関係のもつれ・嫉妬・依存は、投資利益の可視化でも起こり得ます。
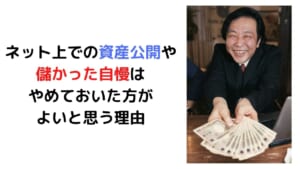
世論の摩擦:なぜ「表に出る投資家」が叩かれやすいのか
実際、表に出る投資家は叩かれやすいです。
その理由として考えられるのは以下です。
行動経済学的な背景
プロスペクト理論では、人は損失を過大評価しやすく、他人の利益を相対的損失として感じやすい傾向があります。
インフレ環境や実質賃金の伸び悩みが強い時期ほど、「投資で成功=自分の不利益」という歪んだ連想が生まれやすく、政治的にも公平負担の名の下のルール変更が支持されやすくなります。
そんな経済のタイミングでテレビやSNS等で「◯◯億儲かった」といった発言をすればターゲットに当然なりえます。
政治家はそのような情報に敏感ですから、投資に対しての課税を強化するという話が出てくるのはある意味仕方ないのです。

インフルエンサー炎上と「政策誘導」の誤解
SNSでは、一部の発言者が“増税のトリガー”にされたり、相場天井のフラグ扱いされたりします。
テスタ氏の指摘通り、毎回出てくる“風物詩”であり、事後合理化の典型です。
政策は政権の合意文書・税制大綱で動きます。
個人の露出が直接の原因になることは、ありません。
ただし、世論の受け止めに影響し、政治家が“公平負担”を掲げやすくなる副作用は否定できません。
目立つことの費用対効果:メリット、デメリット
それでは目立つことのメリット・デメリットはを整理してみましょう。
露出のメリット
目立つことのメリットは当然あります。
投資家といえば・・・という状況になれば、出版・案件獲得・講演依頼などの社会的リターンが考えられます。
また、自己整理による投資プロセスの質向上なんて副産物もありそうです。
さらに信者が多くなれば、自分の買った株等を買い上げてくれるなんてこともあります。
井村ファンド(Kaihou)なんてその典型ですね。

露出のデメリット(期待損失)
一方、デメリットもあります。
- 犯罪リスク(空き巣・強盗・フィッシング・アポ電)
- 炎上コスト(評判ダメージ、時間損失、逆恨み、嫉妬、メンタル悪化)
- 政策摩擦(“公平負担”議論に巻き込まれやすい)
などです。
結局は 期待値 = 露出による期待リターン − 露出による期待損失
で判断するしかないでしょうね。
テスタ氏や井村氏レベルになればメリットの方が大きいでしょうね。
そこまでいかないレベルだとデメリットの方が大きい気もします。
守りの実務:投資家のためのチェックリスト
ここからは今日から実行できる実務対策を考えてみましょう。
SNS・発信面
- リアルタイム位置情報の投稿をしない(旅程・不在情報・高額品は事後投稿に)。
- 資産額・現金・高額時計・住所特定につながる画像は出さない(背景・表札・窓の外景色・郵便物の宛名に注意)。
- 収益のスクショは匿名化(銘柄名・口座ID・端末固有情報のモザイク/撮影角度)。
- オフ会での情報統制:勤務先・自宅エリア・家族構成・保有銘柄集中度は“教えない”をデフォルトに。
物理セキュリティ
- 現金・高額品を自宅に置かない/見せない(青梅事件の教訓)。金庫の存在自体も“シグナル”になり得ます。
- 防犯カメラ・センサーライト・スマートロックの導入。宅配ボックスは住所以外の手掛かりを作らない設置に。
- 郵便受けの管理(投資関連の郵便物が丸見えにならないよう転送・無地化・局留などを検討)。
デジタル詐欺・アポ電対策
- 非通知・未知番号は留守電で一次フィルタ。資産や家族構成を聞く電話はすべて詐欺前提で対応。
- フィッシング:税務署・証券・NISA・マイナンバーを騙るSMS/メールはURLを踏まず公式サイトから。
- 二段階認証はTOTP系(認証アプリ)を基本。SMSは補助に。
情報露出の設計
- 「個人」⇔「発信者人格」を分離(PN運用、ドメイン・名義・請求書・登記等の切り分け)。
- スポンサー・メディア出演は住所や家族情報に触れない契約条項を明記(NDA/個人情報条項)。
- 炎上時プロトコル(コメント欄の動線整理、即時の法的相談窓口、社内・家族連絡チャート)をあらかじめ文書化。
まとめ
今回は「投資家が目立つと損をする?金融所得課税の噂と“嫉妬・空き巣・詐欺”から資産を守る具体策」と題してテスタ氏の発言をもとに投資家は目立つと損をするという話をみてきました。
個人的な意見としては、投資家が目立つことは悪いことではないと思いますが、あまり資産自慢。こんなに儲かった自慢はしないほうが良いと思います。
結局そのような発信をすることのマイナス分の方が大きい気がしますね。
マズローの欲求5段階説でいうところの「承認欲求」なんでしょうけどね・・・
にほんブログ村