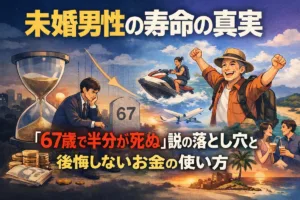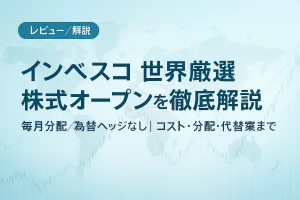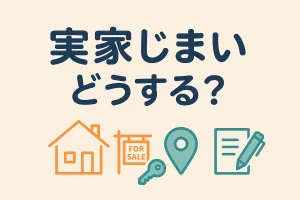NISAで投資信託へ投資をする際に設定するときにはじめての投資の方は悩んだ方もいるかもしれません。
分配金の受取り方を「受取型」もしくは「再投資型」の選択を迫られるからです。
これはつみたてNISAに限ったことではなく投資信託を特定口座で購入する場合も同様なんですけどね。
それではこれどちらを選択するのが正解なのでしょうか?
今回はこの分配金の「受取型」、「再投資型」について考えてみます。
※加筆修正しました。
分配金とは
まずはそもそもの分配金について押さえておきましょう。
分配金とは投資信託の収益などから投資家に還元するお金のことです。
儲かったから還元するってことですね。
株式投資の配当金と似た性質のものになります。
投資信託版の配当金と思っておけば良いでしょう。
分配金や配当金が多いほうが良いとは限らない
特に投資初心者の方がひっかかってしまう罠があります。
それは配当金や分配金が多いほうがよいと思っているんことです。
実はこれちょっと曲者なんです。
分配金や配当を出すと資金効率が悪くなる
配当金でもそうですが、実は成長している投資信託や株などでは分配金や配当金を出さない方が得なケースが多いのです。
これは複利効果による差なんですね。
成長している投資信託や株などでは分配金や配当金を出さない方がより複利効果を活かせるため将来的に儲かりやすいのです。
簡単に言えば儲かるなら分配金や配当に回さずに設備投資などに回したほうが収益があがります。
それが結局、投資信託の価格や株価に反映されてくるためなんですね。
配当金などを出さないほうが得な理由を詳しくこちらで解説していますので合わせて御覧ください。

分配金や配当を出すと税金面でもマイナス
つみたてNISA内では関係ありませんが、NISA外だと税金面も複利効果の邪魔となります。
例えば100,000円配当や分配金をもらう場合、100,000円に対して20,315円の税金が取られます。
つまり、実質的に受け取れる金額は79,685円となります。
対して配当や分配金をもらわない場合は利益を確定するまで(株を売却するまで)は税金が掛かりません。
つまり、その間も20,315円分が運用されることになります。
その分だけ複利効果を活かすことができるのです。(税金が繰り延べされている)
長い目で見ればこの差もかなり大きかったりします。
特別分配金(元本払戻金)には気をつけて
また、配当金と分配金は大きく違う点があります。
それは分配金は利益を出してなくても出してしまうケースがあることです。
元本から分配しちゃってるケースがあるんですね。
つまり、自分の足を食べいるタコ状態担っているのです。
つみたてNISAではありませんが、投資信託全体をみるとかなり多かったりします。
毎月分配型投資信託にはその手のものが多いですね。
商品選びの段階で分配金なしを選ぼう
金融機関も上記の件はもちろん把握していますので、つみたてNISAに採用されているような良心的なインデックスファンドは分配金なしとなっている商品がほとんどです。
ですからそれほど気にしなくても良いですが一部商品は分配金ありとなっています。
基本的には分配金なしの商品を選択したほうが成績がよくなりやすいですね。
一応注文前に買おうとしている商品が分配金を出しているのかは確認しておきましょう。
つみたてNISAのラインナップには金融庁が名指しで批判していることもあり、ラインナップされていませんが、未だに根強い人気を誇る毎月分配型はそういう点から考えてもやめておいた方が無難な商品です。詳しくは下記記事を御覧ください。

「受取型」、「再投資型」の選択について
投資信託を注文する際に「受取型」、「再投資型」を選択する必要があります。
それぞれどう違うのでしょうか。
どちらの方法もメリット・デメリットがあるんですよ。
分配金の受取型とは
分配金の受取型はそのままですが分配金をそのまま受け取ることができる方法です。
ですから運用の成果を実感することができるのはメリットかもしれません。
一方、前述したように資金効率が悪くなりますので成長している投資信託などでは成績が悪くなりがちです。
これがデメリットですね。
NISAならではの考えたいこと
NISAならではの要素もあります。
それは税金面と枠の問題です。
NISA内で受け取る分配金は税金は掛かりません。
分配金について通常ならば税金が20.315%掛かりますからこの点はかなり大きいですね。
分配金のデメリットで書いた複利効果の邪魔も発生しません。
このあたりはNISAならではのメリットと言っても良いでしょう。
また、分配金を受け取ってもNISAの非課税枠は減りません。
こちらもかなり大きいメリットとなります。
分配金の再投資型とは
次に分配金の再投資型です。
こちらは分配金として配布されたお金をそのまま再度投資信託を買う費用に回す方法です。
買う投資信託はその分配金を出した投資信託となります。
こちらのメリットは再度投資に回されますから複利効果をより受けることができることです。
つまり、お金が増える期待値が高いよってことですね。
NISAならではの考えたいこと2
ただし、NISAならではのデメリットがあります。
それは分配金分を投資信託の購入に回しますがその分はつみたてNISAの非課税枠として扱われます。
つまり、分配金がでた分だけ非課税枠が減っちゃうんですね。
これは地味に痛い所です。
NISA外での分配金の受取は再投資型が有利ですが、つみたてNISA内ではそうともいえないのがこの点にあります。
分配金は受取型と再投資型どっちがよいのか?
それでは分配金の設定は受取型と再投資型どちらがよいのでしょうか。
これは考え方次第のところもありますので難しいところではありますが、わたしの結論は以下です。
つみたてNISAやNISAなどの非課税制度外で買うならば複利効果や税金面を考えて「再投資型」一択です。
しかし、NISA内で買う場合にはそもそも税金は発生しませんので「複利効果」VS「枠の消費」の戦いとなります。
NISAの分配金まとめ
今回は「NISAの分配金は「受取型」、「再投資型」のどちらを選択すべきか」と題してつみたてNISAの分配金について見てきました。
つみたてNISAの分配金はなかなか難しい問題ですが、わたしの結論をまとめると以下のとおりです。
- NISAで枠をギリギリまで消費する方は「受取型」がおすすめ
- NISAで枠を余らせるかたは「再投資型」がおすすめ
- そもそも分配金を出さない投資信託がおすすめ
NISAに加入するなら2社が有力
NISAは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)ほど証券会社の差はありません。
選ぶ際のポイントは取扱商品と注文の仕方です。その点を加味すると下記のSBI証券、楽天証券が有力となります。
SBI証券
SBI証券はクレジットカードでの購入等は今の所できませんが、商品ラインナップや注文の仕方などは一番優れていますので楽天カードを使っていない、使わない方には筆頭候補となるでしょう
SBI証券はなにより注文の自由度がかなり高いのがいいですね。
利便性で考えるならSBI証券でしょう。
資料請求等はこちらから
楽天証券
楽天証券最大のメリットは楽天カードでつみたてNISAの投資信託等を購入できることです。
楽天カードを利用することでポイントが付きますので他の証券会社には真似がしにくいかなりのストロングポイントとなっています。
楽天カードを利用しているなら楽天証券がおすすめですね。
資料請求等はこちらから
最後まで読んでいただきありがとうございました。