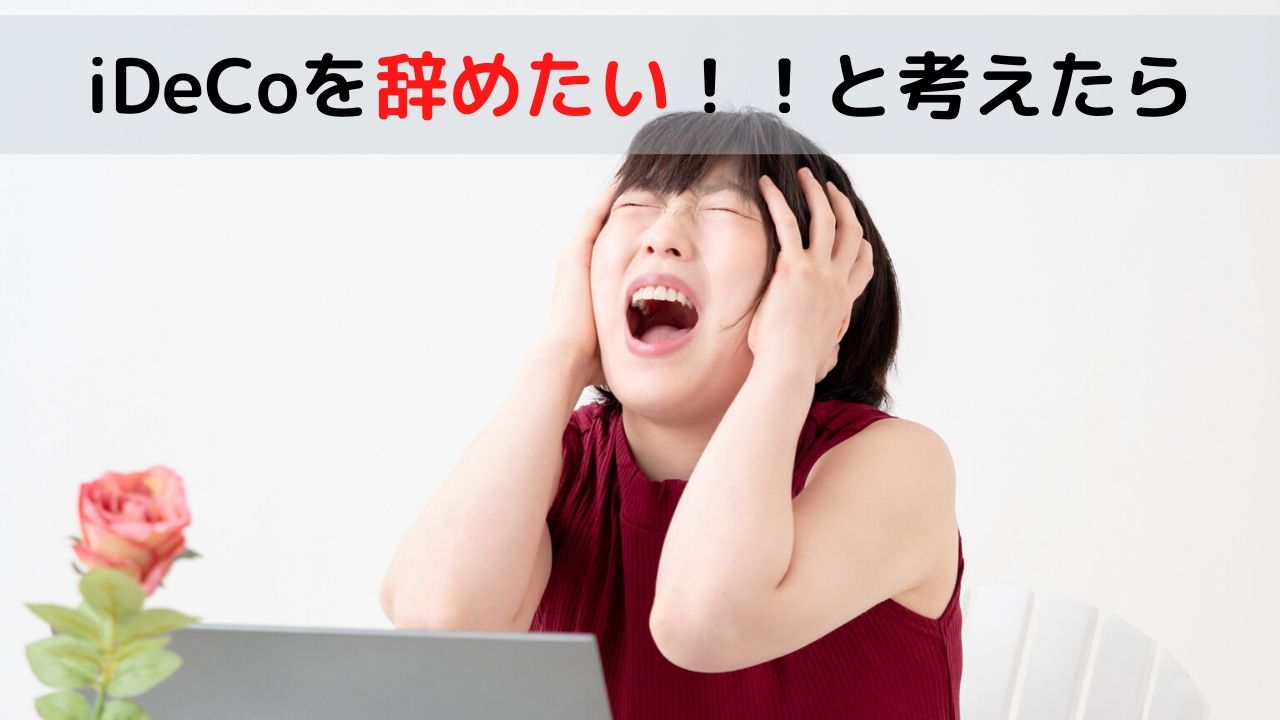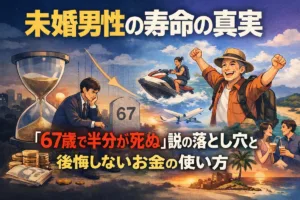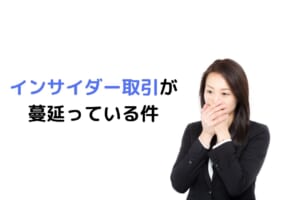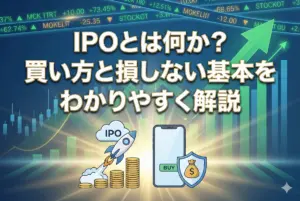相場の調子が悪くなると私のもとに来る質問があります。
それは「iDeCo(イデコ)を辞めたいけどどうしたらよい」というものです。
最近はiDeCoの改悪もありましたしね。
イデコは原則として途中解約もできませんし、引き出すこともできません。
年金目的の制度ですからね。国民年金や厚生年金が引き出せないのと理屈は同じです。
しかし、相場でどんどん資産が減っていくのは見たくないのは当然でしょう。
そんな方におすすめしたいのがリスクを減らす方法があるんですよ。
この方法を使えばみるみる資産が減っていくなんてことはありません。
今回はiDeCo(イデコ)を辞めたくなったらと題してイデコのリスク回避について見ていきます。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を途中解約して引き出しができる時
前述のようにiDeCo(イデコ)は原則的に途中解約できません。
しかし、一部例外があります。
まずはiDeCo(イデコ)を途中解約して引き出しすることができるケースから見ていきましょう。
3パターンあるんですよ。
脱退一時金がもらえるケース
まずは脱退一時金がもらえるケースです。
かなり特殊ですが下記の5つの要件を満たしている場合に脱退一時金として今までイデコで貯めた資産を受け取ることが出来ます。
1.国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けている方
iDeCo公式サイト 脱退一時金の請求手続きについて
2.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
3.通算拠出期間が3年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
4.最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
5.企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
※1.の要件は、日本国の国民年金保険料の免除を受けていることが必要であり、外国籍の方が帰国後に国民年金の加入資格がなくなった場合は、これに該当しません。
なお、脱退一時金をもらうためには条件を満たした上で加入していた記録関連運営管理機関に「脱退一時金裁定請求書」を提出することが必要となります。
障害給付金がもらえるケース
病気や怪我によって加入者や加入者であった人が高度障害に該当する場合も障害給付金として今までイデコで貯めた資産を受け取ることが出来ます。
こちらの条件もちょっとややこしいですが以下のとおりです。
政令で定める程度の障害の状態となった場合、「障害認定日」から70歳の誕生日の2日前までの期間内において、障害給付金を請求することができます
なお、障害認定日とは病気またはケガによって初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)から起算して1年6ヶ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合はその日)のことを指します。この場合の治ったとは治癒したことを指すのではなくその障害がこれ以上よくならない状況のことです。
政令っで定める程度の障害とは以下に該当する場合を指します。
(1)障害基礎年金の受給者(1級および2級の者に限る)
(2)身体障害者手帳(1級~3級までの者に限る)の交付を受けた者
(3)療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者
(4)精神保健福祉手帳(1級および2級の者に限る)の交付を受けた者
こちらも支払いを受けるには請求が必要となります
死亡一時金がもらえるケース
加入者や加入者であった方が亡くなられた場合には遺族に死亡一時金が支給されます。なお、こちらも請求が必要となります。
死亡一時金について詳しくはこちらの記事を御覧ください。
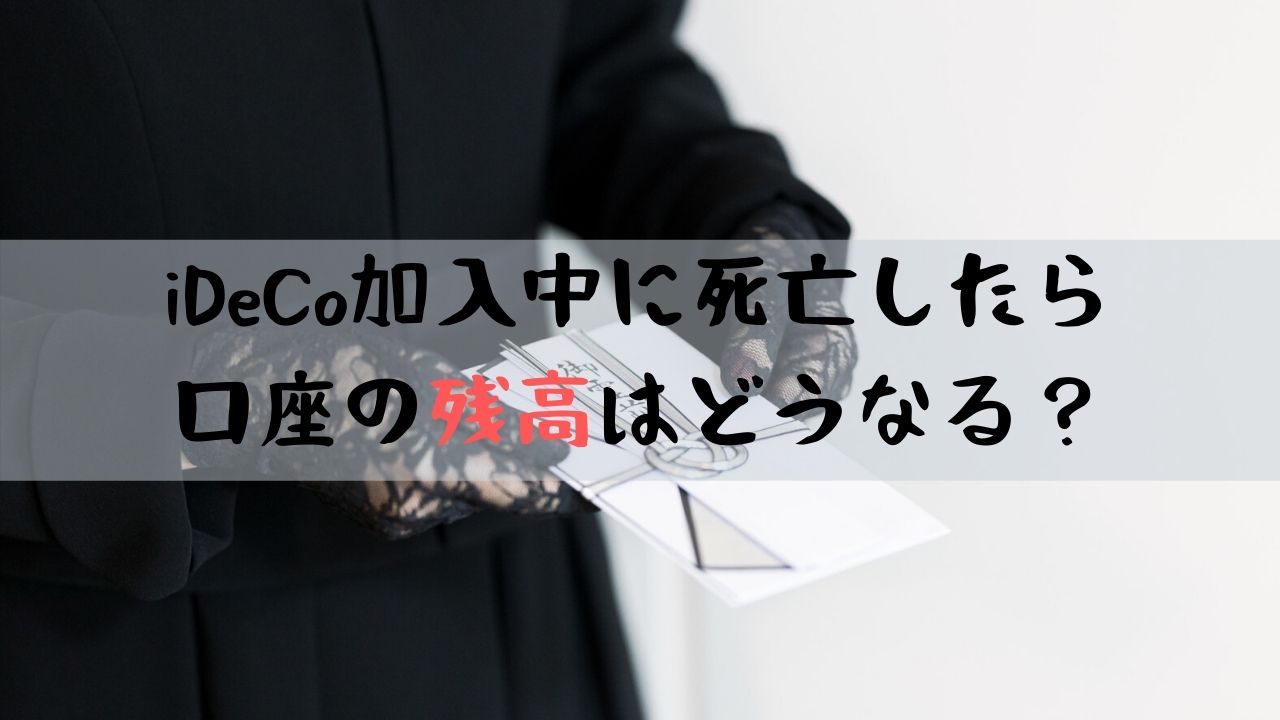
途中解約ができない場合にできるリスク回避策
上記3パターンに該当しない場合はidecoを途中で辞めることはできません。
しかし、リスク回避する方法はあります。
そのあたりを見ていきましょう。
掛け金を減らす
まずは掛け金を減らす事を考えましょう。
月5,000円までは下げることができます。
これだけでもかなり違うでしょう。
スイッチング
また、スイッチングという方法もあります。
スイッチングとは預け替えのことですでに購入して運用している投資信託等を別の投資信託等に切り替える手続きのことです。
たとえば株100%のポートフォリオを組んでいた方がリスクを減らしたい場合に株の比率を50%に下げたり、定期預金を100%にしたりすることです。
また、機動的に動ける人ならば株の調子がよいときは株の投資信託で運用して、調子が悪くなってきそうになったら定期預金などの元本保証の商品や債券などの価格が安定している商品にスイッチングするということも理論的には可能です。
おそらくイデコを辞めたいと考える時点で自分の許容範囲を超えているリスクを取っていると思われます。
まずはリスクを減らす(株やREITなどリスクが高めの資産を少なくする)ことが重要でしょうね。
スイッチングの流れ
スイッチングはこんな流れで行われます。
すでに運用している投資信託の全部または一部を一旦売却して、現金化した後、指定した運用商品を購入し直す流れですね。売却商品と数量、購入商品を指定するだけですからかなり簡単にできます。
株で言えば一旦利確して、その資金で新たな株を買うことを指定するだけで自動でやってくれると思えばよいでしょう。
スイッチングは手数料は無料だが信託財産留保額には注意
スイッチングには手数料等はほとんどの金融機関で掛かりません。無料です。(一部だけかかる金融機関もあります)
ただし、1点注意をしないといけないのが信託財産留保額です。
信託財産留保額は途中解約のペナルティーや売却手数料みたいなもの。
すべての投資信託ではありませんが、一部投資信託には掛かるものです。
信託財産留保額自体は0.3%程度ですから大きな金額ではありませんが、何度もスイッチングを行ってしまうとその都度、手数料が発生してしまいますので効率が落ちてしまうことになります。
信託財産留保額はイデコに限ったことではなく投資信託ごとに課せられていますから特定口座で買ってもつみたてNISAで買っても同じです。
ご自身が運用している商品が信託財産留保額が掛かるのか否かは目論見書などをご確認ください。
スイッチングは多少タイムラグが発生する
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)で運用する商品は基本的に投資信託を買うことになります。
投資信託は株などと違って機動性に掛けるところがありますのでスイッチングすると少しタイムラグが掛かることも知っておきましょう。
売却する商品にもよりますが10日以上掛かるケースも有るようです。特に新興国株なんかが絡んでくる投資信託は長めの期間がかかりますね。
スイッチング(預け替え)は現在保有している運用商品を売却し、売却された現金で指定された別の運用商品を購入します。運用商品は売却の指図をしてから現金化できるまで大よそ3日から5日程度かかります。また購入して投資信託を受け渡すにも同程度の日数がかかるため、すべてのお取引が完了するまで運用商品によっては10日以上かかることもあります。
SBIベネフィットシステム 「Q&Aより」
配分変更
配分変更とはすでに購入した商品はそのままで今後、毎月の掛金で買う商品やその配分を変更することを指します。
前述のような100%株の投資信託から株50%、債券50%にするような大きな変更するのは配分変更では難しいですがちょっとした微調整には最適な方法ですね。
わざわざ既存の商品を売らなくても良いですから信託財産留保額の問題等も発生しません。
配分変更の流れ
配分変更もやり方自体はかなり簡単です。
これだけです
ちなみに配分変更は締め切り前であれば何度もやり直しが効きます
配分変更は機動性には欠ける
配分変更はかなり簡単で気楽です。
しかし、実際に個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)で購入されるのは月に1度だけです。
また、その月の分からしか変わりません。
ですから早くにリスクを減らしたいと考える場合には向きませんのでスイッチングを利用するのがよいでしょう。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

まとめ
今回は「iDeCo(イデコ)を辞めたくなったら。途中解約は原則不可だがスイッチングと配分変更でリスク回避は可能」と題してイデコを辞めたいと考えた場合の話を見てきました。
基本的にイデコを辞めたいと考える時点で自分の許容を超えたリスクを取ってしまっていると思います。
そんな場合は思い切ってスイッチングや配分変更で投資先を変えてみてはいかがでしょうか?
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの3社から選ぼう
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。
しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。
簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。
私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券の3択の中から決めます。
(※私が加入しているのはSBI証券です)
この3つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。
また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。
順番に見ていきましょう。
SBI証券
まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。
SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式といった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。
選択の楽しさがありますよね。
また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。
マネックス証券
次点はマネックス証券 iDeCoです。
こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。
iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。
松井証券
松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。
その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。
こちらも有力候補の一つですね。
さらに2024年8月1日(木)より投資信託の保有でポイントが貯まるようになり、現在の条件なら本命といっても良いでしょう。
総合して考えるとこの3つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。
他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・
最後まで読んでいただきありがとうございました。