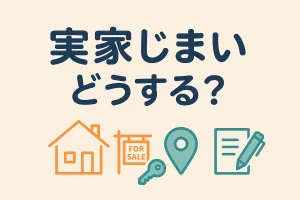会社員や公務員やフリーランスや自営業の方と比較すると老後資金はある程度確保されているといえます。
厚生年金ですし、企業年金や退職金がある会社も多いです。
しかし、それだけでは足りない方も多いのは事実です。
今回はそんな会社員や公務員の方のための老後資金対策。
とくに年金のことについて考えてみたいと思います。
自営業・フリーランス編はこちら
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//5480]
※一部加筆修正を加えました。
会社員や公務員の老後資金事情
会社員や公務員といっても働いている会社や現在の収入などによって将来の老後資金に大きな違いがあります。
退職金
まず、退職金ですが最近はソフトバンクのように退職金をださずに給料に反映する会社も多くなっています。
また、金額が昔と比べて少なくなっている会社もすくなくありません。
まずは自分がどれくらいの退職金がもらえるのかを見積もってみましょう。
会社によって計算方法等は違いますが、就業規則等の付属に退職金規定があると思いますのでそちらで計算してみてください。
大抵の会社は勤務年数と立場(役職)などによって決まるケースが多いです。
勤務年数が増えれば増えるほど上がっていく形となっている退職金制度が多いですから、退職金のことだけ考えれば1つの会社で長く働いたほうが得だったりします。
年金
年金は会社員や公務員は厚生年金ですから国民年金だけの方よりももらえる金額は多くなります。
自分が厚生年金などでいくらもらえるのかはねんきん定期便で書いてありますし、ねんきんネットでも見ることができます。
ねんきん定期便の見方はこちらをご覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//14721]
また、会社によっては企業年金が用意されているところもあります。
私が昔勤めていたといころは最近は解散するところが多くなっていますが厚生年金基金がありましたね。
退職金ともらえる年金がわかれば老後にいくら入ってくるのかがわかります。
あとは老後にいくら必要かで足りない金額がわかります。
老後に必要な金額の計算方法は下記をご覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//8339]
会社員や公務員の老後資金を増やす方法
会社員や公務員の場合には、自営業やフリーランスの方のように老後資金を作る方法の選択肢は多くはありません。
使える制度を有効活用する事が大事ですね。
年金を作る。個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)
まず有効な方法がこのサイトでも何度もご紹介している個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)です。
2017年から自営業やフリーランスだけでなくサラリーマンや公務員にも開放され知名度があがったので知ってる方も多いかもしれません。
この制度は老後資金を作るために非常に有効な方法です。
将来年金としてもらうのか、一時金として一括でもらうのか、併用するのかを選択できます。
またこちらは掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になります。
それにより所得税や住民税の節税をすることができます。
また、貰うときも一時金として貰えば退職金控除
年金として貰えば公的年金等控除が受けられますから有利に受け取ることができます。
掛け金は会社の年金等の状況によりことなります。
企業年金のない会社員の場合は最大月額23000円
企業型確定拠出年金のみに加入している会社員の場合、最大月額20000円
確定給付企業年金のみに加入している場合、確定給付企業年金と企業型確定拠出年金の両方に加入している場合の会社員の場合、最大月額12000円
公務員の場合、最大月額12000円
社会保険に加入していない個人事業所などにお勤めの場合には最大で月額68000円
(付加年金加入する場合67000円まで)
掛けることができます。
また、こちらの個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は自分で運用商品を選んでそれで得た金額を将来もらうことになります。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は途中で引き出すことができませんのでそのあたりを考えた掛け金にする必要があるでしょう。
デメリットもありますが今回紹介する制度の中でもトップクラスにお得な制度ですからぜひ積極的に活用したいところです。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)について詳しくは下記のページを御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//55]
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの5社から選ぼう
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。
しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。
簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。
私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券、大和証券、楽天証券の5択の中から決めます。
(※私が加入しているのはSBI証券です)
この5つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。
また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。
順番に見ていきましょう。
SBI証券
まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。
SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式、ひふみ年金、NYダウ、グローバル中小株、ジェイリバイブといった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。
選択の楽しさがありますよね。
また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。
[afTag id=36558]
マネックス証券
次点はマネックス証券 iDeCoです。
こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。
iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。
[afTag id=36661]
松井証券
松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。
その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。
こちらも有力候補の一つですね。
[afTag id=36658]
大和証券
大和証券 iDeCoは大手証券会社でありながら、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)にもかなり力を入れています。
他のネット証券と違い店舗が全国各地にたくさんあります。そこに魅力を感じる方にはおすすめできますね。
また、取扱商品もダイワつみたてインデックスシリーズなど信託報酬が安めの商品を取り揃えています。
[afTag id=36554]
楽天証券
楽天証券は楽天・全世界株式インデックス・ファンドや楽天・全米株式インデックス・ファンドといった自社の人気商品の取扱が大きなポイントとなっています。
この2つのファンドは人気ですね。
[afTag id=36651]
総合して考えるとこの5つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。
他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・
つみたてNISA
もう一つがつみたてNISAです。
こちらも毎月(毎日や毎週も設定できる証券会社もあります)決まった金額を預金口座から引き落とし設定した投資信託を買う仕組みです。
(年間40万円まで)
つみたてNISAは20年間は非課税で運用することができる制度です。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と似た制度ですが、大きく違う点としていつでも引き出せる点があります。
そのため強制力としてはちょっと弱めですがいざという時に使える安心感はありますよね。
そのかわりに個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)であった掛けた金額が所得控除の対象というのはありません。
つみたてNISAに加入するならこのSBI証券が有力
つみたてNISAは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)ほど証券会社の差はありません。
選ぶ際のポイントは取扱商品と注文の仕方です。その点を加味するとSBI証券が有力です。
SBI証券はクレジットカードでの購入等はできませんが、商品ラインナップや注文の仕方などは一番優れていますので楽天カードを使っていない方には筆頭候補となるでしょう(※2021年6月から三井住友カードでのつみたて購入が可能となりました)
なにより注文の自由度がかなり高いのがいいですね。
SBI証券の資料請求等はこちらから
[afTag id=46620]
トンチン年金
つぎはトンチン年金です。
これは国の制度ではありませんのでお得度は低めですが老後資金の対策の1つとしては選択肢に入るでしょう。
トンチン年金とは長生きのリスクに備えるための保険です。
加入のポイントは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の補助として考え、後述する個人年金保険と合わせて保険料控除内で加入することです。
お得度はあまり高くありませんので保険控除目的で考えるならありでしょう。
トンチン年金については詳しくは下記を御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//3684]
個人年金保険
個人年金保険も前述のトンチン年金と同様です。
国がやっている制度ではありませんのでお得度は低めです。
トンチン年金と合わせて保険料控除内で加入するのがよいでしょう。
お得度はあまり高くありませんので保険控除目的で考えるならありですね。
個人年金保険については下記を御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//3557]
会社員・公務員の老後資金対策のオススメ
私の会社員・公務員の老後資金対策のオススメは下記の組み合わせです。
まずは自身が老後にもらえる金額を確認します。
(退職金、年金など)
そのうえでいくら必要なのかを考えます。
その上で足りない部分を下記方法で補っていきます。
つみたてNISA
トンチン年金・個人年金保険
まずは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に入りましょう。
節税効果もあり、入らないと損なレベルでお得な制度です。
つぎはつみたてNISAでしょう。
年間40万まで購入することができます。
それでも余裕がある場合にはトンチン年金と個人年金保険です。
これらはお得度で言えばそこまで高くありませんので保険料控除内で加入するのがおすすめです。
これだけ用意すればかなり老後資金の対策としてよいと思います。
国民年金・厚生年金の繰り下げ
上記の対策が行われればかなり余裕のある老後のはずです。
それで国民年金や厚生年金を貰わなくても老後資金に余裕があるなら、国民年金と厚生年金の繰り下げを検討しましょう。
繰り下げとは受給開始を遅らせることです。
国民年金や厚生年金は本来ならば65歳から支給となっていますが70歳まで遅らせることができます。
(今後75歳まで繰り下げれるように改正されるとの話もあります)
70歳まで遅らせると1回でもらえる金額が通常時と比べて42%増額されます。
国民年金と厚生年金は死ぬまでもらえる終身年金ですから長生きするならばずっとお得にもらえることになります。
理想はその他の対策を行うことで70歳まで国民年金や厚生年金をもらわなくても生活できる状態にしておくことですね。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//22535]
まとめ
会社員・公務員がとるべき老後の資金対策を紹介しました。
ぜひこれら有利な制度を活用して優雅な老後生活を送ってくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
フェイスブックページ、ツイッターはじめました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです