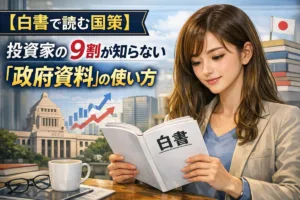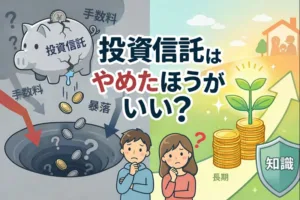最近、退職所得控除の見直しや通勤手当の非課税をなくすなど新たな増税案が続々と報道されています。
それら殆どは観測気球(国民の様子を伺う)だと思われますが、新たな観測気球が打ち上げられています。
それがNISA税です。
一時、ツイッターのトレンドにあがるなどかなりの話題ですね。
今回はNISA税について見ていきたいと思います。
NISAとは
まずは今回の話の前提となるNISAについて簡単に解説しておきましょう。
単に言えば少額の投資なら所得税や住民税が非課税で運用できる制度です。
非課税というのがミソですね。
現在はNISA(一般NISA)、つみたてNISA、ジュニアNISAと種類があり、利用できる金額、非課税で運用できる年数、投資できる商品などが異なります。
具体的には以下の条件で非課税で運用ができます。(ジュニアNISAは廃止)
- 一般NISA:年120万円まで5年、株や投資信託に投資が可能
- つみたてNISA:年40万円まで20年、金融庁が選別した投資信託等に投資が可能
金額が少額ですから富裕層向けというよりも一般の方への投資の敷居を低くしてくれる制度なんですよ。
2024年からは新NISA
さらに来年からはそれらが統一され新しいNISAとして
- つみたてNISA年40万円→120万円(つみたて投資枠)
- 一般NISA年120万円→240万円(成長投資枠)
と拡充されます。さらに非課税期間が無制限化、制度も恒久化されます。
つまり、最大で年間360万円までの投資が非課税で運用できるってことですね。(上限あり全体で1,800万円まで)
NISA税とは
それでは今回話題のNISA税というのはどういうものなのでしょう?
夕刊フジの報道
実はこれ夕刊フジの憶測の内容が広がっただけで具体的なのはないんですよ。
夕刊フジは以下のように報じています。
答申では「非課税所得」についても、「他の所得との公平性や中立性の観点から妥当であるかについて、政策的配慮の必要性も踏まえつつ注意深く検討する必要がある」としている。
参考例として通勤手当や社宅の貸与などが挙げられていることはすでに紹介したが、ほかにも少額投資への非課税を売りにしたNISAの譲渡益や配当、失業等給付、遺族基礎年金や、給付型奨学金も含まれている。出典:夕刊フジ 岸田政権「サラリーマン増税」底なし…奨学金・遺族年金・失業等給付もリストアップ 「アベノミクス以前に逆戻り」専門家警鐘
この記事自体こういう話もでてるよってレベルだけなんですが。。。。
税制調査会第27回答申
それでは夕刊フジの記事の元となった税制調査会の答申(わが国税制の現状と課題 -令和時代の構造変化と税制のあり方)ではどのようになっているのでしょう?
非課税所得等については、それぞれ制度の設けられた趣旨があり ますが、本来、所得は漏れなく、包括的に捉えられるべきであることを踏ま え、経済社会の構造変化の中で非課税等とされる意義が薄れてきていると見 られるものがある場合には、そのあり方について検討を加えることが必要です。特に、政策的要請により非課税等とされている制度については、長寿命化により、そうした所得がこれまで以上に蓄積していく可能性等に鑑みれば、 他の所得との公平性や中立性の観点から妥当であるかについて、政策的配慮の必要性も踏まえつつ注意深く検討する必要があります。
出典:税制調査会第27回答申 わが国税制の現状と課題 -令和時代の構造変化と税制のあり方ー(令和5年6月30日)
おそらくここの部分だと思われますが、NISAに課税するとは一言も書いてないんですよ。
ただし、NISAを含めた非課税所得については検討をする必要があると言ってるので今後ないとは言えないという感じというだけなのです。
NISA税がスタートするとNISAはやると損な制度
ちなみにNISAに課税されるとNISAは通常の投資よりも損な制度になります。(課税条件などにもよりますが)
なぜなら通常の特定口座で株や投資信託を利用した方が得になるからです。
NISAやつみたてNISAは損益通算できないというデメリットがあるからです。
NISAでは損失は税金計算上はないものとして取り扱われます。
現状、NISA口座内での取引は利益が出ても税金は発生しません。
しかし、逆に損失がでても他の口座で出た利益などと相殺(損益通算)できないんですよ。
また、損失の繰越も当然できません。
つまり、NISA内で出た損失は税金の計算上なかったものとされてしまうのです。
利益だけ課税され、損失が他と相殺したり、繰り越せないなんて話になればNISA口座を利用する方が損となってしますのです。
もし課税とするなら制度自体が意味がないですのでなくなるのでしょうけどね。
実現可能性はほぼない
個人的な見解として以下の理由からNISA制度に課税したり、なくなることは無いと考えます。
金融庁の方針と逆行
金融庁では「貯蓄から投資へ」というスローガンの元に投資を喚起する政策をとっています。
老後資金の心配もありますしね。
それに逆行してしまいます。
また、NISAは少額投資ですから富裕層ではなく一般の方へ投資の裾野を広げるための制度なんですよ。
株式市場が冷え込むきっかけに
また、当然、株式市場が冷え込むきっかけにもなりかねないのもあります。
新しいNISAになれば投資の枠が増えますので影響も無視はできないでしょう。
もし廃止やルール変更されるならその前に売るという売り圧力はかなりのものになると予想されます。
政府への信頼
また、政府への信頼の面でも問題です。
非課税ですよと謳って提供している仕組みを途中でちゃぶ台返しするということは政府への信頼問題にも繋がるでしょう。
もしNISA税を実現するとしてもまず制度を止めて新規加入できなくする。
既存の加入者の掛け金分はそのまま期間内非課税というのが現実的ですね。
となると上限の1,800万円まではやく埋めてしまった方が得な気もします。
まとめ
今回は「NISA税がツイッタートレンドに。NISAに課税されるようになるの??」と題してNISA税の噂についてみてきました。
現実的ではない話だと個人的には思いますね。
以前、立憲民主党の江田憲司氏がBSフジの「プライムニュース」でNISAにも金融所得課税30%をかけることを示唆したことで炎上したことがありましたが、その時と同じ流れです。
政府側としてやっちゃったな。。。って感じでしょう笑
NISAに加入するなら2社が有力
NISAは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)ほど証券会社の差はありません。
選ぶ際のポイントは取扱商品と注文の仕方です。その点を加味すると下記のSBI証券、楽天証券が有力となります。
SBI証券
SBI証券は商品ラインナップや注文の仕方などは一番優れていますので楽天カードを使っていない、使わない方には筆頭候補となるでしょう
SBI証券はなにより注文の自由度がかなり高いのがいいですね。
なお、クレジットカードでの投資信託購入時の付与ポイントは楽天証券が1%なのに対して、SBI証券は通常の三井住友カード(NL)が0.5%、 三井住友カード ゴールド(NL)
が1%、プラチナカードが2%です。
プラチナカードは年会費は55,000円(税込)ですからなかなかハードルが高いです。
しかし、ゴールドカードなら5,500円(税込)がかかりますが、年間100万円(税込)のご利用で翌年以降の年会費永年無料となっていますので無料条件クリアできる人ならおすすめできるカードです。
わたしも三井住友ゴールドカード(NL)にしましたね。
資料請求等はこちらから
[afTag id=46620]
楽天証券
楽天証券最大のメリットは楽天カードと楽天キャッシュで合計10万円までNISAの投資信託等を購入できることです。
楽天カードを利用しているなら楽天証券がおすすめですね。
資料請求等はこちらから
[afTag id=46561]
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。