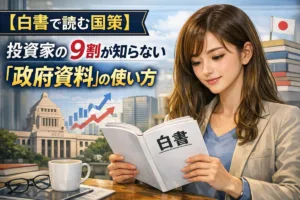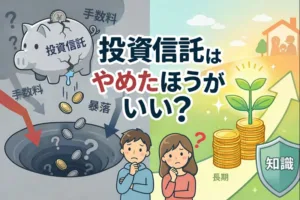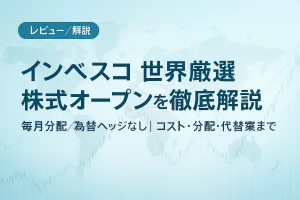「ちょっとした相場観をX(旧Twitter)でシェアしただけ」「仲間内のオンラインサロンで銘柄を推奨しただけ」
「有料noteで銘柄を推奨しただけ」
そんな軽い気持ちが、じつは金融商品取引法違反に該当することをご存じでしょうか。
とくに第38条は無登録で投資助言業を営む行為を、そして158条は風説の流布(根拠のない株価を動かす噂の拡散)を禁じています。違反すれば5年以下の懲役または500万円以下の罰金といった重い罰則のほか、ブラックリスト公表で信用を失うリスクも。
最近は本当によく見かけるようになりました・・・
そこで今回はは、個人投資家が陥りやすい典型例と最新の摘発事例を紹介しながら、今日から守れる“セルフガードルール”をチェックリスト形式でお届けします。
金融商品取引法とは?個人投資家も無関係じゃない理由
まずは前提となる金融商品取引法について簡単におさらいしておきましょう。
金融商品取引法は有価証券や金融商品の公正な取引や価格の維持、流通の円滑化を図り、経済の健全な発展や投資家の保護を目的とした法律です。
2007年に施行されました。
主なポイントは以下です。
・株式・投信・デリバティブ等の“公正で健全な取引”を守るための法律
・投資助言やファンド運用など「業」として行う場合は登録が必須
・SNS拡散による情報の非対称性が拡大し、近年は個人の摘発が増加
金融庁は2024年度行政方針で「SNS型投資詐欺・無登録助言」へ対応強化を表明しています。
第38条「無登録営業の禁止」とは
まずは第38条の条文をざっくり要約してみましょう。
報酬を得て、特定の有価証券について価値判断を助言する行為を“業”として行う場合、内閣総理大臣(財務局)への登録が必須。無登録の場合は刑事罰。
刑事罰なんですよ。
わかりやすくすると以下の要件に該当すると対象となります。
| 主な要件 | チェックポイント |
|---|---|
| 対価性 | 直接課金だけでなく、広告収入・サブスク会費も対象 |
| 特定性 | 「A社株買い」など個別銘柄なら該当しやすい |
| 継続性 | 継続的・組織的に行えば “業” と判断される可能性大 |
無登録営業の罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金(令和7年6月以降は拘禁刑へ改正予定)
個人がハマりやすい違反パターン
ここからは個人がハマりやすい違反パターンをみてみましょう。
SNSやブログでの投資助言
- Xやnoteで有料サロン・投資レポート販売を行うケース
- 「私は○○で億った」系インフルエンサーがフォロワーに個別銘柄を推奨
- 無料でも広告収入があると“対価性”を満たす可能性あり
友人・知人から資金を預かるケース
- 「副業で運用してあげるよ」と預金を集めると投資運用業(第29条)にも抵触
- 元本保証をうたえば出資法・詐欺罪リスクも
オンラインサロン等での助言ビジネス
- 月額会費で銘柄を配信→対価性+継続性=無登録営業確定
- 最近は大物YouTuberやTikTokerの摘発例が増加
インフルエンサーを全面的に信用はするな
なお、利用者としてもその手の情報には気をつけましょう。
多くの投資系インフルエンサーのレポートや有料サロンより海外の著名投資家の書籍の方が安くてためになります。
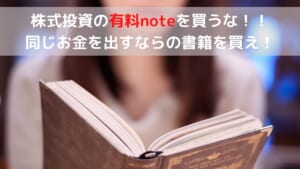

風説の流布とは?
次に風説の流布についてみていきましょう。
金融商品取引法第158条では、相場を操作する目的で「合理的根拠のない噂(風説)」を不特定多数に伝える行為を禁止しています。
条文上は「風説を流布し、偽計を用い…」という表現で、暴行・脅迫と並ぶ重い違反類型として列挙されています。
ポイントは「相場変動を図る目的」と「不特定多数への伝達」。
仲間内チャットでも数百人規模なら“不特定多数”とみなされるリスクがあります
| 規制対象 | 具体例 | 罰則(刑事)* |
|---|---|---|
| 風説の流布 | 虚偽のIR情報をSNSで拡散して株価をつり上げる | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金(2025年6月以降は拘禁刑に一本化) |
| 偽計 | 架空取引を装い出来高を水増しする取引スキーム | 同上 |
*さらに課徴金(行政罰)が加算される場合あり。
SNS時代に急増する風説流布のパターン
Pump&Dump型
自分で買い集め→虚偽情報を拡散→高値で売り抜け。
日本版Meme Stockと呼ばれる動きでも摘発例が増加。
ネガティブキャンペーン型
空売りポジションを取った上で「倒産する」など事実未確認のネガティブ情報を流布し株価を急落させる。
AI・自動生成記事型
生成AIで作ったフェイクニュースをブログ量産→広告収入を得ながら価格をかく乱。
SESCは“新類型”として監視を強化すると明言。
最新摘発事例:ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT)
最近の事例も見ておきましょう。
2024年7月26日、証券取引等監視委員会(SESC)は、HMT株を対象に根拠のない買収噂をYahoo!掲示板へ投稿し株価を操作した個人投資家に課徴金209万円を勧告。
投稿直後に株価は一時+15%急騰。違反者は保有株を売却し利益を得たが、取引履歴と掲示板ログで足がついた。
SESCは「電子掲示板・SNSは証拠が残りやすく、追跡は容易」と警告している。
合法かアウトか?グレーゾーン診断
| ケース | 判断の目安 |
|---|---|
| 業界紙の記事を引用しつつ「この材料で上がりそう」と私見を述べる | 合法:一次ソース引用+主観明示なら風説に当たらない可能性が高い |
| 未確認リークを「絶対上がる」と断定的に投稿しリツイートを促す | アウト予備軍:合理的根拠がない断定は風説認定リスク |
| IR担当者との私的会話を脚色して“関係筋”情報として有料サロン配信 | ほぼアウト:根拠不明情報+対価性+不特定多数で第158条違反の可能性大 |
ワンポイント⚠️
「投資は自己責任です」という免責文では違法性は消えません。
情報の真偽と目的が重視されるため、誤情報を流せば免責文があっても摘発対象です。
防衛策:風説の流布を避ける5カ条
風説の流布と疑われないためにも以下の点を意識するとよいでしょう。
- 一次ソースを添付(IRリリース/TDnet等)
- 推測は“あくまで個人の見解”と明記
- 数字・事実は引用元を明示
- 相場変動を狙った過度な煽り表現を避ける
- 投稿前に“3つの根拠”チェック(事実・裏付け資料・引用元)
実際にあった摘発事例
次に実際にあった摘発事例を見ていきましょう。
ここ数ヶ月でも下記の事例がありました。
| 年月 | 違反内容 | 概要 |
|---|---|---|
| 2025/7 | 風説の流布 | バイオ株HMTの虚偽情報をSNS拡散し課徴金勧告 |
| 2025/6 | 無登録投資助言 | フォロワー20万人のフィンフルエンサーが有料サロンで個別銘柄助言 |
| 2025/4 | 無登録投資顧問 | インターネット投資顧問運営者を警告 |
フィンフルエンサーってなに?
フィンフルエンサーって聞き慣れない方も見えると思いますが、特定の個人を指すわけではなく証券監督者国際機構(IOSCO)が作った造語です。
ファイナンスとインフルエンサーを組み合わせた造語で、「一般的にソーシャルメディア上で投資関連コンテンツを提供する人」を指しています。
違反しないためのチェックリスト
それでは違反しないためにどんなところに気をつければよいのでしょう?
以下の7つの点を意識してください。
- 有料/広告付きで銘柄を語っていないか?
- 「買え」「売れ」など特定銘柄を明示していないか?
- 継続的にアドバイスしていないか?
- 根拠のない噂やインサイダー情報を転載していないか?
- 金融庁/財務局サイトの“無登録業者リスト”に自分や関係者が載っていないか?
- 掲載前にファクトチェック—一次ソース(IR・TDnet)を確認したか?
- 疑わしい場合は登録業者へ外注するか、専門家に相談したか?
チェックに一つでも「✕」があれば、情報発信方法を再考しましょう。
まとめ
今回は「個人投資家必読。SNSやブログ投稿も危険?無登録営業リスクと風説の流布対策」と題して無登録営業リスクと風説の流布についてみてきました。
まとめると以下のとおりです。
- 金融商品取引法第38条は「稼げる情報」発信者にも適用される可能性
- 無登録営業も風説の流布も「知らなかった」で済まず、信用と資産を一挙に失うリスク
- 個人投資家ができる防御策は、①一次ソース確認 ②根拠と免責の明示 ③業としてなら登録か専門家連携
- 情報発信に自信がない場合は“聞く・学ぶ側”に徹し、まずは自己責任の範囲で小さく試す姿勢が安全
投資で最も高いコストは「知らなかった」ことによる損失です。法令を味方につけ、安心して長期投資に集中しましょう。