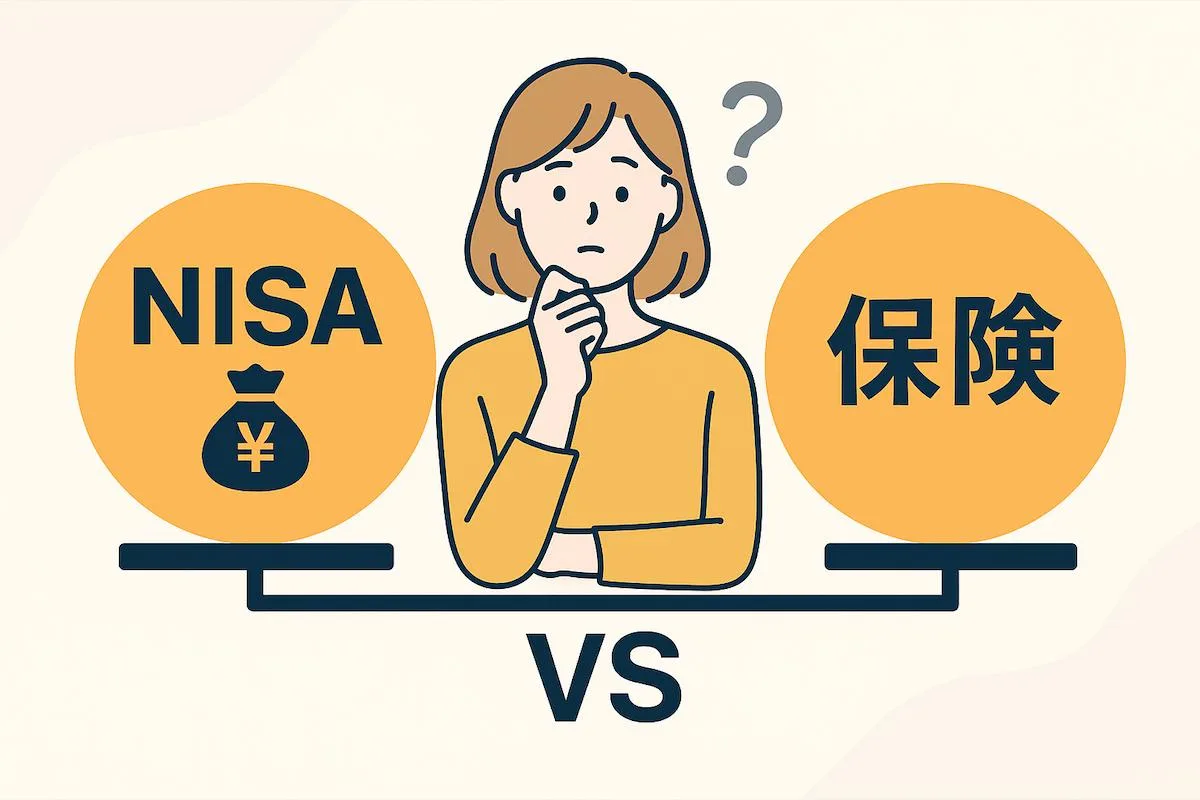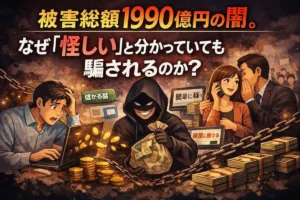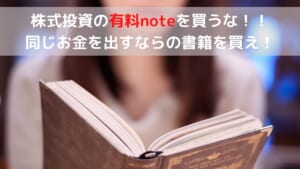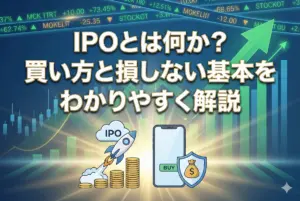ここ数年、とくに20代で「NISAは怖いから、まずは積立保険で」という声をよく聞きます。
日本経済新聞も「NISAさえ怖い20代、選ぶは積立保険(預金以上・投資未満)」という傾向を報じました。
投資の価格変動が不安、でも預金だけでは増えない。
そんな“間”を埋める選択として、積立保険が選ばれやすいわけです。
最近は以前よりも予定利率が上がっていますしね。
一方で、2024年からNISAは恒久化・非課税無期限・枠の拡大など、初心者に有利な制度に進化しています。
制度を正しく理解し、リスク管理を工夫すれば「怖い」はぐっと小さくできます。
この記事では、「NISA 怖い」と感じる理由を丁寧にほどきつつ、「積立保険 デメリット」を中立的に整理。
最後は「NISAと保険 どっち」を選ぶための判断軸をお渡しします。
NISAと積立保険の基本構造の違い(税制・運用先・流動性)
まずは前提となるNISAと積立保険の違いを見ていきましょう。
この比較だけでも積立保険よりもNISAの方がかなり有利であることはわかってもらえるかと思います。
税制
税制面はNISAが圧倒的に優遇されています。
NISA:売却益・配当が非課税。非課税保有限度額は生涯1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)、年間360万円(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)。非課税期間は無期限売却すると翌年以降に枠が復活。
積立保険:受け取り方により課税(例:一時金は一時所得として課税対象になり得る等)。税制優遇は「保険」であって「投資」とは別物。
運用先
運用先はNISAが自分で選べるのに対して、積立保険は目に見えづらいという問題があります。
NISA:投資信託・株式などから自分で選択。2024年4月から投信は「総経費率」の開示が進み、実際の負担コストを比較しやすくなりました。
積立保険:保険会社の一般勘定(主に債券運用)や特別勘定(変額)で運用。契約・維持にまつわる付加保険料などコストが内包され、投資部分の効率が見えづらい
流動性(お金の出し入れのしやすさ)
流動性もNISAが有利ですね。
NISA:多少タイムラグはあるもののいつでも売却・現金化が可能(長期保有を推奨しつつ、緊急時も柔軟)
積立保険:中途解約は解約控除等で元本割れになりやすい。外貨建・変額等は市況調整(MVA)や市場変動の影響も
【比較表】NISAと積立保険のちがい(俯瞰)
| 観点 | NISA(新) | 積立保険 |
|---|---|---|
| 税制 | 売却益・配当非課税、無期限、生涯1,800万円(成長1200)、年360万円。売却で枠復活。 | 受取方法次第で課税(例:一時所得など)。税制は「保険」として扱う。 |
| 運用先 | 投信・株式など。総経費率開示でコスト比較可。 | 保険会社の一般/特別勘定。付加保険料などコストが内包。 |
| 流動性 | いつでも売却(緊急時も柔軟)。 | 中途解約で元本割れリスク・解約控除・MVA等。 |
| 透明性 | 商品比較がしやすい。 | コストや返戻の仕組みが見えにくい。 |
| 目的適合 | 資産形成(成長取り込み) | 保障(万一に備える)。貯蓄は副次機能。 |
積立保険の主なデメリット(手数料・中途解約・運用効率など)
次に積立保険の主なデメリットを見ていきましょう。
デメリット1:見えにくい“保険コスト”が運用効率を圧迫
命保険の保険料には、純粋な保障原価に加えて付加保険料(保険会社の営業職員の人件費や、広告宣伝費等の経費の部分)が含まれます。
例えばライフネット生命の開示例では、商品・条件により保険料の約2〜3割が付加保険料に相当するケースが示されています。
投資目的で見ると、この見えにくいコストが複利効果をそぎやすいのが難点です。
※ライフネット生命の開示の件はこの記事で解説しています。

デメリット2:中途解約による元本割れリスク
多くの保険で短期解約は解約返戻金が払込総額を下回る旨が注意喚起されています。
特に払込期間中の解約では解約控除が引かれ、戻りはごくわずかという記載も。
予定どおり満了まで払える前提でないと、高コスト+低流動性が同時に効いてしまいます。
デメリット3:市場・金利・為替の影響(MVAや外貨リスク)
外貨建・低解約返戻金型・マーケットリンク型などは、金利や為替、指数の動きに応じて解約返戻金が大きく増減し得ます。
MVA(市場価格調整)の適用で、金利上昇局面の途中解約は返戻金が目減りする仕組み。
また、たとえ「元本保証」であったとしても名目ベースの話で、インフレで実質価値が目減りする可能性もあります。
長期の購買力まで保証されるわけではありません。
現在の積立保険の予定利率は国の目標インフレ率(2%)以下ですからね・・・

「NISAは怖い」と感じる理由と、その誤解・リスク管理術
次に積立保険を選んでしまう理由のNISAは怖い理由について考えて見ましょう。
投資の怖さの正体
NISAに限らず投資が怖いと感じる正体は主に3つあると言われています。
(1)価格変動(短期の上下)
(2)知識不足(何にいくら投資すべきかの不安)
(3)損失回避バイアス(損は倍怖く感じる人間の心理)
特に大きいのが損失回避性バイアス(プロスペクト理論とも呼ばれる)
これが原因で株などに勝てない人が多いとも言われていますね。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。

怖さを乗り越える仕組み化
怖さを乗り越えるカギは仕組み化です。
以下を意識して取り組むと怖さはかなり減ると思われます。
- つみたて:毎月の定額積立で価格のブレを平準化
- 分散:国内外の株式・債券に広く(最初は全世界株式のインデックス投信一択でもOK)
- 長期:非課税無期限を味方に、最低10年以上の視点
- 現金バッファ:生活防衛資金は別口座で確保(売らされるリスクを下げる)
- コスト最重視:投信は総経費率で比較(0.1%と0.5%の差が20年で効いてきます)
「暴落が怖い」よりも、何もしないでインフレに負けるほうが長期ではリスクという見方も。
“やらないリスク”にも目を向けたいところです
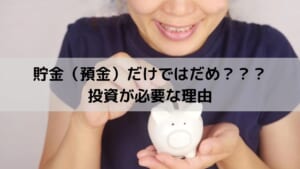
将来の資産形成におけるリスクとリターンのバランス
とはいえ保険にも良い点もあります。
保険の強み
万一に備える保障(死亡・医療・就労不能、自動車保険など)。
確率は低いが発生時の損失が大きいリスクに一点集中で効く。
投資の強み
成長の取り込み(世界経済の拡大・企業の利益成長)。長期×分散×低コストが効く。
弱点の補完
それぞれ良いところをかけ合わせるのが正解なんですよ。
この切り分けがトータルの効率を上げます。
全部保険で賄おうとするのが間違いなのです。
要は使い方次第ってことなんですよ。

保険が適しているケース/NISAが適しているケース
それでは保険が適しているケースとNISAが適しているケースをまとめてみましょう。
保険(積立型を含む)が適しているケース
- 保障が主目的(家族の生活費・住宅ローン・就労不能の備えなど)
- 途中解約の可能性が極めて低い(満了まで支払えるキャッシュフローが固い)
- 外貨建の為替・金利リスクを理解し、それでも商品特性を取りたい人(例:年金原資確保を名目ベースで優先
NISAが適しているケース
- 資産形成 初心者で、長期×分散×低コストを「仕組み化」できる人
- 流動性を確保したい人(いつでも売却可)
- インフレに負けない実質リターンを目指したい人(世界の成長を取り込む)
結論
まずは掛け捨てで必要保障を確保し、余力はNISAで育てるのが王道ですね。
まとめ
今回は「NISAは怖いから積立保険を選ぶのはおすすめしない理由」と題してNISAと積立保険について比較してみました。
まとめると
「保障は保険」「資産形成はNISA」。
と目的を切り分けて利用するのが吉ってことです。
まずは必要保障は掛け捨てで、余裕資金はNISAでコツコツ。
投資は怖いけど、やらないリスクもある。
この“地味だけど強い”基本設計が、10年後のあなたを一番守ってくれます。
NISAに加入するなら取り扱い商品が多様で、投資信託保有でポイントが貯まるSBI証券がおすすめ。