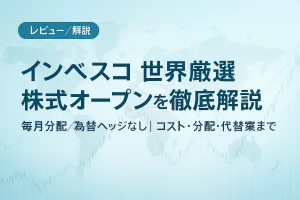人気ファンド「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」の新しいバージョンが登場します。
「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)」です。
名前のとおり、決算が年4回から年1回になった形ですね。
今回は「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)」について詳しく見ていきます。
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)の概要
まずは概要から見ていきましょう。
基本スペック
愛称:S・米国高配当株式100(成長型)
設定日:2025年9月12日(予定)
決算:原則毎年9月28日、初回は2026年9月28日
投資手法:ファミリーファンド方式でSCHDに実質投資
ベンチマーク:ダウ・ジョーンズ US ディビデンド100インデックス
為替:ヘッジなし
費用:購入時手数料なし/信託財産留保額なし/実質的な負担年0.1227%(税込)程度
(内訳:ファンド0.0627%+投資対象ETF経費0.06%程度)
出典:SBIAM「申込メモ・費用・リスク」、交付目論見書。
「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」と同じく信託報酬がかなり低いシリーズとなります。
SCHD:高配当×クオリティ重視の指数設計
本ファンドの実質的な投資対象であるSCHDは、Dow Jones U.S. Dividend 100に連動。
10年以上の連続配当を前提に、①キャッシュフロー/負債、②ROE、③配当利回り、④過去5年の配当成長率などの“質”でスクリーニングするのが特徴です。
REITは原則除外、大型株中心のバランスも持ち味。
このアプローチは「高配当“だけ”を追わない」点が魅力。
極端な高利回り銘柄に偏らず、持続可能な配当に重心を置きます
NISAは使える?
「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)」のNISAの取り扱いはどうなるのでしょう?
年4回決算型は新NISAの成長投資枠対象として案内があります。
年1回決算型(成長型)も、性質上は成長投資枠での取扱いが想定されます。
つみたて投資枠の扱いも金融庁の判断次第ですが可能性はありそうです。
複利を最大化したい人向け
この商品最大のポイントは分配の部分。
「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」は年4回の分配が原則です。
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)は交付目論見書に「信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制」と明記。
年1回の決算は行うものの、基本はファンド内で収益を再投資し、長期の複利効果を狙う設計です(市況や基準価額次第で分配が生じる可能性はあります)。
つまり、分配はあまり出さずに複利での値上がりを狙っていく商品ってことですね。
分配を出す、出さないのどちらが良いのかは好みの部分が大きいですが、より複利を活用したい方はこちらの方がおすすめですね。
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)についてはこちらで解説しております。

年1回決算型と年4回決算型、どちらが合う?
それでは「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)」と「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」のどちらを選択すればよいのか?をタイプ別に考えてみましょう。
インカム重視(定期的に分配がほしい)
まず、定期的に分配がほしい方は考えるまでもなく「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」を選択するのが良いでしょう。
「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)」などあまり分配を出さない投資信託を買っておいて、必要な分を取り崩すという考えもありですけどね。
手軽さははやりはじめから分配が決まっているタイプでしょう。
資産成長重視(複利を最大化したい)
少しでも増やしたいと考えている方は「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)」が良いでしょう。
分配抑制方針で、原則は無分配寄り。
本家(SCHD)の分配金が自動で再投資されるイメージで成長しやすくなっています。
基本的に分配金を出すよりも成長しているなら、運用に回したほうがプラスになるんですよ。

競合比較:楽天・SCHD、SBI・V(VYM連動)など
次に競合との比較を見ていきましょう。
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド
まずは直接のライバルとなりそうな商品「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド」です。
こちらもSCHDに実質投資する投資信託。
四半期決算型/資産成長型の二本立てで、NISA成長投資枠対象となっています。
こちらは楽天証券と三菱UFJ信託銀行だけでの扱いとなっていますので、現状は楽天証券なら「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド」、SBI証券なら「SBI・S・米国高配当株式ファンド」という棲み分けになっています。
信託報酬は5月に引き下げが行われ、年率0.0638%程度(税込)。
「SCHD」の経費率が0.06%ありますので、合わせると0.1238%ですね。
「SBI・S・米国高配当株式ファンド」シリーズとほぼ同水準となります。

SBI・V・米国高配当株式インデックス(VYM連動)
もう一つのライバルとなりそうなのがSBI・V・米国高配当株式インデックスです。
こちらは同じSBIの米国高配当インデックスですが、投資対象が違います。
こちらはVYMで「高配当銘柄に広く」投資をします。
SCHDはクオリティ指標での絞り込みが強く、同じ“高配当”でも性格が少し異なります。
簡単に言えばVYMはより広く、SCHDは質で勝負といった感じでしょうか。
どちらが良いのかは一概には言えず好みの問題の部分が大きいでしょう。

取り扱い金融機関
取り扱い金融機関はEDNETの提出時点では下記です
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)もSBI証券だけの取り扱いですし、こちらもその形になりそうです。
SBI証券の目玉商品の一つとして扱うんでしょうね。
想定リスクと“SCHD系”ならではの留意点
想定リスクと留意点をみていきましょう。
為替リスク(ヘッジなし)
多くの米国株ファンドがそうですが、為替リスクがどうしてもあります。
円高に振れると円換算リターンは目減りします。
逆に円安は追い風。
このあたりは事前に知っておきましょう。
指数ルールの偏り
SCHDは10年以上の配当実績+質の指標で濾過。
大型株寄りになりやすいため、市場全体とは異なる動きとなる可能性もあります。
分配抑制(成長型)
年1回決算型は原則分配を抑制。
まとめ
今回は「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)爆誕。年4回決算型との違い等を徹底解説」と題してSBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)についてみてきました。
高配当×クオリティというSCHDの設計哲学に共感できるが、分配金の再投資を自分でするのは面倒という方にはドンピシャの商品となりそうです。
逆に定期的に分配金を受け取りたい方には向きません。
SBI証券の方は幅広く投資をする「SBI・V・米国高配当株式インデックス」と合わせて悩みましょう笑
選択肢が増えるのはありがたいですね。