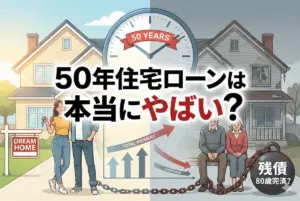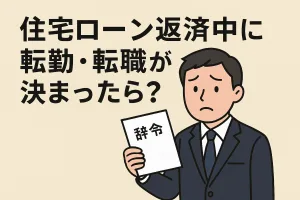2025年4月から住宅ローン減税(住宅ローン控除)の適用条件が本格的に変わります。
最大のポイントは「省エネ基準への適合が原則必須」になったこと。
これを知らずに契約・着工してしまうと、数百万円規模の控除を丸ごと逃すおそれがあります。
この記事では、改正ポイントと“落とし穴”を整理したうえで、損しないための10項目チェックリストと対策をまとめました。
2025年改正の概要
まずは2025年の改正の概要から見てみましょう。
| 項目 | 2024年まで | 2025年以降(新ルール) |
| 省エネ基準適合の要否 | 床面積や入居時期によっては不要 | 原則必須(建築確認が2024年1月以降の新築は適合必須) |
| 控除率・期間 | 年0.7%×最大13年(変更なし) | 同左。ただしZEH水準住宅は借入限度額+500万円 |
| 必要書類 | 省エネ証明があれば有利 | 証明がないと控除そのものがNG |
一番大きな違いが2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準に適合していない場合、住宅ローン減税の対象外となったことでしょう。
また、借入限度額や控除期間も住宅の性能に応じて異なります。
たとえば、省エネ基準適合住宅の場合、借入限度額は3,000万円、控除期間は13年間です。
一方、長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅では、借入限度額がそれぞれ4,500万円、3,500万円となります
そもそも「省エネ基準」とは?
断熱等性能等級4以上
一次エネルギー消費量等級4以上
これらの基準は、建物の断熱性能やエネルギー消費効率を評価するもので、2025年4月以降に新築される住宅は、これらの基準に適合することが義務付けられます。
ちなみにこの基準自体は一般的なハウスメーカー、工務店では当然にクリアしている数字だから全く問題はないかと思います。
見落としがちな“3つの落とし穴”
床面積40〜50㎡は猶予措置の落とし穴
床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅については、特例措置が適用されますが、適用条件を満たさないと控除を受けられません。
2025年12月31日までに建築確認を受けた場合は旧基準でもOKだが、一日でもずれるとアウト。
設計完了後の仕様変更は高コスト
省エネ仕様に合わせるには窓・断熱材・換気設備を再計算。着工後に気づくと追加費用が膨らみます。
また、設計時に省エネ基準への適合を確認しないと、後からの修正が難しくなり、追加費用が発生する可能性があります。
事前のすり合わせがとても大事ですね。
書類不足で確定申告NG
住宅ローン減税の申請には、省エネ基準適合を証明する書類が必要です。これらの書類が揃っていないと、控除を受けられない場合があります。
損しないための10項目チェックリスト
それではここからは損しないための10のチェックポイントを見ていきましょう。
・建築確認日を確認(2024年1月以降か)
・設計士に等級を明示的に指示(断熱4・一次エネ4以上か)
・ZEH水準、断熱等級6,断熱等級7の追加コストと控除上乗せ額を比較
・省エネ証明書の取得方法を合意書に明記
・窓種・サッシ材質(樹脂/アルミ樹脂複合)を確認
・UA値・ηAC値、C値のシミュレーション結果を受け取る
・補助金(子育てエコホーム等)申請スケジュールと申請費用、手続きを確認
・登記前に住宅家屋証明書の取得可否を確認
・入居翌年の確定申告で必要書類をリスト化
・ライフプラン(転勤/売却)まで含めた回収シミュレーション
大手ハウスメーカーの場合は当然にこれらのことをやってくれるかと思います。(担当にもよると思いますが・・・)
しかし、小さな工務店の場合にはこちら側から確認をしておかないと漏れてしまうなんてトラブルはよくあります。
必ず10項目の部分は確認してくべきでしょう。
シミュレーション:省エネ対応 vs 非対応
| ケース | 住宅種別 | 借入額 | 控除総額(13年) | 初期追加コスト | 差引メリット |
|---|---|---|---|---|---|
| A. 省エネ基準適合 | 断熱等級4 | 3,000万円 | 約273万円 | +90万円 | +183万円 |
| B. ZEH水準 | 等級5+太陽光搭載 | 3,500万円 | 約318万円 | +160万円 | +158万円 |
| C. 非適合 | 旧基準 | 3,000万円 | 0円 | 0円 | ▲273万円 |
※年0.7%、所得税住民税控除上限フル活用の場合。
上記は単純な初期費用コストと控除の部分だけで見ていますが、電気代の差も出てきますので最低ZEH基準をクリアしておくのがおすすめですね。
今現在でちょうどよいのが断熱等級6だと言われていたりもします。

これから契約する人の“5つの対策”
入居前後の補助金+税控除スケジュールを一枚表に
補助金や税控除の申請スケジュールを一覧表にまとめることで、申請漏れを防ぎ、スムーズな手続きを行うことができます。
※大手ハウスメーカーはだいたいこれをやってくれると思います。
省エネ性能計算を着手金前に実施する
設計段階で省エネ性能を確認し、必要な対策を講じることで、後からの修正を防ぎ、追加費用を抑えることができます。
特に断熱等級6や断熱等級7に上げる。気密性能(C値)の測定をして保証してもらうなどとなると費用が結構かかります。
事前に確認が必要です。できれば契約前がよいでしょう。
太陽光リースという手も
ZEH水準の住宅は、省エネ性能が高く、住宅ローン減税の控除額も増加します。
太陽光発電設備をリースで導入することで、初期費用を抑えつつ、ZEH水準を満たすことが可能です。

長期優良住宅認定で固定資産税も節税
長期優良住宅の認定を受けると、固定資産税の減額措置が適用されます。住宅ローン減税と併せて、税負担の軽減が期待できます。
金利は読めないことを意識して
変動金利がお得。固定金利のほうが安心などいろいろなことを言われるかと思います。
しかし、今後の金利動向なんかは専門家でも予想は困難なんですよ。
個人的な考えとしてはもし金利が急激に上昇しても、手持ち資金である程度繰り上げ返済とかできてしまうなら変動金利を選ぶほうが得だと考えます。
逆にそれができないなら変動金利はかなり危険ですね。
ですから固定金利を選ぶべきです。

よくある質問(FAQ)
ここからはよくある疑問点を見ていきましょう。
Q1:中古住宅を購入する場合も省エネ基準は必要?
A:中古住宅の場合、省エネ基準の適合は必須ではありません。
ただし、一定の条件を満たすと、住宅ローン減税の適用を受けることができます。
詳細は国土交通省のガイドラインをご参照ください。
Q2:建築会社が証明書を取ってくれない場合は?
A:建築会社が省エネ性能の証明書を取得しない場合でも、登録住宅性能評価機関や指定確認検査機関に依頼して、「住宅省エネルギー性能証明書」を取得することが可能です。
費用や手続きについては、各機関にお問い合わせください。
そもそも証明書を取ってくれないような建築会社に頼むべきではないと思いますけどね・・・
Q3:床面積49㎡のマンションを買ったら?
A:合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件が40㎡以上に緩和されます。
ただし、2025年12月31日までに建築確認を受けた住宅であることが条件です。
詳細は国土交通省の情報をご確認ください。
まとめ
今回は「2025年改正・住宅ローン減税の落とし穴―省エネ基準必須化で損しないチェックリスト―」と題して住宅ローン減税についてみてきました。
まとめると以下の通り。
・2025年以降の住宅ローン減税は「省エネ基準適合」が大前提。
・設計段階から断熱性能や一次エネルギー消費量の等級を確認し、必要な証明書を取得することが重要です。
・ZEH水準の住宅や長期優良住宅の認定を受けることで、控除額の増加や固定資産税の軽減など、さらなるメリットが得られます。
・チェックリストを活用し、設計・契約・入居・確定申告までの各ステップでの注意点を把握して、住宅ローン減税の適用を確実に受けましょう。
住宅ローンについては比較することが重要ですよ。
今後も税制・補助金のアップデートがあれば随時追記しますのでブックマークしておきましょう。