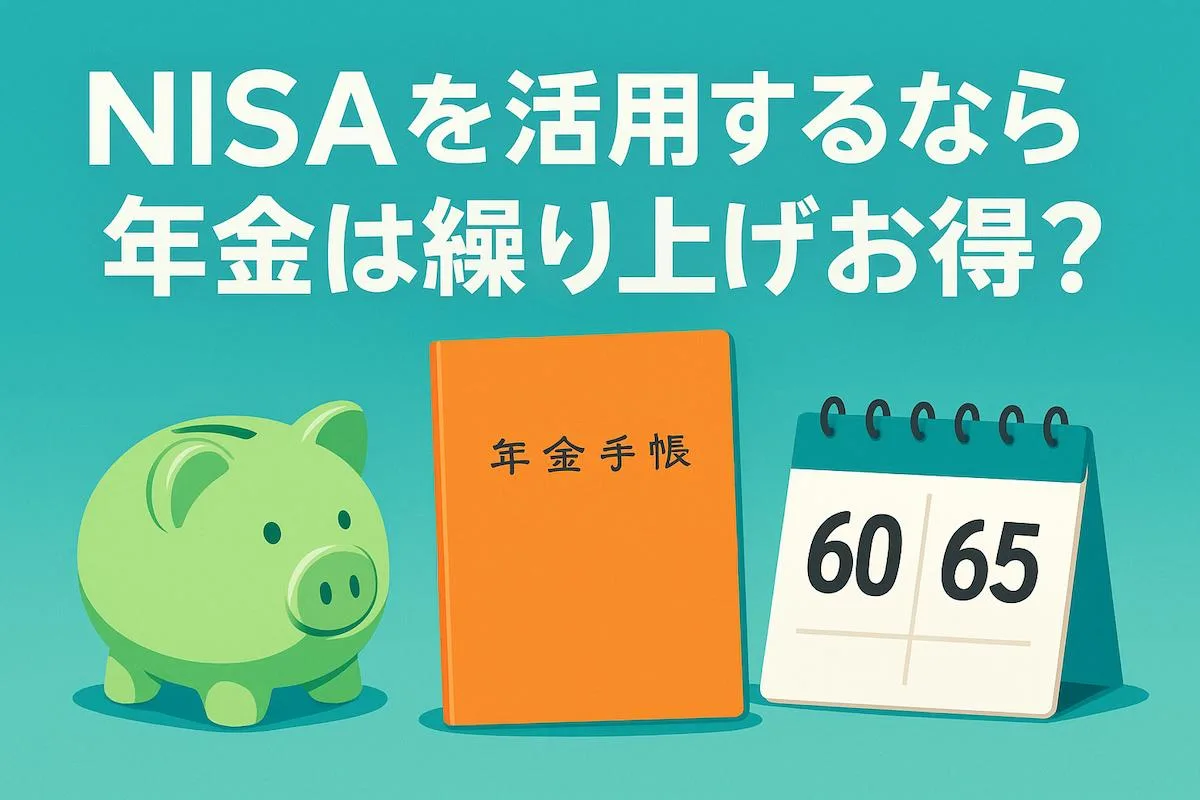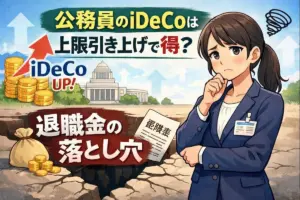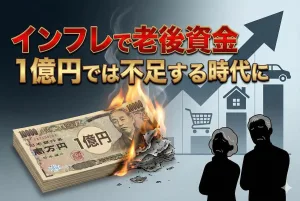先日、ちょっと興味深いXでの投稿を見かけました。
年金を繰り上げ(早く貰う)してNISAに突っ込んだほうが得という趣旨の投稿です。
確かにそれもあるかも!と思ったので今回は60歳開始×NISA運用の損益分岐点をシュミレーションしてみました。
まず制度の最新要点:繰り上げ・繰り下げ・NISA
まずは今回の話の前提となる年金の繰り上げ、繰り下げ、NISAに関する要点からみておきましょう。
年金の繰り上げ
年金の繰り上げとは簡単に言えば年金を早くもらう事ができる制度です。
そのかわりに1回で受給できる金額が減ることになります。
繰り上げ減額は0.4%/月(2022年改正)。
60歳から繰り上げ開始だと
減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
となりますので24%減となります。(65歳から貰う人と比較して)。
減額は一生固定で、一度繰り上げしてしまうと取り消し不可です。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求が原則です。
ちなみに少し古いデータですが、繰り上げを選択している人は約13%とのこと。

年金の繰り下げ
繰り下げは逆に年金を貰うのを遅らせる代わりに一回の受給額を増やす制度です。
繰り下げの増額は0.7%/月
最大75歳まで(2022年改正)繰り下げでき、その時の増額は最大+84%となります。
なお、繰り下げは基礎年金と厚生年金を別々に選べます(繰り上げは原則同時)。
なお、繰り下げを選択している方は1%程度とあまり多くはありません。

NISA
現行の新NISAは年間投資枠はつみたて120万円/成長240万円で合計360万円
また、生涯投資枠が設けられており1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円)です。
売却すると翌年に生涯投資枠が復活するという特徴もあります。
年金で使おうとすると生涯投資枠の部分がポイントになりそうですね。
※今回は制度の一次情報(日本年金機構・金融庁)を土台に、投資利回りは保守的な仮定でシミュレーションします。NISAは非課税“口座”であり、年金を直接NISAに入れるわけではありません(受け取った年金や他の資金でNISA枠を使って投資するイメージ)。
「繰り上げ×投資」か「標準65歳開始」か。ざっくり比較
それでは繰り上げしてNISAをつかって投資をするのか、そのまま標準にもらうのかを比較してみましょう。
前提:年金額は人それぞれなので65歳開始の満額を「100」とする比率で比較
受取総額の素朴な損益分岐(運用しない場合)
まずは運用しない場合の比較をしてみましょう。
- 60歳繰り上げ:月額 76(=100×(1−0.24)を60歳から生涯
- 65歳開始:月額 100を65歳から生涯
- 両者の累計が並ぶ年齢は60歳+(65−60)÷0.24 ≒ 80.8歳
つまり60歳に繰り上げした場合と65歳でもらう場合を比較するとおよそ81歳が素の損益分岐点(平均額は仮置きしても比率なので同じ結論)。
長生き(≒81歳超)想定なら65歳開始が優勢になる
60歳からの5年分をNISAで運用したら?
- 割引率=実質利回り r としてキャッシュフローの現在価値を比較。
- 想定寿命(分析地平)を95〜100歳とすると、NPVが逆転する目安の実質利回りはおおむね年4%前後。
- 寿命95歳想定→約4.0%
- 寿命100歳想定→約4.5%
つまり実質利回り4〜4.5%を長期でキープできる投資力(商品選択・リスク耐性・暴落時の継続)がある人は、60歳繰り上げ+NISAで優位になり得ます。
日本の年金を運用しているGPIFの利回りがちょうどそれくらいですので、決して無理がある数字ではないですけどね。
逆に実質3%前後までだと、65歳開始が有利になりやすい。
なお、NISAでなく、特定口座等での投資だと税金分だけ利回りがより必要になります。
NISAは非課税で有利ですが、市場リスクは消えるものではありません。
年金×NISA 簡易シミュレーション
まとめるとこんなかんじですね。
素の損益分岐(運用なし):約81歳で並ぶ(60歳で“76”を5年早く、65歳で“100”)。
運用を考慮:実質利回り次第
- 3%:65歳開始有利になりやすい
- 4〜4.5%:拮抗〜60歳繰り上げ+投資が優位
- 5%以上:60歳繰り上げ+投資が有利になりやすい(ただしボラ耐性必須)
試算はねんきんネットの見込額と突き合わせるのがおすすめです
NISA観点のチェック:本当に“繰り上げ”が必要?
もう一つの論点があります。
生涯投資枠です。
60歳になるまでに生涯投資枠が埋まっていれば、今回の話はそれほど意味がないんですよ。
ただし、NISAは売却で枠が翌年復活しますので、老後の取り崩し期も非課税メリットを活かしやすい制度設計ではあります。
ケース別「年金 繰り上げよかった」/注意が必要だった例
それではケース別で年金の繰り上げについて見ていきましょう。
よかった例(代表パターン)
繰り上げしてうまくいくパターンは以下のようなケース。
- 60〜64歳の生活費を投資以外で賄える(退職金・預貯金余力が大きい)うえ、市場の下落局面でも投資ルールを崩さないタイプ。実質4%超の長期運用を“仕組み化”している。
- 配偶者の年金・資産と合算しても生活防衛資金が厚い。年金の月額が24%減ってもキャッシュフローは崩れない。
- NISAの年360万円×5年投資計画が現実的(年金+貯蓄のミックス)。
注意が必要な例
逆に注意が必要なのはこちらのようなパターンですね。
- 在職老齢年金の支給停止ラインや税・社会保険(公的年金等控除など)を踏まえずに現金収入を増やし、手取りが想定より伸びなかった。在職老齢年金は基準緩和がありつつも就労収入との兼ね合いに注意。
- 障害・遺族関連の給付との関係を見落とした。繰り上げ後は原則として障害年金が請求できない期間が生じ得るなどの制約があり、家計の“保険性”が低下。
- 取り消し不可を軽視し、相場急落や健康悪化で後悔。繰り上げは原則撤回できません。
実務で必ず押さえる制度の勘所
繰り上げ、繰り下げの検討で意識した方がよいポイントをまとめるとは以下の通り。
- 減額率:昭和37年4月2日以降生まれは0.4%/月。60歳開始で−24%、
- 同時繰り上げの原則:基礎と厚生は原則セット。繰り下げは別々に可。
- 取り消し不可/試算推奨:請求後は変更できない。事前に年金事務所で試算を。
- 在職老齢年金の基準見直し:制度の基準・停止調整額は都度確認。
- 繰り下げオプション:0.7%/月、最大75歳まで。長生きリスクに強い。
- NISAの設計:生涯1,800万円・成長枠1,200万円・翌年枠復活
判断チェックリスト
それでは最後に判断するチェックリストを作成しましたので確認してみましょう。
寿命
まず重要なのが何歳まで生きるのかという話。
家系の健康・個人の体力。
長寿寄りなら65歳開始/繰り下げも検討したほうがよいかも。
最近は医療の進歩でより寿命が伸びるって話もありますしね。

なお、未婚男性の場合は余命が短いケースが多いので、投資などを絡めなくても繰り上げの方がオトクのケースが多くなっています。
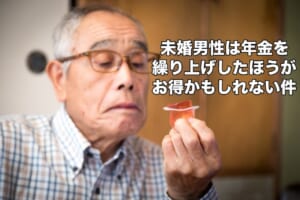
投資力
実質4%前後を“規律を持って”長期で回せるか。
暴落時の行動も含め自己点検が必要
生活防衛資金
年金24%減でも生活が揺らがないか
就労との関係
在職老齢年金や税・保険料の手取りインパクトを把握。
給付の併給関係
障害・遺族関連の制約リスクを確認
NISA枠
NISAの生涯投資枠の使用量も要確認
特定口座でもできますが、より利回りが必要に
取り消し不可
一度繰り上げを選択すると取り消しは不可
年金事務所で事前試算をしてみましょう。
まとめ
今回は「NISAを活用するなら年金は繰り上げがお得?60歳開始×NISA運用の損益分岐点をシュミレーション」とだいして繰り上げとNISAの活用について検討してみました。
まとめると
- 基本線:長生きリスクに強いのは65歳開始(or繰り下げ)。
- “攻め”の例外:実質4〜4.5%を長期で狙える運用×厚い生活防衛資金×制度理解がある人は、60歳繰り上げ+NISAで合理的になり得る。
- どちらにせよ、NISAの非課税メリットは大きい。ただし、“年金は一生の保険”という性格を忘れず、取り消し不可・併給制限・在職老齢年金の影響まで織り込んで決めましょう
どちらが正解なのかは人によるということですね。
慎重に検討してみましょう。
あとは公的年金以外の制度の活用も検討しましょう。
詳しくはこちら。