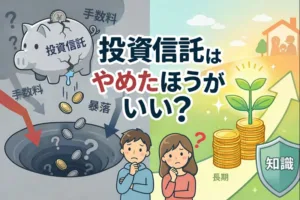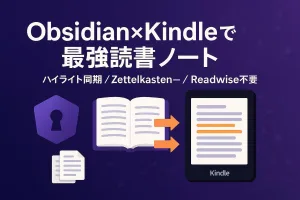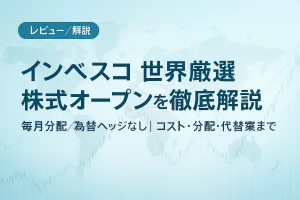日本人の平均寿命は男性81.09年、女性87.13年で世界トップレベル。
一方、高齢無職夫婦世帯の生活費は平均月約26.3万円、年金などの給付は20.9万円、年金だけでは毎月約5万円の赤字というデータが示されています。
数年前に年金だけでは老後に2000万円足りないというレポートがでて、大騒ぎとなり無かったことにされましたが、全く解決したわけでもなんでもないんですよ。
60歳代の金融資産の中央値は530万円。50代は200万円です。
毎月5万円の赤字でて、退職後30年生きることを考えれば到底足りない・・・
長生きリスクとなっているんですよ。
今回は老後貧乏の回避策について考えてみましょう。
押さえておきたい社会保険の基礎|年金・健康保険・介護保険
まずは老後のベースとなる社会保険の基礎から見ておきましょう。
| 制度 | 標準的な給付 | 留意点 |
|---|---|---|
| 厚生年金 | 平均月14.6万円(基礎年金含む) | 賃金スライド・マクロ経済スライドで実質減少リスク |
| 高齢者医療 | 70〜74歳:自己負担2割(現役並3割) | 高額療養費制度の上限は5.7万円/月(一般所得) |
| 介護保険 | 原則1割(所得により2〜3割) | 居住費・食費は全額自己負担 |
受け取れる年金
厚生年金の平均受給額は月14万6,429円(男性16.7万円・女性10.7万円)
国民年金(基礎年金)のみの場合は満額でも月6万9,000円弱です。
インフレが続いている状況ではかなり厳しい・・・
なお、年金には繰り上げ、繰り下げという論点もあります。

健康保険、介護保険
健康保険は医療費3割負担の方でも70歳以上の高額療養費上限5.7万円(一般所得層)を超えた分は還付対象。
介護保険は自己負担1〜3割+居住費・食費は全額自己負担となっています。
公的年金+高齢者医療+介護保険で“最低限”は守られるが、「ゆとりある生活費」や住宅リフォーム、治療費の上乗せ分は自助努力が必須となります。
長生きリスクを考える
日本人の平均寿命は男性81.09年、女性87.13年とご紹介しましたが、実はもう一つ知っておく必要がある数字があります。
それは60歳まで生きた人だけの統計を取ると90歳まで生きる人の割合46.4%、95歳まで生きる人の割合25.3%となっているってことです。
つまり、100歳くらいまで生きることを想定して資金計画をしておかないと詰んじゃう可能性があるんですよ。
DIE WITH ZEROという考え方
最近、死ぬまでにお金を使い切るという考え方 “DIE WITH ZERO”が流行っていますが、老後資金とのバランスが難しいところではあります。

さらに長生きになるという話も・・・
さらにここ数年AIの登場などで医療が急激に進歩しているという話もあります。
人生150年時代もそう遠くはないとの話もありますね。
そこまでの資産を残して置こうとおもうと投資をして複利を活かしまくる必要はありそうです。

資産形成の柱|iDeCoとNISA
その対策としてまず考えたいのがiDeCoとNISAです。
とりあえずこの2つを上手く活用すればほぼ老後資金に困ることはないでしょう。
iDeCoで年金を自分で“増築”する
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は簡単に言えば自分の老後生活のために老後資金を自分で作るための制度です。
具体的にはこんな感じの流れになっています。
60歳までの間に自分で決めた金額を積み立てをする
↓
その積み立てたお金で投資信託や定期預金、保険などの商品を選択して運用
↓
60歳以降にその運用した資産を受け取ることができる。
国民年金や厚生年金と合わせた年金制度の上乗せ部分を自分で運用できる制度として考えると良いでしょう。
最大のメリットは掛けた金額が全額所得控除の対象となり、掛ければ掛けるだけ所得税と住民税の節税効果があるところです。
また、運用で利益がでてもその部分について非課税となります。
受け取る時は課税対象ですが、税制優遇あり。
つまり、税金面でかなり優遇された制度ってことですね。
老後資金を考えるならまずはiDeCoを中心に検討したいですね。
例えば月2万円でもこれだけ老後資金になるんですよ。
| 掛金 | 運用利回り | 運用年数 | 受取見込み(税引前) |
|---|---|---|---|
| 月2万円 | 年4% | 30年 | 約1,350万円 |
さらに掛け金には節税効果があります。
節税効果例(所得税10%・住民税10%の場合)
・年間掛金24万円 → 所得控除4.8万円
・30年間で144万円の節税+運用益非課税
なお、掛け金の上限金額については、その方の種別によって異なります。
改正もありますので、詳しくはこちらの記事を御覧ください。

NISAで長期分散投資
老後資金だけではありませんが、もう一つ有効なのがNISAです。
少額の枠内なら非課税で運用できる制度です。
つまり、NISAの枠内なら株や投資信託で利益がでても税金が取られないんですよ。
少額と言っても2024年から年間投資枠360万円(つみたて120万+成長240万)、へ大幅拡充。(生涯非課税枠1,800万円)
非課税期間が無期限化。
売却すると翌年枠が復活し再投資可能とかなり老後資金用としても使いやすくなりました。
うまく使えばこれだけでも老後2000万円足りない問題はある程度解決できるんですよ。
モデルケース
つみたて枠:eMAXIS Slim 全世界株式を月5万円(年間60万円)
成長枠:高配当ETFや個別株を年100万円
20年間で想定利回り年4%なら元本1,600万円→約2,900万円
想定利回り年4%って聞くとそんなうまくいくのか?って疑問をお持ちの方も多いと思います。
投資等をやってない方だと預金の利息と比較して考えてしまうので、かなり高い数字になっていると思われるかもしれません。
しかし、これは現実的な数字なんですよ。
日本の年金を運用しているGPIFは運用開始後、2025年度第1四半期までで年+4.33%の利回りとなっています。
GPIFは債券半分のかなり固い運用しているですけどね。
ちなみにGPIFの運用を真似るのはかなり簡単です。詳しくはこちらの記事を御覧ください。

最大の問題となり得る住居費用
次は住居問題です。
これは下手したら最大の問題となりかねないんですよ。
住居に掛かるお金
持ち家夫婦高齢世帯の平均住居費は月1.6万円。
住宅ローンの返済が終わっていなければそれが上乗せされる形ですね。
最近は住宅価格高騰の影響もあり35年ではなく、50年で借りる人が増えているそうですから、65歳までに返し終わっている人の方がすくないかもしれませんが・・・
賃貸の場合、家賃8万円とすると老後支出は持ち家と比較して年+96万円。
30年で約2,800万円の追加負担となります。
高齢になると賃貸もなかなか借りられなくなる問題もあります。
住居の件は早めに確認しておく必要があるでしょう。
60歳までに繰り上げ返済計画を組もう
個人的には今の金利水準なら50年で借りるのは別に悪いことだとは思いません。
しかし、収入がなくなる時期までに繰り上げ返済をできる計画を組む必要はあるでしょう。(充分な資産があれば無理して繰り上げ返済不要)
難しいようなら自宅を担保にお金を借りるシニア向けのローン商品リバース・モーゲージ(詐欺的な業者もいるので注意)を活用したり、はじめから残価設定型住宅ローンの活用も検討してもよいかもしれません。
賃貸派は退職前に長期入居可物件へ住み替え検討しましょう。
今日からできる5つの黄金ルール
それでは今日からやりたい5つの黄金ルールをまとめてみました。
| 黄金ルール | 概要 | 目的 |
|---|---|---|
| 1. 家計の見える化&固定費の絞り込み | 家計簿アプリで収支を可視化し、通信費・サブスク・保険料などの固定費を月1万円以上削減 | 投資や自己投資に充てる“原資”を捻出 |
| 2. 新NISAで非課税投資を習慣化 | つみたて投資枠(上限年120万円)を軸に、全世界株インデックスなどを自動積立 | 長期・複利で老後資金を効率的に増やす |
| 3. iDeCoで“自分年金”を増築 | 掛金全額所得控除+運用益非課税+受取時控除の三重優遇を最大活用 | 公的年金の上乗せと節税を同時に達成 |
| 4. 保険の適正化でリスクとコストを最適バランス | 社会保険でカバーできる医療・死亡リスクを確認し、過剰保証を解約 | 月々の保険料を削減しつつ必要保障は確保 |
| 5. スキルアップ投資で人的資本を強化 | 資格取得・リカレント講座などに月5,000円〜1万円を投資 | 収入アップ → 投資原資アップ → 資産増大の好循環 |
順番のコツ
まず①で資金を作り、②③で“殖やす仕組み”をセットし、④で無駄をそぎ落としたうえで、⑤に再投資するイメージです。
複利を味方につける
①を早く実行できるほど、②③に回る金額と時間が増え、将来リターンも大きくなります。
無理はしない
すべて月1万円前後から始められる設計にしています。
ハードルが低く、小さく始めて大きく育てるのがポイントです。
無理な金額を設定すると続かないのでお気をつけください。
よくある質問(FAQ)
よくある質問もみておきましょう。
20代で収入が低くてもiDeCoは始めるべき?
掛金は月5,000円から。所得控除メリットが薄くても長期複利の効果は大きい。
また、受け取る際の税金が優遇される退職所得控除も掛けていた期間がベースでの計算となりますので、少額でも長く掛けた方がお得です。
無理のない金額でスタートしましょう。

新NISAとiDeCoの優先順位は?
流動性重視ならNISA、高い節税効果ならiDeCo。
まずは緊急資金6カ月分を確保したうえで、並行活用がベスト。
方向性は似た制度ですが、受け取れる時期や離婚時の扱いなど細かい違いが結構あるんですよ。
両方やっておくのがよいかもしれません。

住宅ローン完済と投資、どちらが先?
返済金利>投資期待利回りなら繰上返済優先。
今の金利水準なら繰り上げ返済するよりその分を投資に回した方が良いケースが多いかもしれません。
また、団信の保障機能も考慮しバランスを取る必要はあります。
まとめ
今回は「「老後貧乏」を回避せよ!いま動けば間に合う5つの黄金ルール」と題して老後貧乏を回避する方法について見てきました。
平均寿命87歳時代、「長生きリスク」は避けて通れません。
公的年金の平均月額夫婦ふたりで20.9万円に留まり、総務省家計調査によると無職夫婦世帯の実際の生活費は月26万円超。
毎月約5万円の赤字を埋めるには、若いうちからの資産形成が不可欠です。
まずは社会保険の仕組みと限界を押さえたうえで、iDeCoで税優遇付き年金を増築し、新NISAで非課税の長期投資を行いましょう。
併せて住居コストを最適化し、ローン繰上返済やリフォーム資金を計画的に準備することが大切です。
最後に、日々の家計改善とスキルアップ投資を通じ「人的資本」を高めれば、収入増→投資原資増→資産拡大という好循環が生まれます。
行動が早いほど複利が味方します。
今日からできる5つの黄金ルールを実践し、将来「お金の不安」から解放された豊かなセカンドライフを手に入れましょう。