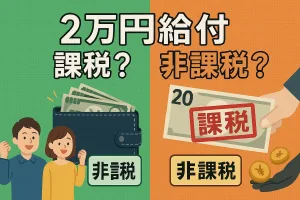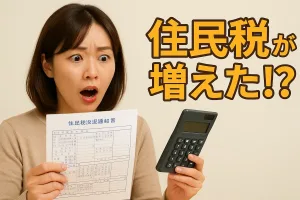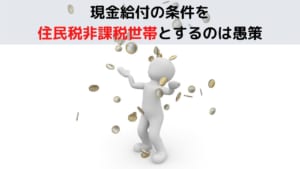最近、知り合いから離婚を考えているとのことで、シングルマザー(母子家庭)になるともらえる手当や助成制度についてご相談がありました。シングルマザーになると経済面で不安はとても大きいのではないでしょうか。
今回はそんなシングルマザー(母子家庭)向けの手当や助成金等の支援制度について見ていきたいと思います。
※記事内容は投稿時の内容になります。手当や助成内容や条件等は変更になる場合がありますので、最新情報は自治体などに直接お問い合わせください
日本人の100人に1人はシングルマザー(母子家庭)
ライフスタイルの多様化からシングルマザーを選択する人が増えています。
平成28年に行った厚生労働省の調査によると日本には123.2万人のシングルマザー(母子家庭)がいます。ちなみに父子家庭は18.7万人でした。実に国民の100人に1人近くがシングルマザー(母子家庭)なのです。また、シングルマザーのうち離婚でシングルマザーとなったのが91.1%、死別が8.0%となっています。離婚の方はシングルマザーになるまでに時間的に余裕はあるはずですからできれば今回ご紹介する制度などはある程度事前に熟知しておきたいところですね。
そんなシングルマザーの方は働くのにも様々な制限がでてきます。実際に母子家庭の平均年間収入は243万円と一般的な児童のいる平均世帯の49.2%しかありません。(出所:厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要」)
そんな状況ですからお金の面に不安があるシングルマザーの方も多いでしょう。そんな方向けの手当等をまずはみていきます。ほとんどの制度が申告制ですから申告しないともらえません。つまり、知っている方はもらえるし知らない方はもらえないという制度なのです。ぜひ知っておいてくださいね。
シングルマザー(母子家庭)向けの手当、助成金
まずはシングルマザー向けの手当や助成金を見ていきましょう。手当や助成金のほとんどは条件を満たした人が申請してようやく給付されるものになります。しっかり調べておきましょう。
児童手当
まずは児童手当です。児童手当とはシングルマザーに限らず全ての家庭を対象とした子育て世代を支援する制度です。少し前までは子ども手当という名称でしたね。児童手当の対象となるのは日本国内に住む0歳以上から中学卒業(15歳に到達してから最初の年度末)までの子どもとなります。支給額は子供の年齢により変わり以下のとおりとなります。
0歳〜3歳未満 :月15,000円
3歳〜小学校修了前:月10,000円(第一子、第二子)、月15,000円(第三子以降)
中学生 : 月10,000円
なお、児童手当には所得制限が設けられており、年間の所得が約960万円を越える世帯の子供に対しては、支給金額が月5,000円とされています(2019年以降については廃止が検討されています)
支給日
支給月は2月(10月〜1月分)、6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月)です。実際に支給される日にちは自治体により異なりますのでお住まいの自治体にお問い合わせください。
児童手当の支給を受ける際の注意点
児童手当は毎年6月1日に条件を満たしているのかを判定します。毎年市役所等から現況届が郵送されてきますのでそれを記載して手続きを忘れないようにしましょう。また、引越しなどをする際にも届け出が必要になりますので忘れないようにしましょう。
詳しくはこちらを御覧ください。内閣府「児童手当制度の概要」
児童扶養手当
次は児童扶養手当です。児童扶養手当とは両親の離婚などにより、子の父又は母と一緒に生活していないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。支給は、子どもの年齢が0歳から18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの間にある世帯が対象になります。児童扶養手当等の支給額は自動物価スライド制が採用されているので毎年金額が変わります。平成30年4月分からは下記の通りです。
| 対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
| 1人目 | 42,500円 | 42,490円から10,030円まで (所得に応じて10円刻み) |
| 2人目 | 10,040円 | 10,030円から5,020円まで (所得に応じて10円刻み) |
| 3人目以降 (1人につき) |
6,020円 | 6,010円から3,010円まで (所得に応じて10円刻み) |
支給日
支給月は4月(12月〜3月分)、8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月)です。実際に支給される日にちは自治体により異なりますのでお住まいの自治体にお問い合わせください。
支給制限
手当を受ける人の前年中の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。 また、同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。
| 扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 所得額 | 所得額 | 所得額 | |
| 0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
| 1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
| 2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
| 3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
| 4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
| 5人 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
詳しくはこちらを御覧ください。厚生労働省「児童扶養手当について」
児童育成手当
自治体によっては独自に別途手当を支給しているところもあります。例えば東京都は児童育成手当という制度があり、児童1人につき月額13,500円が支給されます。住んでいる自治体に確認してみましょう。
母子家庭の住居手当
こちらも自治体によりますが、母子家庭や父子家庭に住宅手当や家賃補助を行っているところもあります。住んでいる自治体に確認してみましょう。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者に対して支給される国の手当です。支給要件としては20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
支給金額は1級 51,700円、2級 34,430円
支給日
支給月は4月(12月〜3月分)、8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月)です。
ひとり親家族等医療費助成制度
ひとり親家族等医療費助成制度は国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成する制度です。こちらも自治体ごとの制度となっており内容も微妙に異なります。住んでいる自治体に確認してみましょう。
子ども医療費助成制度
子どもがケガをしたり、病気になった時に、健康保険証を使って病院などで治療を受けたり、薬をもらったときに窓口で支払う自己負担分を助成する制度です。こちらも自治体ごとの制度となっており内容も微妙に異なります。住んでいる自治体に確認してみましょう。
離婚の場合に知っておきたい制度
離婚してシングルマザーになる場合、年金分割制度を知っておきましょう。例えば、専業主婦は第3号被保険者という立場で年金に加入しています。保険料を払っていないのに将来もらえますのである意味優遇されているのですが、問題となるのが離婚したときです。元夫と比較してもらえる年金が少なくなってしまうのです。また、パートなど給料が比較的低めの仕事をしている場合も同様です。前述のように年金は給料額をベースに決まりますから不利となります。しかし、この年金分割という制度を使うとそれを解消することができるかもしれません。これも知らずに手続きを取らないとそのまま損をすることになります。ぜひ知っておきましょう。
やり方は2つあります。
合意分割制度
まずは合意分割制度です。元夫と合意もしくは裁判で按分割合を決めてもらってそれを元に年金を分ける方法です。
具体的には下記のようなルールとなっています。
離婚等をした場合に、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
- 婚姻期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
- 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
出所:日本転年金機構 年金分割
3号分割制度
合意できない場合このようなせいどがあります。合意とか関係なく平成20年5月1日以後の部分については年金を半分にすることができるのです。
平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
出所:日本転年金機構 年金分割
両制度とも期限が離婚した時などから2年以内ですから該当する方は忘れずに手続きしておきましょう。
年金分割について詳しくはこちらの記事も御覧ください、
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//24376]
死別時の場合に知っておきたい制度
死別の場合にはこのような制度があることを知っておきましょう。遺族年金です。遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は国民年金分の遺族年金にあたります。
| 国民年金(遺族基礎年金) | ||
|---|---|---|
| 支給要件 | ★ | 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。) |
| ※ | ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 | |
| 対象者 | ★死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある配偶者 (2)子子とは次の者に限ります
|
|
| 年金額 (平成30年4月分から) |
779,300円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,300円
|
|
出所:日本年金機構「遺族基礎年金」
遺族厚生年金
遺族厚生年金は名前の通り厚生年金分の遺族年金にあたります。サラリーマンの方などはこちらも該当してきます。
| 厚生年金保険(遺族厚生年金) | |
|---|---|
| 支給要件 |
|
| 対象者 | 死亡した者によって生計を維持されていた、
※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。 ※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。 |
出所:日本年金機構「遺族厚生年金」
遺族年金に関してはこちらの記事も御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//23434]
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//29610]
寡婦控除
納税者自身が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。
一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
- (1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
- (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
- (1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
- (2) 扶養親族である子がいる人
- (3) 合計所得金額が500万円以下であること。
出所:国税庁「寡婦控除」
控除の金額
一般:27万円
特別:35万円
なお、寡婦控除は2020年から条件等が変更になります。詳しくはこちらの記事を御覧ください。
共通の知っておきたい制度
他にも様々な制度があります。
国民年金・国民健康保険の免除
国民年金や国民健康保険は所得が少ない場合に減免措置があります。最寄りの市役所等で相談してみてください。相談しないとそのままですから忘れずに。
住民税非課税
所得など条件がありますが、住民税非課税世帯になると様々な免除措置があります。こちらも確認しておきましょう。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//16348]
交通機関の割引
JRなどの交通機関で一人親家庭向けに割引制度が実施されているケースがあります。交通機関により内容は異なりますのでお問い合わせください。
上下水道の減免
児童扶養手当を受けている場合には上下水道の減免措置が受けられる制度がある自治体があります。住んでいる自治体に確認してみましょう。
粗大ごみ処理手数料の減免
こちらも同様に児童扶養手当を受けている場合には粗大ゴミ処理手数料の減免措置が受けられる制度がある自治体があります。住んでいる自治体に確認してみましょう。
保育・幼児教育
保育幼児教育については消費税増税に合わせて2019年10月から無償化が始まります。母子家庭の場合には自治体によりすでに減免措置が自治体もありますのでこちらも住んでいる自治体に確認してみましょう。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//17808]
生活保護
生活保護とは資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。自治体により対応がかなり違いますのでこちらも住んでいる自治体に確認してみましょう。
まとめ
今回は「シングルマザーの方必見。母子家庭向けの手当、助成金等の支援制度、知っておきたい知識まとめ」と題してシングルマザーの方が知っておきたい手当などの制度、知識についてまとめてみました。
ほとんどの制度が知っていて申請しないと使えないですからまずはしっかりどういう制度があるのか知り、使えるものは申請するようにしましょうね。
また、今回ご紹介した以外にもシングルマザーに関係なく使えるお金がもらえる制度などもありますのでこちらも合わせてチェックしておきたいところ。詳しくは下記の記事を御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//11470]
また、単身世帯の場合老後のことも早めに考えておきたいところです。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//13975]
読んでいただきありがとうございました。
フェイスブックページ、ツイッターはじめました。
「いいね」、「フォロー」してくれると嬉しいです。