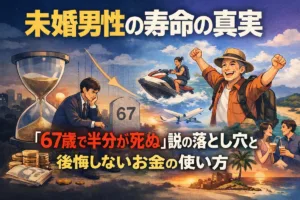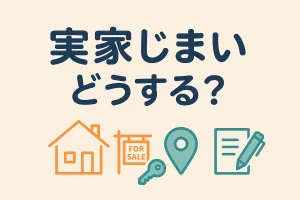読者様から以下のようなご質問をいただきました。(個人情報保護のため一部要約、ぼかし)
結婚後のNISAで考えたいこと
NISAは少額から投資を支援するための非課税制度です。
とくにつみたて投資枠(旧つみたてNISA)は金融庁が選別した投資信託を非課税で運用できるんですよ。
普通に特定口座で投資信託を買うと利益に対して20.315%が掛かりますので非課税なのはかなり大きなメリットです。
ただし、いくつか考える必要があります。
結婚後の財産は夫婦の共有
まず、考えなければいけないのが結婚後の財産は共有であるということ。
婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産は「共有の財産」として扱われるんですよ。
名義がどちらとかは基本的に関係ないんです。
ですから夫婦どちらかが掛けたNISAやつみたてNISAも共有の財産という考えとなります。(結婚前のものは別)
つまり、結婚後もNISAを継続するということは、結婚後は夫婦の共有の財産を積み立てるということですね。
そこで重要になってくるのが配偶者の考えです。
NISAは長期的に考えれば勝つ可能性が高いと言ってもリスクのある投資ですから、夫婦どちらかが反対ならやめた方がよいかもしれません。
知り合いでも奥さんは乗り気なんだけど旦那さんがどうしても投資は怖いといってもiDeCoもNISAも始められない方が見えますね。
そういうケースもありますから結婚前にしっかりそのあたりも話し合っておくと良いでしょう。
周りを見ていてもお金の価値観が合わない人は続かない傾向が強いですしね・・・
仲の良いときはそれほど気にならないのでしょうが、不仲になるとお金の話は大きくなってきます。
離婚なんて話になれば共有財産ですから、NISA分も基本的に分ける形となります。
ですからしっかりあらかじめ話し合っておくべきですね。
配偶者も同様の考えなら枠が2倍に
逆に言えば配偶者がつみたてNISAなどに賛成できる方ならば有利に利用が可能です。
NISAは税制優遇があるため、上限が1人あたり年間360万円(生涯1800万円)までしか利用ができないように制限があります。
しかし、夫婦ふたりで加入すれば生涯で合計3,600万円まで利用できることになりますからね。
かなり有利に老後資金の準備ができるようになります。
夫婦二人で掛ければ老後資金問題解決?
例えば夫婦ふたりで月5万円ずつ合計10万円掛けた場合で考えてみましょう。
公的年金の積立金の管理・運用を行う機関GPIFの運用成績(2023年末)は運用開始からの年率平均+4.36%です。
仮にその利率と同様に20年の間、月10万円の積立運用できれば3,820万円となります。
夫婦ふたりの生涯上限3,600万円(一人1,800万円)まで積み上がる30年なら7,404万円となります。
さらにそこから運用だけ続けて40年ころには1億円超えてしまうんですね。
しかも非課税です。
あくまで運用利率4.36%の場合の数字ではありますが、これだけで少し前に話題となった老後生活2,000万円足りない問題が解決しちゃうんですよね。
ちなみに後述しているようにGPIFと同様の運用をすること自体はまったく難しくありません。
投資の素人の方でも可能だったりします。
王道の投資をしているんですよ。
なお、上記のようなシュミレーションは金融庁のWEBサイトで簡単にできます。
試してみてくださいね。
夫婦でアセットアロケーションを考えよう
後でもめないように夫婦ふたり分の投資を合わせてアセットアロケーション(資産配分)などを考えてもよいかもせん。
前述した公的年金の積立金の管理・運用を行う機関のGPIF(年金積立管理運用独立行政法人) と同じ運用は容易です。
以下の記事にあるようなかなりわかりやすいアセットアロケーションを組んでいるので真似も容易なんですよ。

iDeCoも合わせて考えよう
つみたてNISAを同様に税制優遇のある制度としてiDeCo(個人型確定拠出年金/イデコ)という制度もあります。
こちらは60歳まで途中解約ができないという癖があるものの、つみたてNISAよりも更に有利な所得税と住民税の節税効果があります。
イデコも1人あたりの上限がありますのつみたてNISAとも合わせて検討しましょう。
なお、イデコの場合には節税効果の部分が大きいですから所得がより大きい方が掛けた方がお得ですね。
そのあたりも含めて検討してください。


まとめ
今回は「結婚したら独身時から続けているNISAをどうするのが良いのかを考える」と題して結婚後のNISAについてみてきました。
まとめると以下の通り。
ぜひ夫婦で話し合ってくださいね。
NISAに加入するなら
NISAは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)ほど証券会社の差はありません。
金融機関で違いとなるのは取扱商品と注文の仕方、ポイント制度です。
その点を加味すると下記のSBI証券が有力となります。
私もSBI証券でやっていますね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。