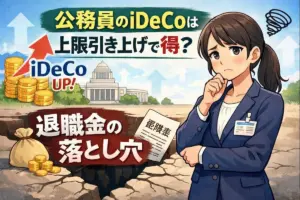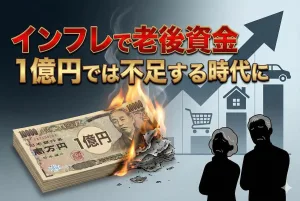公的年金の積立金の管理・運用を行う機関のGPIF(年金積立管理運用独立行政法人)が2024年度第一四半期の運用実績を発表。
+3.65%、+8兆-9,732億円となっています。
かなり順調に増えていますね。
GPIFは四半期ごとに運用実績を発表しており、マイナスを計上すると毎回そうですが、年金を溶かした的な報道や年金が破綻するって話までされている状況です。
テレビに出ている自称経済評論家の中には日銀がETF買う話と混同している方もいます。
また、多くの報道はほらみたことか、株なんかで運用するからだ・・・ってニュアンスとなっています。
逆に収益が出ているときはほとんど報道されていませんので年金で集めたお金を国が溶かしていると勘違いしてる方が多いです。
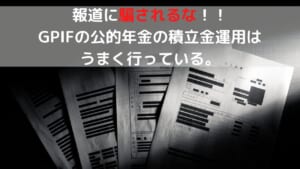
しかし、GPIFはもちろんトータルでみてかなりの利益をあげていますし、個人投資家のお手本となるようなわかりやすいインデックス投資をしているんですよ。
今回はご質問をいただきましたので私がおすすめする4社のiDeCoでGPIFと同じような運用をする方法を具体的にご紹介します。GPIFの運用方法はiDeCo(個人型確定拠出年金)のような老後資金を準備する仕組みとはとても相性が良いのです。
年金を運用するという意味では目的はGPIFもiDeCoも同じですしね。
GPIFの運用
それではまずはGPIFがどのような運用をしているのかを見てみましょう。
GPIFの実績(2024年度第一四半期)

出所:年金積立管理運用独立行政法人 より
GPIFは2002年度から運用を開始して2024年度第一四半期までに162.8兆円を稼ぎ出しています。
これは年率に換算すると4.47%。
年に4%以上増やしてくれているのです。
この成績はリーマン・ショックや新型コロナウィルスでの大暴落が含まれていますからなかなかの成績でしょう。
GPIFのアセットアロケーション

出所:年金積立管理運用独立行政法人より
GPIFはかなりわかりやすいアセットアロケーション(資産配分)をしています。
国内債券25%+-7%
国内株式25%+-8%
外国債券25%+-6%
外国株式25%+-7%
国内債券、国内株式、外国債券、外国株式をそれぞれ25%ずつを基本としています。
分散することによってリスクを低減させているのです。
これは金融庁は個人投資家に「長期」「分散」投資を勧めていますが、その内容にそのまま合致しているんですよ。
GPIFがこの比率にしている理由はわかりませんが、おそらくかなり厳密なシュミレーションの結果リスクとリターンのバランスがよくなるのがこの比率なのでしょう。
ですからそれを真似るのは理にかなっているといえるのかもしれません。
ちなみに具体的な保有銘柄も公開しているんですよ。

2024年第一四半期の収益状況
実際に2024年第一四半期は+3.65%ですが、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式別でみると収益が全然ちがっています。
国内債券: -2.39%
国内株式:+5.50%
外国債券:+1.75%
外国株式:+9.96%
2024年は外国株式と国内株式が大きく収益をあげている状況ですね。
これだけみると外国株式だけ買っておけばよいと思う方も多いでしょう。
しかし、時期によってどの分野がよいのかは大きく異なるのです。
たとえば新型コロナウィルスの影響をもろに受けた2019年度は以下の成績です。
国内債券: -0.36%
国内株式:-9.71%
外国債券:+3.55%
外国株式:-13.08%
こちらは外国株式と国内株式が大きく足を引っ張っているのがわかるでしょう。
SBI証券のiDeCoでGPIFのマネをする
それでは私がおすすめする4社のiDeCoで実際にGPIFと同じような運用をする方法をご紹介しましょう。
まずはSBI証券(セレクトプラン)です。
iFree 年金バランスを買う
SBI証券で一番簡単にGPIF を真似た運用するなら大和アセットマネジメントの「iFree 年金バランス」を買うのがおすすめです。
iFree 年金バランス
「iFree 年金バランス」はそもそものコンセプトが「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標とします。」なんですよ。
つまり、今回テーマとしているGPIFと同じような運用をすることを目的とした投資信託なのです。
ですから「iFree 年金バランス」を1本だけ買えばGPIFとほぼ同じ投資が可能なのです。
今後、GPIFがアセットアロケーションを変更してもそれに合わせて投資先を変えてくれるでしょうからそのあたりも安心ですね。
実際、過去の成績もGPIFにかなり近いものなっていますね。
信託報酬率も低めに設定されています。
4つの分野ごとに
次は国内債券、国内株式、外国債券、外国株式を別に購入する方法です。
1つで4つに分散投資をする場合と比べてのメリットとしてはそれぞれの収益がわかりやすいということでしょう。
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
この4つの組み合わせでGPIFがベンチマークとしている4つの資産とも同じベンチマークとすることが可能です。
これを25%ずつ購入すればほぼGPIFと同じ投資先とすることができます。
ちなみに前述の「iFree 年金バランス」を利用する場合と比較して信託報酬率も低くなりますね。
オリジナルプランの方
なお、オリジナルプランの方は以下の5本を利用しましょう。
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
DCニッセイ外国株式インデックス
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
外国株式はGPIFがベンチマークとしているのはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)です。
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)をベンチマークとした商品はオリジナルプランで存在していないため、先進国株式の「DCニッセイ外国株式インデックス」と新興国株式の「三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド」を組み合わせる必要があります。
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は4月末時点で87.4%が先進国株、12.6%が新興国株ですから
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 25%
DCニッセイ外国株式インデックス 22%
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 3%
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 25%
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)25%
以上の比率で投資をすればほぼGPIFと同じような投資先とすることができます。
ただし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)の投資比率は多少変動がありますのでご注意ください。
そこまで厳密にやらなくてもよいやって方は新興国株部分の「三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド」を外して「DCニッセイ外国株式インデックス 」を25%としてもよいでしょう。
マネックス証券のiDeCoでGPIFのマネをする
次はマネックス証券です。
マネックス証券では1本でGPIFのマネは出来る商品がありませんので組み合わせで行います。
具体的には以下の5本でGPIFのマネが可能です。
One DC 国内株式インデックスファンド
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
なお、それぞれの投資信託の比率は以下の通りです。
投資比率
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)をベンチマークとした商品がないため、先進国株投資信託と新興国株投資信託で代替えします。
マネックス証券はeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の取り扱いがなく、代わりにeMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)の扱いはあるんですけどね。
One DC 国内株式インデックスファンド 25%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 22%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 3%
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)25%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 25%
そこまで厳密にやらなくてもよいやって方は新興国株部分の「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」を外して「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 」を25%としてもよいでしょう。
また、ちょっと比率が面倒ですが「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」の代わりに「eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)」をいれて国内株部分を少し減らすのもありです。
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)には日本株が7.5%含まれています。
その部分を「One DC 国内株式インデックスファンド」から減らす感じですね。
松井証券のiDeCoでGPIFのマネをする
次は松井証券です。
こちらはマネックス証券と全く同じ投資信託及び比率となります。
One DC 国内株式インデックスファンド
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
当然投資比率も同じですね
投資比率
One DC 国内株式インデックスファンド 25%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 22%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 3%
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)25%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 25%
こちらもそこまで厳密にやらなくてもよいやって方は新興国株部分の「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」を外して「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 」を25%としてもよいでしょう。
楽天証券のiDeCoでGPIFのマネをする
最後は楽天証券です。
楽天証券も5本の投資信託で実現します。
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
たわらノーロード 先進国株式
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
たわらノーロード 国内債券
たわらノーロード 先進国債券
当然投資比率も同じですね
投資比率
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 25%
たわらノーロード 先進国株式 22%
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 3%
たわらノーロード 国内債券 25%
たわらノーロード 先進国債券 25%
こちらもそこまで厳密にやらなくてもよいやって方は新興国株部分の「インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式」を外して「たわらノーロード 先進国株式 」を25%としてもよいでしょう。
また、楽天証券には「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」という全世界の株に投資をする商品があります。こちらも日本株が8%含まれていますので、ちょっと比率が面倒ですが「たわらノーロード 先進国株式」の代わりに「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」をいれて国内株部分「三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド」を少し減らすのもありです。
まとめ
今回は「公的年金を運用するGPIFが過去最高益。iDeCoでGPIFの運用を真似してみよう。」と題してiDeCoでGPIFの投資を真似する方法を金融機関ごとにみてきました。
今回ご紹介した6社以外でも商品さえ揃っていれば可能です。また、iDeCoでなくても企業型確定拠出年金やつみたてNISAでも考え方は同じですよ。
GPIFの投資を真似したい人はやってみてください。
なお、今回はある程度厳密にみましたが、そこまで必要ないよって方は国内株式、外国株、国内債券、外国債券の4資産に分散されているバランス型ファンドでも似たような成績となりますのでそちらで代替えしてもよいでしょう。
人気となっている8資産分散タイプだと新興国株や新興国債券の比率が大きいですし、REITが入りますのでGPIFとは少し違った値動きとなりますのでご注意ください。どちらが良いのかは後にしかわかりませんけどね。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの3社から選ぼう
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。
しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。
簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。
私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券の3択の中から決めます。
(※私が加入しているのはSBI証券です)
この3つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。
また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。
順番に見ていきましょう。
SBI証券
まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。
SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式、ひふみ年金、NYダウ、グローバル中小株、ジェイリバイブといった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。
選択の楽しさがありますよね。
また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。
マネックス証券
次点はマネックス証券 iDeCoです。
こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。
iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。
松井証券
松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。
その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。
こちらも有力候補の一つですね。
さらに2024年8月1日(木)より投資信託の保有でポイントが貯まるようになり、現在の条件なら本命といっても良いでしょう。
総合して考えるとこの3つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。
他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・
最後まで読んでいただきありがとうございました。