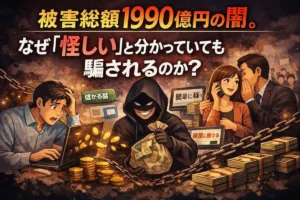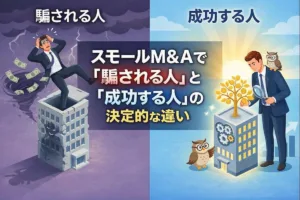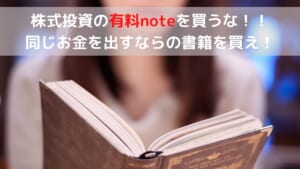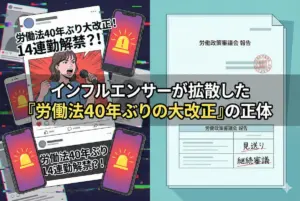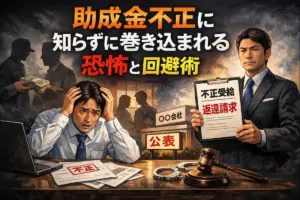近年、日証協(日本証券業協会)が主導する非上場株式の取引・資金調達ルールの整備が進み、個人投資家がアクセスできる場面が拡大しています。
とりわけ、株式投資型クラウドファンディングは、一般投資家にも門戸を開く仕組みとして認知が広がりました。
日経の報道でも、個人による非上場株投資のハードルや手続の見直しが議論されている旨が伝えられ、関心を後押ししています。
ただし「買いやすくなる」ことと「投資として適切か」は別問題。
リスクの総量と中身を正確に理解した上で意思決定する姿勢が欠かせません。
今回は、未上場株(非上場株/プレIPO/未公開株)のリスクを解説していきます。
検討されている準特定投資家制度とは
まずは今回の日経の報道内容から確認していきましょう
日本証券業協会は非上場企業の株式を取引する個人投資家を増やす。投資経験や年収などで一定の要件を満たした個人なら、従来必要だった証券会社への届け出がなくても限られた範囲で取引できるようにする。非上場株の投資家の裾野を広げ、上場を目指すスタートアップへの資金供給を増やす。
出典:日経新聞 個人も非上場株買いやすく 証券会社への届け出不要に、日証協が検討
今回の規則改定では、本人による届け出がなくても証券会社が非上場株を勧誘できる「準特定投資家(仮称)」を新たに設ける。資産や年収、取引経験などの要件は特定投資家と同様にする方向だ。大手証券は資産運用の提案のために富裕層顧客の資産状況を細かく聞き取っており、こうした情報を手掛かりに要件を満たすか判断するとみられる。
背景と狙い
金融庁・政府は、プロ投資家向け私募(特定投資家私募)の利便性向上を進め、2025年にインターネット経由の勧誘などを可能にする見直しを実施(通称「日本版ルール506」)。あわせて特定投資家の要件明確化も行われました。
その次の論点として、特定投資家に“なれる実力があるのに、現に移行申請をしていない個人”を対象に、勧誘対象を段階的に広げる構想が日証協の懇談会で検討されています。
この層を「準特定投資家」と呼び、自主規制の中で勧誘可能範囲に含める案です
一般投資家と特定投資家と準特定投資家の違い
| 区分 | 勧誘対象にできる有価証券の例 | 主な条件・想定運用 | 保護・留意点 |
|---|---|---|---|
| 一般投資家 | 原則、未上場株の勧誘対象外(例外:ECF/株主コミュニティ等) | 行為規制・開示規制のフル適用 | 適合性原則、勧誘規制の保護が手厚い |
| 準特定投資家(仮称) 検討中 | 少人数私募・少額公募等を通じ、特定投資家と並べて勧誘可にする案 | 「特定投資家へ移行可能な個人」だが未申出を対象。指定会員・社内規則整備等を前提に勧誘範囲拡大 | 適合性を実質確認できる体制を義務付け等の検討。運用詳細・投資上限は未確定。 |
| 特定投資家(現行) | 特定投資家私募・J-Ships銘柄等 | 2025年にインターネット勧誘容認、要件明確化 | 行為規制の一部適用除外。特定証券情報の提供等が求められる場面あり。 |
ある程度知識と資産などがある投資家を特定投資家と読んでリスクが高い商品を販売できる制度が特定投資家です。
ただし、特定投資家に“なれる実力があるのに、手続きが面倒で登録しないカテゴリーの人を準特定投資家(仮称)として非上場株式などをリスクの高い商品を販売しやすくするってことですね。
特定投資家の詳細はこちらの記事を御覧ください。

未上場株の基本(用語整理)
次に未上場株の関連用はややこしいので、そちらの整理をしておきましょう。
未上場株/非上場株/非公開株
未上場株、非上場株、未公開株といろいろな言い方がありますが、すべて東証など株式取引所に上場していない株式のことを指します。
未公開株や未上場株は上場を目指している企業、非上場株はあえて上場していない企業と線引する解釈もあります。
正式な定義はありません。
なお、多くは譲渡制限株式(定款で譲渡に会社の承認が必要)で、売買の自由度が低いです。
プレIPO投資
将来の上場を期待して、上場前のラウンド(例:Series A〜Pre-IPO)に参加する投資。
エンジェル投資
個人がシード〜アーリーに資金を供給。
少額分散が原則。

株式投資型クラウドファンディング
登録事業者が募集・媒介。
一般投資家の上限(同一発行体50万円/年、年間合計200万円)などの枠がある。
一般投資家の投資上限や取扱業者の登録など、投資家保護の枠組みは整備されていますが、個別案件の成否は別問題
多くの場合、上場できずに終わっているのが実情のようです。
一次情報の確認と分散が重要です。
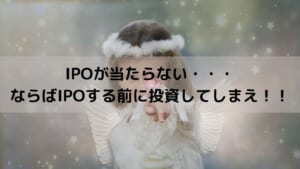
株主コミュニティ制度
日証協の制度。
原則禁止の未公開株勧誘の例外として、運営会員(証券会社)が審査したコミュニティ参加者に限定して勧誘・売買機会を提供。
毎週の取扱状況も公表される。
非上場株の主要リスク8選
次に非上場株のリスクについて見ていきましょう。
特に大きいのが流動性リスクとエグジット不確実性ですね。
非上場株は上場しないと現実的になかなか売れないというのが現状ですからね・・・
1. 流動性リスク(売りたくても売れない/売却コスト)
まずは流動性リスク
仕組み:未上場株は譲渡制限が付くのが一般的。売却には会社(取締役会等)の承認が必要で、相対交渉になることが多い。
何が起きるか:買い手不在・会社不承認・低い提示価格などで売却不能/長期化。
兆候:発行会社が自己株買いのルール不備、株主コミュニティ活用実績なし。
予防策:投資前に定款の譲渡承認プロセスを確認。株主コミュニティの運営有無や実績、想定の二次流通経路をヒアリング。
上場やM&Aしてくれないとなかなか株を売れないよって話です。
会社側が自己株取得をしてくれたり、株主コミュニティでの売却という可能性もありますが・・・
知り合いの事例
私の知り合いも上場を目指している会社にヘッドハンティングで入社。
上場前の社員向け販売で株を数百万円購入。
上場すれば儲かったのですが、実際は数年経っても実現せず。
売ることもできない状況だそう。
配当もないそう・・・
会社は潰れてはいないので株の価値はあるでしょうが、売ることもできない、配当もないのではあまり意味がありません。
損が確定したわけでもないので確定申告で戻すこともできません。
そもそも未公開株は上場株との損益通算できないですが・・・
非上場の株は実際にそういうことが多いんですよ。
そもそも上場を目指した企業が上場できる確率はそれほど高くはないのは知っておきたいところ。
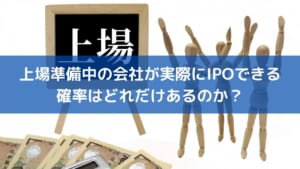
2. バリュエーション不確実性(希望的評価・希薄化)
次はこちら。
仕組み:上場のような市場価格がないため、発行体・投資家間の交渉価格に依存。将来ラウンドでダウンラウンドが発生すれば希薄化が進む。
何が起きるか:IRR低下、1株当たり価値の毀損。
兆候:前回ラウンドからの急な評価引上げ、オプションプール拡大、清算優先権の強化など。
予防策:プレ/ポストマネーと発行株式総数(FDベース)を把握し、希薄化シミュレーションを最低限実施。
株価が分かりづらいってことですね。
非上場株は言い値で買うことになると思いますが、そもそもその株価が割高な可能性が大。
また、将来的な希薄化などのリスクも高いです。
3. 情報非対称・開示の限定(財務・KPI・契約情報の取得困難)
次は情報の非対称性です。
仕組み:未上場は任意開示が中心。財務・KPI・主要契約を十分入手できない場合がある。
何が起きるか:誤解や見込み違いが起き、期待値のブレが大きくなる。
兆候:監査の有無不明、四半期KPIの定義が曖昧、関連当事者取引の説明が薄い。
予防策:一次資料の閲覧(データ室)を求める。官報・決算公告・法人番号・登記などの公的一次情報で裏取り。
上場してないと情報が得られにくいってことですね。
下記の記事の通り、決算書を見る方法はありますが、そもそもその数字が正しいかどうかすらわかりません。
粉飾決算は上場していると大きな問題となりますが、非上場の会社の場合には税務署からすれば余分に税金を納めてくれているありがたい企業みたいな扱いなんですよ・・・
銀行からお金を借りてて、粉飾した決算書を出していれば詐欺ですけどね。

4. ガバナンス・関連当事者取引
次はガバナンスです。
仕組み:役員・主要株主・関係会社との取引は利益相反が生じやすい。上場に比べ外部監視が弱い。
何が起きるか:不利な条件や内部統制の脆弱性が、価値毀損・訴訟・監督当局対応につながる。
兆候:役員貸付の多用、親族会社への外注濃度、内部監査不在。
予防策:第三者比較・社外取締役/監査役の機能・関連取引の承認フローを確認。
これも多い話です。
非上場の会社は役員の暴走も多いんですよ。
それを監視する機能はあまりありません。
そのあたりはリスクですね。
5. 事業継続・資金繰り(ダウンラウンド、ブリッジ条件悪化)
次はそもそもの問題。
仕組み:手元資金月数(Runway)が短いと、条件不利な資金調達になり希薄化が加速。
何が起きるか:評価下落、投資家間の優先順位確執、債務的資本(ブリッジ)の条件悪化。
兆候:コベナンツ接近、資金調達計画の遅延。
予防策:月次CF・資金計画・次ラウンド条件を入手し、最悪ケースの希薄化を織り込む。
資金繰りの悪化などで事業継続の危機になる可能性もあるって話。
前述のように決算も正確なのかは不明で、判断する材料がかなり少ないんですよ。
定性的な状況で判断するのが良いかもしれません。
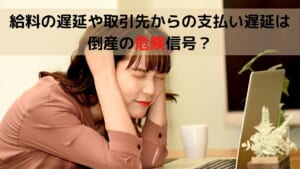
6. 詐欺・不適切勧誘(デューデリ不足・誇大広告)
次も実際よくある話です。
仕組み:無登録業者や詐欺的スキームがSNS等で接触。確実な利益を謳う手口が典型。
何が起きるか:資金流出、権利保護が困難。
兆候:登録番号非開示、会社実体不明、官報・登記・法人番号で裏が取れない。
予防策:金融庁の無登録業者警告リスト、財務局の注意喚起を確認し、一次情報で裏取り。
SNSや電話での勧誘される非上場株の売買はそもそも投資詐欺の可能性が高いです。
基本的に勧めませんが、どうしてもやりたい場合はしっかりチェックをしましょう。

7. エグジット不確実性(IPO/TOB/M&Aの低確率・時間軸)
流動性と被ってきますが、IPOやTOBの不確実性も大きいです。
仕組み:IPO・M&Aは外部要因の影響が大きく、タイミングは読みにくい。株主コミュニティのような二次流通もあるが、参加・勧誘範囲が限定される。
何が起きるか:長期塩漬け、想定IRRに届かない。
兆候:上場準備のロードマップ不在、主要KPIが加速していない。
予防策:最大保有年数・途中売却の選択肢(自己株取得・株主コミュニティ経由)を事前に設計。取扱状況の公表も参考。
実際問題、未公開株で上場できないとほとんどの場合が損をします。
前述したようなリスクが多いため、ほとんどがゴミになる・・・
株式投資型クラウドファンディングでお金を集めた企業で上場できたのは数%という話もあります。
しかし、「にじさんじ」というVチューバーの会社のように上場前に株を購入した社員みんなが億超えするなんてこともありますからね。
ハイリスク・ハイリターン投資の代表格といえます。

8. 税務・相続の留意(評価・損益通算の難しさ)
最後は税務上の話。
仕組み:株式の譲渡益は申告分離課税。上場株式等と一般株式等(非上場等)は別区分で、損益通算できないのが原則。評価・贈与・相続時の算定も難しい。
何が起きるか:税負担の読み違い、損失の通算不可で実効利回りが悪化。
兆候:税区分の混同、持株会社経由の取引で論点が増える。
予防策:区分・税率・手続をタックスアンサー等で事前確認。個別論点は税理士へ
普通の上場会社の株と違ってかなり複雑です。
上場株式等と一般株式等(非上場等)は別区分の申告分離課税で、損益通算できないのが原則。
個別論点は税理士に相談をするとよいでしょう。
ただし、税理士もあまりやりたがらない仕事だったりします・・・
非上場株を買うなら個人投資家がやるべきこと。
それでは非上場株を買う場合に個人投資家がやるべきことはなにがあるでしょう?
小口・分散
まずは大きな資金を入れないってことです。
小さく、分散投資をしましょう。
非上場株は当たりにくいですが、当たれば大きいですからね。
ただし、ゼロもあることを前提に。
決算書や事業計画は話半分で
前述したように決算書はあまり信用しないほうがよいでしょう。
また、事業計画もなんとでも書けますからね・・・
話半分に聞くくらいがちょうどよいかもしれません。
希薄化リスク、優先条項を数字で確認することは有効です。
また、ChatGPTなどに事業計画などからビジネスモデルを整理してもらうのは有効です。

退出戦略の事前確認
実際のIPOなどのエグジットの計画がどうなっているのかをしっかり確認しましょう。
また、自己株取得の方針などを確認しておくと良いでしょう。
勧誘業者の確認
勧誘業者の登録番号と会員区分、警告リストを照合しましょう。
無資格業者の場合は詐欺ですから回避しましょう。
一次情報を調べる
官報・登記・法人番号・会社サイトの決算公告、定款で条項を読むなど入手できる一次情報をかならず調べましょう。
役員の名前や住所でググると過去の犯罪履歴が出てくるケースもあったりして回避できるケースもあります。
その他、その企業のニュースや報道など多方面からチェックしましょう。
Perplexityとかを使えばかなり調べることができます。

まとめ
今回は「準特定投資家制度で非上場株が買いやすくなるかも。未上場株リスク完全ガイド」と題して未上場株のリスクについて考えてみました。
未上場株は打ち上げ花火型の分布(多くが低回収〜ゼロ、少数が大化け)。
ゼロの太い尾と長期化を織り込める設計(小口・分散・退出想定)で臨み、「数字と一次情報」に基づく意思決定を徹底しましょう。
リスクを知ったうえで参加するための第一歩です