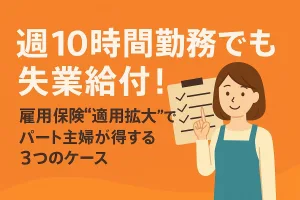2025年通常国会で審議中の年金制度改革関連法案に、「基礎年金(国民年金)の給付水準を“底上げ”するために厚生年金の積立金を活用する」という修正案が滑り込みました。
メディアや一部政治家はこれを “あんこを入れる” と呼び、河野太郎氏は X(旧 Twitter)で「毒入りあんこだ」と痛烈に批判しています
本記事では、社会保険労務士としての視点から
- そもそも“底上げ案”とは何か
- 厚生年金積立金はどこから生まれたお金なのか
- 修正案に対するメリット・デメリット
- 読者が今から取れる対策
をやさしく、しかし踏み込んで解説します。
基礎年金“底上げ案”の中身を整理
まずは今回の案の中身を整理してい行きましょう。
なぜ基礎年金の底上げが必要なのか
厚労省の 2024 年財政検証では、就職氷河期世代以降が老後を迎える 2050 年ごろに基礎年金水準が現在より最大3割低下するシナリオも示されました。
つまり、このまま何もしなければ就職氷河期世代が老後を迎える際に基礎年金が大きく減ってしまうということです。
私も就職氷河期世代ですが、不安定な職業につかざる得なかった方も多いですからね。
そうなると厚生年金もまともに加入していない、預金もないという積んだ状況になってしまった上に基礎年金まで減ってしまえば生活保護をもらうしかないという状況になりかねないのです。
修正案が出るまでの流れ
元々は5年に1度行われる大型の年金制度改革でこの話は盛り込まれていました。
しかし、年金制度の案を決める社会保障審議委員を務めるタレントのたかまつなな氏がXで大炎上するなどしたことからか、この部分は最終案でなかったことになったんですよ。
しかし、立憲民主党が就職氷河期の切り捨てだと指摘し、修正案を出したことで自民党、公明党がその案を飲んだ形となります。
元々は立ち消えになった案を立憲民主党が復活させた形ですね。
修正案のポイント
修正案のポイントをまとめると以下のとおり。
・財源:厚生年金積立金(GPIF が運用する年金特別会計の余剰)を主財源に、税金も上乗せ
・方式:将来の給付減少分を前倒しで穴埋め(=“あんこを入れる”)
・対象:国民年金1号被保険者(自営業・学生など)と3号被保険者(専業主婦等)中心
・スケジュール:2025 年度内成立→2026 年度施行を目指すが、積立金取り崩し比率や上乗せ額は法成立後に政令で調整予定
元々、炎上したのは厚生年金積立金の積立金を財源で国民年金を救済するという部分でした。
今回の修正案でもその部分は残っていますね。。。
もう少しわかりやすくまとめるとこんな感じですね。
少子高齢化で国民年金(基礎年金)の水準が将来大幅に減る見込み
↓
会社員が加入する厚生年金の積立金を振り分ける
↓
国民年金の低下幅を抑える
厚生年金積立金ってそもそも誰のお金?
厚生年金の保険料は労使折半で18.3%(2025 年度以降固定)。
つまり、会社と本人が9.15%ずつ支払っているってことですね。
この保険料と運用益のうち、給付にすぐ使わない分を積み立ててきたものが厚生年金積立金です。
2024 年度末時点で残高約 220 兆円。
そのほとんどは厚生年金の将来給付を賄うために存在します。
言い換えれば現在の積立金は「将来の厚生年金受給者(主に現役サラリーマン)のための前払い金」。
流用すれば厚生年金の長期安定性は低下します。
国民年金は加入者だけで支えるのは無理
とはいえ国民年金の加入者だけで支えるのは制度設計上無理があるんですよ。
厚生年金と国民年金では加入者の違い
まず、厚生年金と国民年金では加入者が全然違います。
具体的にはそれぞれ以下の条件の方が加入することになっています。
※スマートフォンの方は横スクロールすれば表全体がご覧いただけます。
| 加入保険 | 条件 | 主な方 | |
| 第一号被保険者 | 国民年金 | 日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方 | 自営業者 農業 漁業 学生 無職 第三号被保険者以外の専業主婦 |
| 第二号被保険者 | 厚生年金 | 民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者 | 会社員 公務員 教職員 |
| 第三号被保険者 | 国民年金(負担なし) | 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方 | 専業主婦 |
国民年金の納付者は加入者の半数程度しかいない
特に大きいのが国民年金の加入者のうち半数程度しか納付していないという点も大きいです。
第一号被保険者には無職、学生、第三号被保険者以外の専業主婦(自営業者の配偶者など)といった所得の無い方が多く含まれているんですよ。
そのため、全額免除もしくは猶予者が全体の42.6%もいます。
無職の方や所得の少ない方は免除が受けられる可能性がありますし、学生は学生納付特例制度というのがありますからね・・・
さらに一部免除や猶予者もみえますから全体の第1号被保険者数が1,431万人なのにたいしてすべて納付している人は784万人しかいないのです。※令和3年末
さらにサラリーマンの配偶者が専業主婦の場合は、第3号被保険者という負担がはじめから不要な制度の加入者となります。
つまり、半数程度しか全額払えていないんですよ。
未納の方もなんだかんだでまだまだいます。
半数の方は負担をしていないけど国民年金は老後にもらえるという。
民間の年金制度なら運営は難しい状況になっているでしょうね・・・
なお、国民年金には国からの国庫負担もありますが、それと国民年金の納付者だけで支えろというのは、少子高齢化が進めば進むほど厳しい状況になってしまうのは考えるまでもないでしょう。
ですから厚生年金の流用に怒る方も多いですが、国民年金だけの加入者だけで支えるのはそもそもかなり無理がある制度設計なんですよ。

修正案をめぐる賛否
今回の修正案はかなり賛否が起きています。
| 視点 | 賛成派の主張 | 反対派の主張 |
|---|---|---|
| 公平性 | 自営業や無業の低年金対策は急務 | サラリーマンが二重負担を背負う |
| 財政健全性 | GPIF 運用益で賄える範囲なら問題なし | 積立金は将来不足を補う“虎の子” |
| 世代間バランス | 現役世代への負担も軽減できる | 将来世代が結局ツケを払う |
| 税財源との組み合わせ | 所得再分配を強化できる | 財源内訳が不透明で“毒入りあんこ” |
河野太郎氏は前述の X ポストの中で「保険料の目的外使用」と断罪し、国民民主党の玉木雄一郎氏も同調しています。
制度改正が実現したら家計はどう変わる?
それでは制度が実現したらどのように変わるのでしょう?
| ケース | 変更前(見込み) | 変更後(例示) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 国民年金フル納付40年 | 月 65,000 円 | 月 72,000 円 | +7,000 円 |
| 専業主婦(第3号) | 同上 | 同上 | 同上 |
| 厚生年金平均的会社員 | 報酬比例+基礎=月 150,000 円 | 報酬比例▲(数千円減る可能性)+基礎↑ | ±ゼロ〜▲数千円 |
あくまで公表資料と各種報道を基にしたシミュレーションです。具体額は今後の政令で確定します。
社労士が見るメリット・デメリットまとめ
それでは社労士でもある私が見たメリット・デメリットを見ていきましょう。
メリット
- 低年金層の生活保護依存リスクを軽減
- 非正規・自営業の老後不安を緩和し、消費下支え期待
デメリット
- 厚生年金加入者の「取り崩され感」→保険料納付意欲や消費マインドにマイナス
- 積立金減少で GPIF のリスク許容度が下がれば運用収益率も低下
- 制度の“ツギハギ感”が世代間対立を先鋭化し、将来さらなる改修が必要になる恐れ
個人的にはこのような小手先の変更ではなく、抜本的な改正が必要な時期に来ていると感じています。
今すぐできる4つの備え
法律改正について一般の人ができるのは選挙での投票だけです。
決まってしまったことについはどうしようもない部分が大きいですよね。
ですから個人的には以下の4点を実施していくのが良いのかと思います。
一時期話題になった老後2000万円足りない問題。
その対策としてもiDeCo・企業型 DC、新NISAは有効です。
それだけガチるだけでも老後資金の問題は解決できる可能性が高いと考えます。
老後の資金のことも早めに考えることをおすすめします。
老後2000万円足りない問題についてはこちらの記事を御覧ください。

まとめ――制度議論を「自分ゴト」に
今回は「基礎年金底上げは“毒入りあんこ”なのか?――厚生年金積立金流用をめぐる年金制度改革法案を社労士が徹底解説」と題して基礎年金底上げの話を見てきました。
“あんこ”を入れるか否かは政治判断ですが、私たちの老後は国任せでは守り切れません。
厚生年金の人も国民年金の人も、「制度がどう変わっても困らない」よう、公的年金+自分年金+投資+現金クッションの4本柱で備えましょう。
特に自分年金のiDeCoが有効ですよ。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの3社から選ぼう
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。
しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。
簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。
私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券の3択の中から決めます。
(※私が加入しているのはSBI証券です)
この3つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。
また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。
順番に見ていきましょう。
SBI証券
まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。
SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式といった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。
選択の楽しさがありますよね。
また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。
マネックス証券
次点はマネックス証券 iDeCoです。
こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。
iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。
松井証券
松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。
その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。
こちらも有力候補の一つですね。
さらに2024年8月1日(木)より投資信託の保有でポイントが貯まるようになり、現在の条件なら本命といっても良いでしょう。
総合して考えるとこの3つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。
他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・
最後まで読んでいただきありがとうございました。