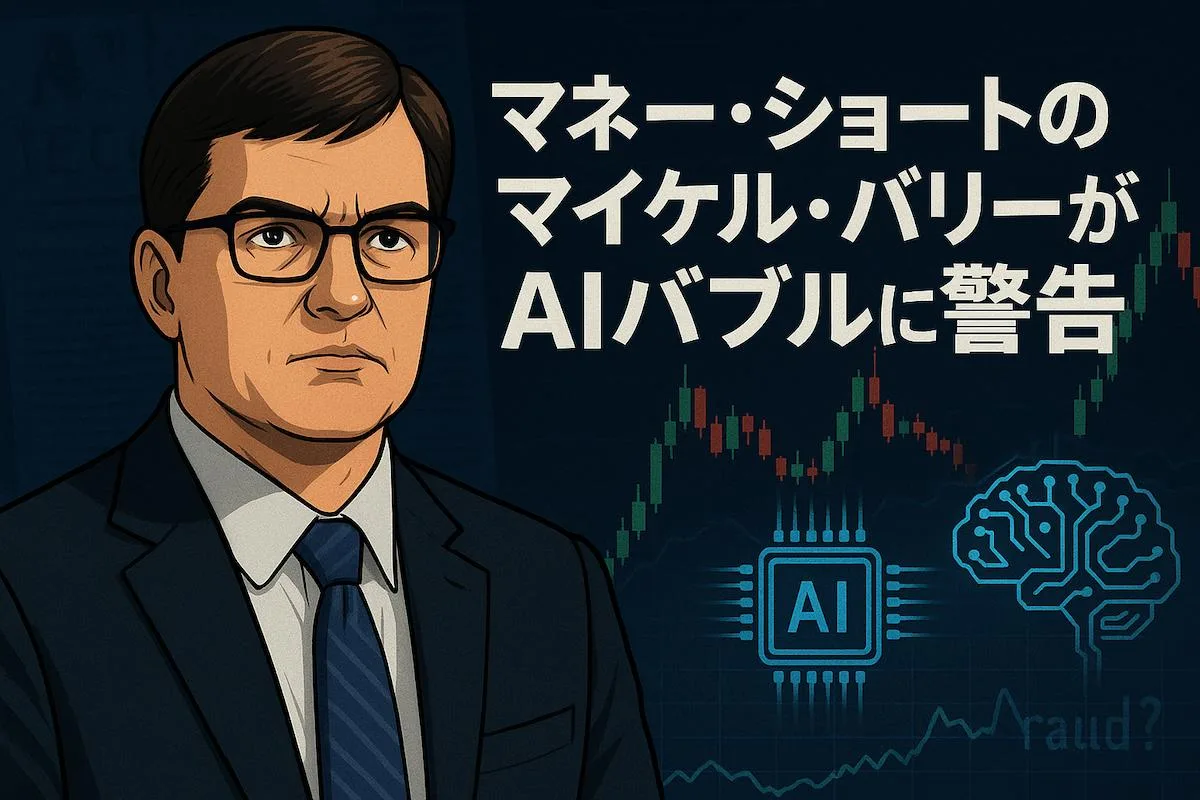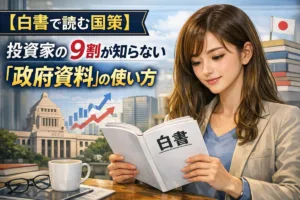映画『マネー・ショート 華麗なる大逆転』のモデルとなった投資家マイケル・バリー氏が、再び世界の注目を集めています。
今回はサブプライムローンではなく、「AI企業の決算の中身」、さらにいえば減価償却の扱い方に踏み込んで「不正(fraud)」とまで表現したからです。
あわせて自身の運用会社サイオン・アセット・マネジメントでは、パランティア(Palantir)やエヌビディア(NVIDIA)といった代表的なAI銘柄に対して、大きなプットポジション(事実上の空売り)も構築。
X(旧Twitter)上でも「AIバブル」への警鐘を鳴らしており、「マイケル・バリー AIバブル」「マイケルバリー パランティア」といった検索が増えている状況です。
リーマンショック前の住宅バブル崩壊を見抜き、7億ドルの利益を上げた伝説の投資家が、今度はAI革命そのものに疑問符を投げかけたのです。
今回はマイケル・バリー氏のAI企業への空売りが何を意味するのか、バリー氏が具体的に何を「不正」と呼んだのか等を解説していきます。
マイケル・バリーとは誰か?映画『マネー・ショート』のモデル
まずはマイケル・バリー氏をご存知ない方も多いと思いますので、どういう方なのかを解説していきます。
映画で描かれた住宅バブルの空売り
マイケル・バリー氏を一躍有名にしたのは、2015年公開の映画『マネー・ショート 華麗なる大逆転』です。
この作品は、2008年のリーマンショックを予見し、サブプライムローン市場の崩壊に賭けた実在の投資家たちの物語を描いています。
この映画でクリスチャン・ベールが演じたのが、実在の投資家マイケル・バリー氏。
彼は2000年代半ば、誰も本気で崩壊を信じていなかった米国住宅バブルに対し、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)を駆使して大規模なショートポジションを構築しました。
結果として2008年のリーマンショックで住宅市場が崩壊し、莫大な利益を手にしたことで一躍「伝説の投資家」となります。
利益率489%という結果は、彼の鋭い市場分析力を証明しています。
映画では、周囲から「頭がおかしい」とまで言われながらも、自分の分析を信じてポジションを維持する姿が描かれました。
この「孤独な逆張り」のイメージが、今も「マイケル・バリー 予想」を特別なものとして受け止めさせる背景になっています。
映画の中で特に印象的なのは、マイケル・バリー氏が格付けの高い不動産抵当証券の事例を一つひとつ調べ上げ、サブプライムローン債権を含む債務担保証券が数年以内にデフォルトに陥る可能性を発見する場面ですね。
世界中が住宅市場の永続的な成長を信じていた時代に、彼だけが破綻の兆候を読み取っていたのです。
まだ見たことない方はぜひ見ていただくのをおすすめします。
映画と現実のマイケル・バリー氏は少し違う
一方で、映画はドラマとして分かりやすくするために、どうしてもマイケル・バリー氏を「常に正しい天才」のように描きがちです。
しかし現実のマイケル・バリー氏は、その後も何度も大きな警告や空売りを行い、そのすべてが当たったわけではありません。
たとえば2023年初めには「Sell.(売れ)」と短いツイートで株式市場の大幅下落を警告しましたが、その後S&P500は70%以上上昇し、本人も「売れと言ったのは間違いだった」と認めています。
また、マイケル・バリーバリー氏の空売りが裏目に出た事例を整理した日本語記事でも、「相場の予測が当たることと、そこでちゃんと儲けられることは別問題だ」と指摘されています。
映画のイメージだけで「今回も絶対当たる」と思い込むのは危険で、過去の成功と失敗の両方を冷静に見る必要があります。
パランティアとエヌビディアへの大規模空売り
今回のマイケル・バリー氏の発言や行動を確認していきましょう。
明らかになった空売りポジションの全容
2025年11月6日前後、マイケル・バリー氏が率いるサイオン・アセット・マネジメントの保有銘柄開示が、市場に大きな波紋を広げました。
SEC(米国証券取引委員会)への報告書により、同ファンドがポートフォリオの約66%をパランティア・テクノロジーズのプットオプションに、約13.5%をエヌビディアのプットオプションに投入していることが判明したのです。
プットオプションとは、株式を一定の価格で売る権利を購入する金融商品です。
株価が下落すれば、その権利を行使して利益を得られます。
つまり、バリー氏はAI関連の二大銘柄の株価下落に賭けたのです。
報告書の数字は衝撃的でした。
ポートフォリオ全体の約80%が、エヌビディアとパランティアという「AI革命の双子の神々」への売りポジションに集中していたのです。
これは単なるヘッジではなく、確信に満ちた投資判断であることを示していました。
「80%ショート」の誤解と実態
市場では「バリー氏がポートフォリオの80%をAIショートに投じた」という衝撃的な数字が独り歩きしました。
しかし、詳細な分析によれば、この数字は誤解を招く可能性があります。
13F報告書に載るのはプットオプションの名目額(行使対象株式の理論価値)であって、実際にバリー氏が支払ったプレミアム(オプション料)はその一部に過ぎないこと。
あくまで13F報告書は過去時点の「スナップショット」であり、公表された時にはすでにポジションを閉じている可能性。
これらを考えると「資産の80%をショートに突っ込んだ」と決めつけるのは危険かもしれません。
市場の反応と株価への影響
この開示を受けて、パランティア株は第3四半期の好決算にもかかわらず、一日で7.9%急落しました。
エヌビディア株も同様に下落し、ナスダック指数全体が2%の下落を記録しました。
金融アナリストの豊島逸夫氏は、今回の株価変動について「バリー氏は『The strong short』というふたつ名を持ち、同氏の映画が制作公開されたことがあるほど有名な存在ゆえ、プットオプションの総額が10億ドル程度でもニューヨーク市場を震撼させた」と分析しています。
興味深いのは、この市場の動揺が24時間以内に収束に向かったことです。
投機筋の仕業として処理され、翌日には株価も金価格も反騰しました。
しかし、この短期的な収束が、バリー氏の指摘する構造的問題の不在を意味するわけではありません。
メタとオラクルの減価償却を「もっともありふれた不正」と批判
2025年11月時点で、マイケルバリー氏はAI関連企業の会計操作に注目しています。
具体的には、メタ、グーグル、マイクロソフト、アマゾン、オラクルといった「ハイパースケーラー」と呼ばれる大企業が、サーバーやGPU(グラフィックス処理ユニット)の減価償却期間を延長していると指摘しています。
Xの投稿で、彼はこう述べています。
「減価償却を低く見積もって資産の使用可能期間を延ばすことは、利益を人為的に増やす一般的な不正の一つだ。」
要約すると
要旨をかみ砕くと、次のような主張になります。
- Meta(メタ)やOracle(オラクル)など大手テック・AI企業がサーバーやAIチップなどの資産の「耐用年数」を引き延ばしている
- それにより、減価償却費が実態より少なく計上され、利益がかさ上げされている
- 2026〜2028年にかけて、減価償却費の過小計上額は合計で約1,760億ドル(約26兆円)に達し、
Oracleで26.9%、Metaで20.8%も利益が水増しされる - こうした「減価償却をいじって利益を膨らませるやり方」は「現代でもっとも一般的な不正のひとつだ」とまで表現
ポイントは、ここで言っている「不正」が、必ずしも違法な粉飾決算を意味しているわけではないことです。
減価償却というのは、本来は資産の価値が年々減っていくことを会計上でならして計上する仕組みですが、「何年で減るとみなすか」は会社の見積もり次第という側面があります。
この裁量の幅を目一杯使って「耐用年数を長く見積もる=当面の費用を小さくする」ことで、短期的には利益を押し上げることが可能になります。
バリー氏は、これを「実態から乖離した楽観的な前提に基づく利益の水増し」とみなし、「fraud」と強い言葉で批判したわけです。
減価償却期間の延長がもたらす影響
通常、ハイテク企業はGPUやサーバーを購入後、3~4年で減価償却します。
しかし、バリー氏によると、これらの企業は最近、5~6年に延長しています。
たとえば、メタは2020年に3年だった期間が2025年には5.5年、オラクルは5年から6年に変更されています。
これは、NVIDIAの製品サイクルが2~3年と短いことを考えると、現実と乖離している可能性があります。
減価償却を延ばすことで、毎年計上する費用が減り、利益が膨らむ仕組みです。
バリー氏は2026~2028年の間に、この手法で約1760億ドル(約26兆円)の減価償却が未計上されると試算。
オラクルは利益を26.9%、メタは20.8%水増ししていると見ています。
アナリスト側は「粉飾というよりタイミングの問題」と反論
もちろん、市場側が一方的にバリー氏の主張を飲みこんだわけではありません。
テック企業の分析を専門とするアナリストの中には、次のような反論も出ています。
- 減価償却の見積もりはたしかに会計上の「グレーゾーン」だが、今回のような変更は他社でも行われており、即粉飾と決めつけるのは早計
- 費用を「今から将来へ後ろ倒し」にしているだけなので、「今期の利益が多すぎる分、将来の利益はその分少なくなる」だけ
- 長期的にはトータルの利益は変わらず、税制や投資サイクルとの兼ね合いで調整している側面も大きい
つまり、「不正」とまで言うかはともかく、数字の見せ方で利益をよく見せているのは事実だが、それをどう評価するかは投資家次第——というのが冷静な見方です。
マイケル・バリーの予想はどこまで当たってきたか
サブプライムローンでの崩壊を予想したことで、一気に知名度が上がりましたが、マイケル・バリー氏の投資スタイルには、一つの弱点があります。
それは「常に早い」ことです。
サブプライムローン
サブプライム危機の際も、彼がクレジット・デフォルト・スワップを購入し始めてから実際に市場が崩壊するまで、数年の時間差がありました。
その間、彼は顧客からの解約圧力と批判に晒され続けました。
市場全体が住宅バブルを信じている中で、一人だけ逆張りのポジションを維持することは、精神的にも財務的にも大きな負担でした。
しかし、最終的に彼の分析は正しく、莫大な利益を生み出しました。
早いことと間違っていることは、時間だけが隔てています。
そして時間は決して負けません。
バリー氏が指摘する構造的問題が実際に存在するならば、それが顕在化するのは時間の問題です。
ただし、それがいつなのかを正確に予測することは、誰にもできないのです。
サブプライム・ローン後の予想
その後も、
- 2022〜23年にかけて、株価暴落や長期不況を何度も警告
- 2023年には「Sell」とツイートし、その後の株高で「売れと言ったのは間違いだった」と撤回
- テスラやARKなどへの空売りで利益を出した一方、大きなショートがうまくいかなかったケースも指摘されている
といったように、早すぎたり外れたりしているんですよ。
ここから言えるのは、
- バリー氏の分析や問題意識は参考になる
- しかし、「予想が当たるかどうか」「いつ当たるか」は保証されない
というかんじなのです。
投資家が取るべき戦略──マイケルバリー氏の教訓から学ぶこと
それでは投資家はどう動けばよいのでしょう?
分散投資とリスク管理の重要性
バリー氏自身が示しているように、投資戦略の核心はリスク管理にあります。
彼のバーベル戦略は、極端なポジションを取りつつも、ポートフォリオの中核を堅実な資産で固めるという、バランスの取れたアプローチです。
一般の投資家にとって、この教訓は重要です。AIバブルが崩壊するかもしれないという懸念があるからといって、AI関連株をすべて手放すべきではありません。
同時に、AI株だけに集中投資するのも危険です。
分散投資の基本原則は、今も昔も変わりません。
複数の資産クラス、複数のセクター、複数の地域に投資を分散することで、特定のバブル崩壊による壊滅的な損失を回避できます。
空売りでの真似は危険
映画のイメージもあり、「マイケル・バリーのようにAIバブルを空売りしたい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、これは個人投資家が真似すると危険な部分です。
もともとバリー氏のポートフォリオは「極端な集中投資+大胆な空売り」で構成されており、一般の投資家が同じことをすると、タイミングを誤ったときの損失は甚大となります。
公表された時点では、すでにポジションが大きく変わっていたり、イナゴが狙われる可能性も高いんですよ。
マネー・ショートの世界をそのまま再現しようとするのではなく、
- バリー氏の問題意識(AIバブル・会計のグレーゾーン)をリスク認識として取り入れる
- 実際の取引は、自分のリスク許容度に合わせて現物とロング中心で組む
くらいの距離感がちょうど良いと思います。
なにより空売りは難しいんですよ。

休むも相場
また、ウォーレン・バフェット氏が3800億ドル超の現金を保有していることは、重要な示唆を与えます。
偉大な投資家は、機会が訪れるまで辛抱強く待つことができます。
無理に投資機会を作り出そうとせず、明らかに割安な資産が現れるまで、静観する規律を持っています。
現在のAI株の評価が高すぎると感じるならば、無理に買う必要はありません。
市場が調整し、適正な価格水準に戻ったときに投資すれば良いのです。
FOMO(取り残される恐怖)に駆られて、割高な資産を掴まされることは、投資家にとって最も避けるべき失敗です。
「休むも相場」も検討してみると良いでしょう。
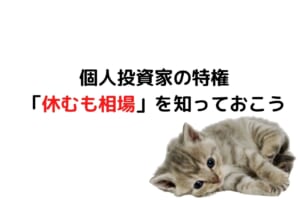
まとめ
今回は「パランティアとエヌビディアへの大規模空売り。マネー・ショートのマイケル・バリーがAIバブルに警告したことを解説」と題してマイケル・バリー氏の警告について見てきました。
マイケル・バリー氏が長い沈黙の末、久しぶりにXに投稿したメッセージは印象的でした。
「Sometimes, we see bubbles. Sometimes, there is something to do about it. Sometimes, the only winning move is not to play.」
バブルが見える時もある。それに対して何かできる時もある。
しかし、最良の手は、時として「プレイしないこと」である──この言葉は、彼の投資哲学の核心を表しています。
日本語だと「休むも相場」ですね。
バリー氏は2025年第3四半期、「AIショート」というゲームにオールインしませんでした。
彼はポートフォリオの核をヘルスケア株という安全資産で固め、投機的なベットはバーベルの両端に留めました。
これは、市場の熱狂から一歩引いた、極めて冷静なプレイヤーの姿勢です。
私たち一般の投資家も、この教訓から学ぶことができます。
AIバブルが存在するかもしれないという認識を持ちつつ、極端な行動を避ける。
分散投資を維持し、規律を守り、明らかに割安な機会が訪れるまで辛抱強く待つ。
そして、自分が理解できる範囲で投資を行う。
AIという技術は本物です。
私たちの社会を変革し、多くの産業を再編する力を持っています。
しかし、それと株価の評価は別問題です。
マイケル・バリー氏の警告を、投資家としてどう受け止めるかを一度考えて見ても良いでしょう。
清原達郎氏も似たことを言ってるんですよね。

【免責事項】 本記事は情報提供のみを目的としており、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。