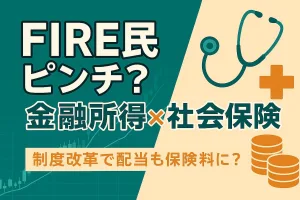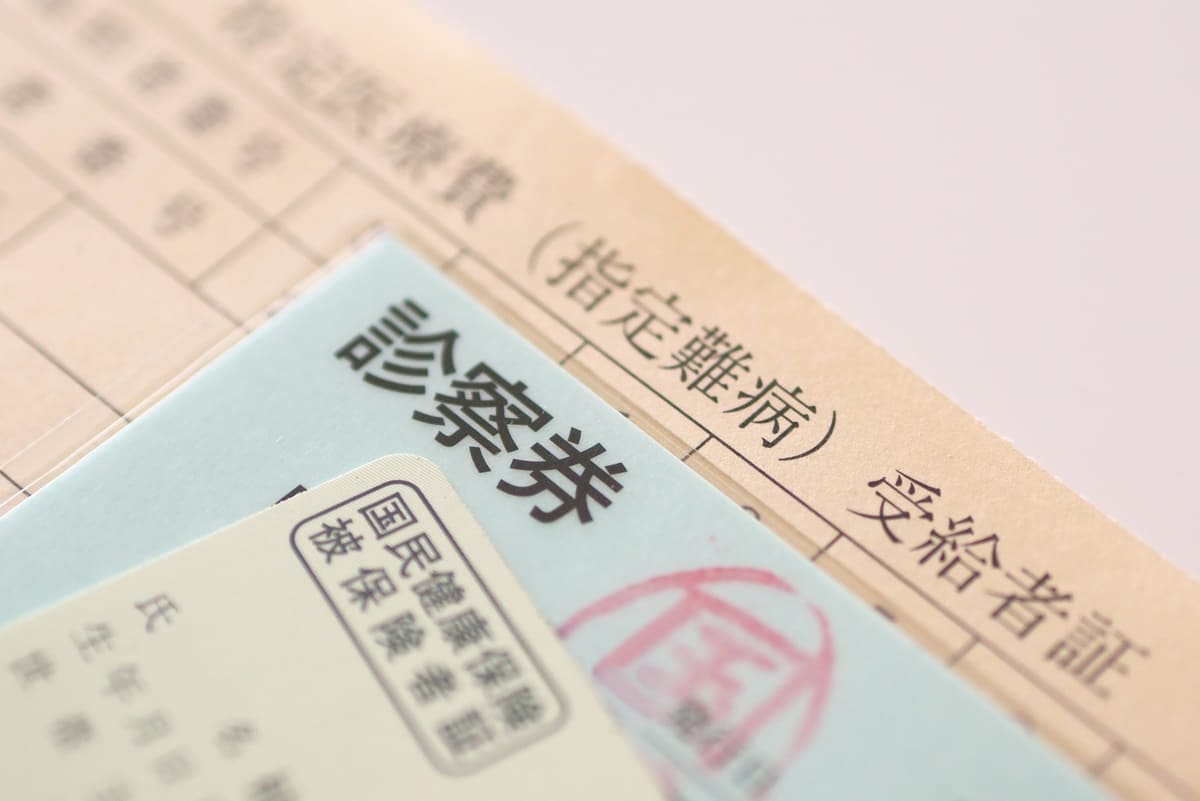最近、毎年恒例になりつつありますが、またもや国民健康保険が値上がりしそうです。
自営業者などが加入する国民健康保険について、厚生労働省は保険財政を改善するため、所得の高い人が支払う年間の保険料上限額を来年度から3万円引き上げて92万円にする方針を決めました。上限額の引き上げは4年連続となります。
出所:NHK
年間3万円の値上げは結構痛いですね・・・今回はこの問題について考えてみましょう。
国民健康保険とは
国民健康保険とは自営業、フリーランスの方や社会保険に加入していない会社に勤める労働者、無職の方などが加入する健康保険です。
サラリーマンの方やその扶養の方が加入している健康保険は、会社により組合健保だったり協会けんぽ(全国健康保険協会)だったりしますがそれとはすこし扱いが違います。
今回値上がりするのは自営業、フリーランスの国民健康保険の法です。
もともと国民健康保険は割高である。
私も会社員から自営業者になった口ですが、実際払う段階になって国民健康保険の高さに驚きました。
この理由は大きく分けて2つあります。
会社の負担がなくなるため
まず一番大きいのがサラリーマンの方などが加入する組合健保や協会けんぽは会社負担が半分あるのに対して国民健康保険はそれがないことでしょう。
つまり、実は会社勤めのころは健康保険を会社が半分負担してくれてて自分自身は半額を払っているだけだったんですよね。それがなくなることで体感的に高く感じてしまう点が一番大きいと考えられます。
ちなみに会社によっては半分より多く負担してくれているところもあります。たとえばトヨタなどは6割超が会社負担ですね。転職や就職するときは給料だけでなくそのあたりの社会保険や福利厚生の部分もチェックしておかないと生涯を考えたらかなりの差となります。
加入者層の違い
体感だけでなく実際に金額も大きいのですがその理由としてあげられるのが加入者層の違いです。
会社員の入る組合健保だったり、協会けんぽは基本的に加入者は会社員の方及びその扶養者です。つまり、ある程度収入のある方がほとんどとなります。
対して国民健康保険の加入者は「自営業」、「社会保険に加入していない事業所に勤務する労働者」、「無職」、「高齢者」となります。つまり、国民健康保険は無職の方や高齢者の方が多いため相対的に見ると所得が少ない方や所得のない方が多いのです。
また、高齢者の場合には医療費が掛かる頻度や金額が多くなります。
そのため財政面が組合健保や協会けんぽと比べるとあまり良くなく、自営業者など所得がある人の負担が大きくなってしまうのです。
ただし、人材派遣健康保険組合が解散を発表するなど組合健保の中には赤字でかなり厳しい財政のところもあります。そんなところは高い保険料率が設定されています・・・。逆にIT系など加入者が若い人の多い組合健保は保険料率も安く福利厚生も充実している傾向にあります。
地区による大きな違いも
平成30年から都道府県単位化されましたが、国民健康保険は地区による違いもかなり大きいです。
医療費が多く掛かる高齢者が多い少子高齢化が進んでいる市町村と医療費があまりかからない若者が沢山すんでいる地域では保険料がかなり違います。
たとえば年収400万円であったとして一番高い地域だと国民健康保険は年間60万円オーバーとなります。
対して一番安い地域だと30万円を切ります。
つまり、倍くらい違うのです。
住んでいる地域でこれだけ違うと正直やってられませんよね。
高い地域はより少子高齢化がすすんでしまうかもしれません。
国民健康保険の上限の影響を受けるのは年収どれくらいからか?
前述のように地区により国民健康保険はかなり金額が違います。
そこで主要都市の単身者の年収がどれくらいの場合に今回の上限アップの影響を受けるのかを算定してみました。
だいたい1100万円くらいの地区が多いようです。
東京や神奈川、愛知などは1200万。鹿児島などでは900万円くらいからほぼ上限となっていますので今回の上限変更の影響を受けます。
詳しくはお住まいの自治体にお尋ねください。
健康保険を安くするテクニック5選+1
それでは健康保険を少しでも安くする方法はあるのでしょうか?
ちなみにこのサイトで何度もご紹介している個人型確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済、国民年金基金に加入しても国民健康保険は減らすことができません。
これらの制度は所得税と住民税に対しては効果絶大ですが、国民健康保険にはまったく効果がないんですよ。
そのためこれらの制度を使って節税している方したら国民健康保険は本当に高く感じるのです。
私もです(笑)
それでは健康保険を安くするテクニックを見ていきたいと思います。
国民健康保険組合に加入する
まず一番始めに検討したいのが国民健康保険組合に加入する方法です。
国民健康保険が市町村(県単位に平成30年度から変更)ごとの制度なのに対して、国民健康保険組合は同じ業種や職業の人ごとに組織される健康保険になります。
これは同じ業種の人しか加入できませんので(無職の人などがいない)ため一般の国民健康保険よりも負担金額が安くなる場合がほとんどになります。
今現在、国民健康保険組合は全国に164組合(建設業32組合、三師92組合、その他一般40組合)あります。
一覧は下記をご覧ください。
三師とは医師、歯科医師、薬剤師のことです。
その他一般には様々な業種があります。
例えば弁護士、税理士、理容、芸能、食品、衣料品、質屋、青果卸など。
それぞれの国民健康保険組合ごとに仕事内容や地域の制限があります。
それらを満たした場合にだけ加入することが出来ます。
条件は組合ごとに定めていますのでバラバラなのが現状です。
該当しそうな国民健康保険組合がある場合には問い合わせをしてみるとよいでしょう。
昔から営業しているところがほとんどでWEBページも持っていないところも多いですが・・・
ちなみ健康保険組合は原則として新規設立が認められていないため164組合に該当しそうな組合がない方は期待薄です。
そのため昔からの業種ばかりで新しい業種はほとんどありません・・・
世帯合併
世帯合併という方法で健康保険を減らせる可能性もあります。(地域によりですが・・・)
世帯合併とは2世帯住宅などで1つの家族で2つの世帯を持っている場合に1つに合併してしまうことです。
世帯合併を行うと「平等割」という世帯単位にかかる保険料を減らすことができます。
また、世帯全体の年収が上限に達する場合も節約効果があります。(上限額は地区により異なります)
クレジットカードやQR決済で支払う
もうひとつの方法はクレジットカードで支払うことです。
大きく減らせるわけではありませんが、少しでもお得に支払うことができます。
QR決済などポイントが貯まる支払い方法を使う方法です。
このあたりは住民税などお得に払う方法と同じですね。
がお得です。どんどん改悪が進んでいてお得な支払い方法は減っています・・・
法人化する
もう一つ考えられるのが法人化してしまうってことです。
法人化すれば健康保険は健康保険組合や協会けんぽに加入することになります。
健康保険組合や協会けんぽに加入すると計算方法が違うため一概には言えませんが、前述のとおり、まず加入者層の違いがありますので法人化することで保険料が下がる可能性が高いです。
国民健康保険が高い理由でお話したように健康保険組合や協会けんぽの場合は会社が半分負担してくれますが、自分の会社の場合、会社が半分負担してくれるといっても結局は同じことですからそれほど大きな意味はありません。
しかし、その点を除いても健康保険組合や協会けんぽに加入した方がお得な点が多いのです。
例えば、国民健康保険は世帯人数で保険料は変わるのですが、協会けんぽや健康保険組合の場合、人数を問わず被保険者の収入(標準報酬月額)のみで保険料が決まりますので、家族が多い人はより有利になる仕組みとなっています。
また、配偶者が働いていない場合には第三号被保険者となり、その方の国民年金保険料を支払う必要がありませんので家族全体の社会保険で考えると法人化した方が安くなるケースの方が多いでしょう。
その他、健康保険組合や協会けんぽには合って国民健康保険にない出産手当金や育児休業の保険免除、傷病手当金などもあります。
また、健康保険組合の場合にはかなり福利厚生のサービスが充実しています。
これらの有無が大きいですね。
もちろん法人化すれば個人事業主のころは所得税だったのが法人税になったり、赤字でも払う税金があったり、自分の給料が経費(役員報酬)になったりいろいろな変更点がありますのでそれらをトータルで考える必要はありますけどね。
法人化について詳しくはこちらの記事も御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//38437]
健康保険組合と協会けんぽでも結構違う
また、協会けんぽと健康保険組合でも結構違います。
これも加入者層の違いが大きいです。
たとえばIT系の健康保険組合は若い加入者や独身の人(扶養者がいない)が多く、医療費負担が少ないことから保険料が安かったりします。
福利厚生等のサービスもよかったりしますね。
また、大企業の健康保険組合も加入者の給料水準が高い方が多いため各自の負担で考えると低く押さえられています。
一方、協会けんぽは健康保険組合に入れない、入らない企業の方用の健康保険ですから比較すると高くなっています。
市役所の窓口で相談する
災害、病気、失業など何かしらの理由により前年と比べて所得が大幅に減少している場合や減少することが見込まれている等の場合には市町村が保険料の減免措置を認めることがあります。
また、障害者手帳などをお持ちの方も減免が認められる自治体もあります。
もちろん審査がありますので全員が受け入れられるわけではありませんが、保険料の負担が大きい場合には相談してみるのも良いでしょう。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//25432]
また、自治体にもよりますが住民税の非課税世帯の場合、減免措置が得られることがあります。最寄りの自治体に確認してみてください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//16348]
経営セーフティ共済に加入
最後は+1として事業をやっている方にだけ使えるテクニックを紹介しましょう。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)を使うという技です。
経営セーフティ共済は独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する公的な制度で、取引の倒産などに備えるためのものです。
ポイントは全額経費扱いとなることです。
個人型確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済、国民年金基金などの方法は所得控除の対象ですから国民健康保険を下げる効果はありません。
しかし、経営セーフティ共済は経費扱いのため掛け金を払えば払うほど個人事業主ならば国民健康保険や所得税、住民税、事業税を下げることができます。
また、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできるメリットもあります。
掛け金は5,000円から200,000円の間で選ぶことができます。
また、途中で増減させることも可能です。
掛金は12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
ただし、、、弱点もあります。
それはイデコや小規模企業共済のようにもらうときの税制優遇がないことです。
そのためもらうタイミングに注意しないとその時の国民健康保険や所得税、住民税、事業税がどんと上がってしまう可能性があるということなのです。
そのためこの方法は税金や健康保険を恒久的に減らすのではなく、税金や健康保険の支払を今ではなく将来に繰り延べることができる制度と思うのが正解かもしれませんね。
例えば赤字の時期などがあればそのときにもらうなど工夫すればもらうときも大きな問題にはならないでしょうが。
経営セーフティ共済について詳しくはこちらをご覧ください
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//15425]
詳しくは下記の記事を御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//14125]
まとめ
今回は「国民健康保険が来年度からまたもや値上げへ。対策を考えよう」と題して国民健康保険の値上げについてみてきました。今年も都道府県単位化の影響もあり、値上げする自治体が多かったです。さらに来年もか・・・って感じですね。
そうはいってもどうしようもありませんから、自分でとれる対策をしっかり押さえて少しでも節約しましょうね。
今回ご紹介した国民健康保険の上限引き上げ以外の税制改正は下記の平成31年度税制改正大綱のポイントを御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//21061]
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
ブログランキング参加中です。
![]()
にほんブログ村
最後まで読んでいただきありがとうございました。