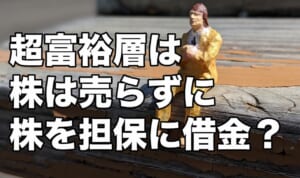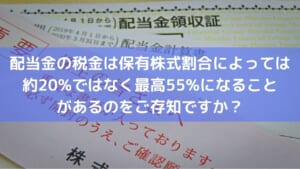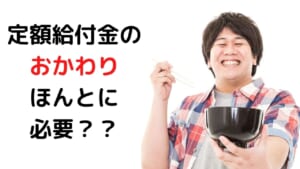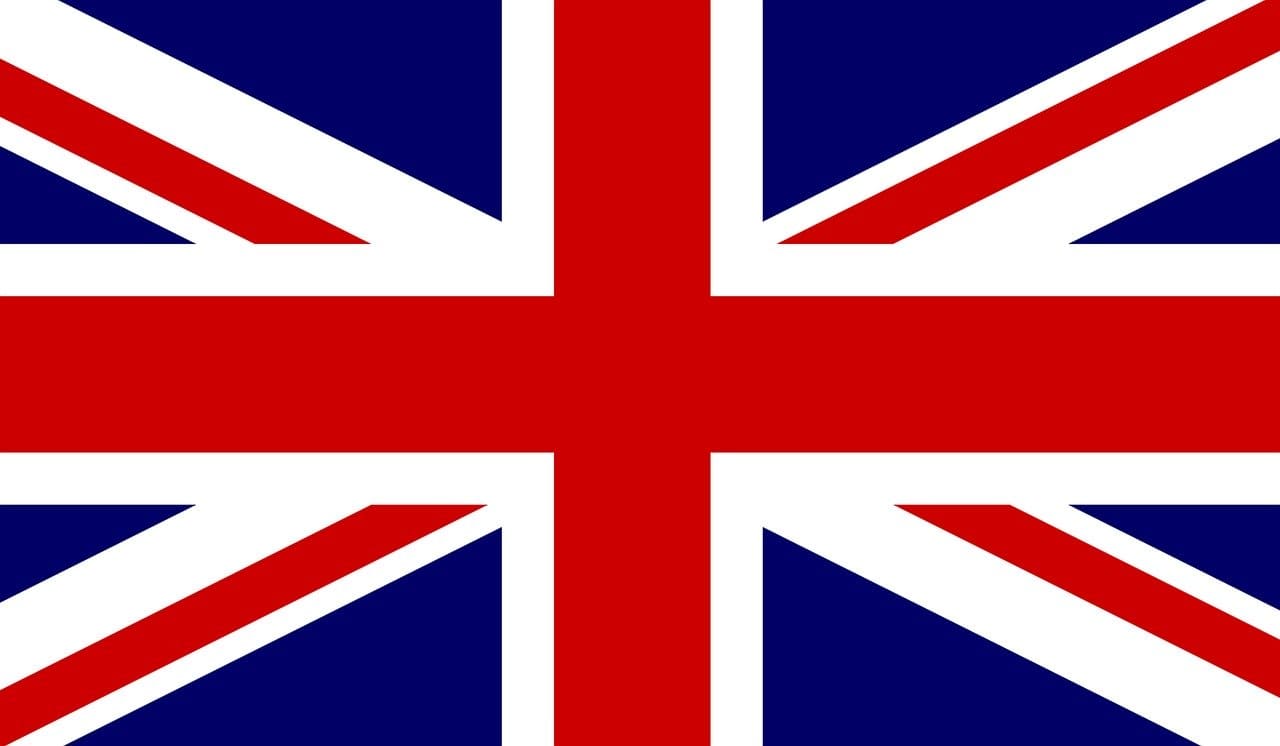先日、各社一斉に下記の報道がされました。
政府、与党は16日、期限付きで導入された少額投資非課税制度(NISA)について、恒久化を見送る方針を固めた。恒久化は金融庁や証券業界が求めていたが、現行制度は富裕層への優遇だとの指摘もあり、認めるのは難しいと判断した。
出所:共同通信 10/16「NISAの恒久化を見送りへ 投資非課税は「富裕層優遇」より
期限付きで導入されているNISA(少額投資非課税制度)について金融庁や証券業界などが要求してきた恒久化が認められないとのこと。
理由が「富裕層への優遇」という判断のようです。
個人的にかなり疑問でいっぱいとなりましたので今回はNISAは富裕層を優遇する制度なのか?について考えてみたいと思います。
※改革案がでましたね。かなり微妙な・・・詳しくはこちらの記事を御覧ください。
NISA(少額投資非課税制度)とは
NISA(少額投資非課税制度)とはその名前の通り、少額の投資ならば5年間非課税で運用できる制度です。
通常は株式投資や投資信託、ETFなどで利益がでればその利益に対して20.315%の税金がかかります。
しかし、NISA口座内で運用している場合には利益が出ても税金は免除(非課税)してくれるのです。
現在は非課税投資枠が120万円となっています。
例えば120万円分の株を買って200万円で売却したとします。
本来なら80万円分の売却益が出ていますので162,520円の税金がとられます。(特定口座で源泉徴収ありなら自動で差し引かれます)
しかし、これがNISA口座内ならば税金は0とかなり有利に投資できるってことです。
私もそうでしたが、120万円までの少額投資が対象ですから富裕層向けという認識はなく、投資初心者向けの制度という認識の方が多いと思われます。
NISA(少額投資非課税制度)は富裕層を優遇する制度なのか?
ここからはNISA(少額投資非課税制度)は富裕層を優遇する制度なのかという点について考えてみたいと思います。
今回の話を理解するためには株式譲渡益課税の歴史を知る必要があります。
まずはNISAの歴史から振り返ってみましょう。
株式譲渡益課税の歴史
財務省の「利子・配当・株式譲渡益課税の沿革」から株式譲渡益課税の歴史を見ていきましょう。
かなり変遷しているんですよ。
| 昭和22年 | 総合課税 |
| 昭和28年 | 原則非課税(回数多、売買株式数大、事業類似は総合課税) |
| 平成元年 | 申告分離課税26%、源泉分離課税20% |
| 平成13年 | 1年超保有上場株式等の100万円特別控除の創設 |
| 平成14年 | 特定口座制度創設 |
| 平成15年 | 申告分離課税への一本化 上場株式等に係る税率引下げ(26%⇒20%) 上場株式等に係る軽減税率(20%⇒10%) 上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度の創設 |
| 平成16年 | 非上場株式に係る税率引下げ(26%⇒20%) |
| 平成25年 | 上場株式等に掛かる軽減税率の廃止(10%⇒20%) |
| 平成26年 | NISA(少額投資非課税制度)スタート 100万円上限 |
| 平成27年 | NISA(少額投資非課税制度)上限改定(100万円→120万円) ジュニアNISAスタート |
日本の株の譲渡益課税はかなりその時々で変化しています。
当初は総合課税(給料など他の所得と合算して税額計算)としてスタート。
その後、長い期間「非課税」でした。
平成元年からは分離課税
平成15年からは20%に税率が引き下げされ、さらに軽減税率が導入され利益の10%が税金となります。
軽減税率って2019年10月からの消費税に係るものだけでなく過去には証券税制でもあったんですよ。
それが平成25年末まで続きます。
つまり、10年間は税率10%だったのです。
私はそのころから株をやっていますのでこの印象がとても強いですね。
そしてそれが富裕層優遇という批判が強かったこともあり、平成25年末で廃止になります。
その代わりに翌年、平成26年から導入されたのがNISA(少額投資非課税制度)なのです。
10%の軽減税率だとかなり有利な税制ですね。
特に当時、デイトレーダーなんかの話も目立ったこともありやり玉にあげられたんですよ。
そこで、それをやめる代わりに株式市場への影響も考えて100万円まで非課税よってしたんです。
つまり、この時点でNISAは富裕層優遇をやめようとして導入された制度なんですよね。
NISAの利用状況
金融庁の「NISA利用状況調査」によると2019年(令和元年)6月時点でNISAは1,161万8,539口座あります。
実に日本人の10人に1人が口座を開設しているという計算ですね。
ちなみにつみたてNISAが147万872口座です。
NISAの方が歴史が古いこともあり実は普及しているんですよ。
NISA口座の多くは開設だけ
ただし、これカラクリがあります。
それは多くの方がNISA口座を作っただけで使っていないのです。
私も頼まれたことが何度かありますが、銀行や証券会社ではNISA口座の開設にノルマがあるのです。
そのため口座開設だけでもしてって依頼を受けて口座開設をしたけど一切に使っていない人がかなり多いのです。
NISA口座の買付額は17兆593億2,467万円あります。
口座開設数が1,161万8,539口座ですから単純計算で1口座あたり151,423円となります。
買付額は2014年〜2019年までの5年間での利用枠内での買付金額の合計ですからかなり少ないことが分かります。
つまり、多くの口座は開設しただけと予想されるのです。
NISA利用金額の多くや高齢者
それでは稼働しているNISAの実際の買付金額を見てみましょう。
かなり買付金額をみると高齢者の割合が非常に高くなっています。
30歳代:8.8%
40歳代:13.4%
50歳代:16.9%
60歳代:28.8%
70歳代:22.2%
80以上:7.0%
出所:金融庁「NISA利用状況調査」より抜粋
NISAの買付金額の半分程度を60歳代、70歳代が占めているんですよね。
富裕層の定義はいろいろありますが、総務省が出している「家計調査」では金融資産残高の階級別の最高が4,000万円以上ですからそこを基準と考えると7割が60歳以上の高齢者です。
さらにこの層は日本全体で1割しかいませんが、4割の資産を保有している計算となります。
つまり、富裕層と考えられる高齢者の利用が多くなっているのがNISA口座なのです。
ですから「現行制度は富裕層への優遇だとの指摘もあり」という話も間違えてはいないと思われます。
富裕層の優遇をやめようとした制度なのに富裕層が使っている
NISAは元々富裕層の優遇をやめようとして導入された制度でした。
しかし、実際のNISAの利用者の買付状況を見ると高齢者が半数以上となっており、実質的に富裕層の優遇につながってしまっているという指摘もあながち間違えてはいないようなのです。
統計資料では年齢別にしかわかりませんから高齢者=富裕層と紐付けるのはちょっと無理あるかもしれせんけどね。
ただし、富裕層の多くは高齢者ですからそういう傾向にあるのは確かでしょう。
つみたてNISAは若者利用が多い
それではつみたてNISAはどうでしょう?
以下の通り、今回の話でもつみたてNISAについてはは期限の延長を議論されるようです。
廃止すれば株価に悪影響を与える恐れもあるため、制度設計を見直した上で時限措置で存続させる方法を模索する。若年層など幅広い世代に資産形成を促すために創設された長期積立枠「つみたてNISA」は期限の延長を議論する。
出所:共同通信 10/16「NISAの恒久化を見送りへ 投資非課税は「富裕層優遇」より
なお、つみたてNISAってなんだ?って方はこちらの記事を御覧ください。
つみたてNISAの始め方から金融機関の選び方、商品の選び方、出口戦略まで分かります。
つみたてNISAの利用状況
それではNISAと比較するためにつみたてNISA利用状況をの金融庁の「NISA利用状況調査」でみてみましょう。
2019年(令和元年)6月時点でつみたてNISAは147万872口座あります。
2018年にスタートしたばかりの制度ですからNISAと比較すると10分の1程度と少なくなっています。
つみたてNISAは実際に利用されている
つみたてNISAはNISAと違い実際に利用されている率が高いようです。
つみたてNISAの買付額は1780億8,925万円で口座開設数が147万872口座です。
単純計算で1口座あたり121,077円となります。
1年半で121,077円ですから掛け金額の差はあるにしろ多くの方は実際に利用していることが予想されます。
この辺りはがNISAとの大きな違いですね。
つみたてNISA利用の多くは若者
次につみたてNISAの実際の買付金額を見てみましょう。
かなり買付金額をみるとNISAと違い若者が多いことが分かります。
30歳代:26.5%
40歳代:28.8%
50歳代:18.4%
60歳代:10.1%
70歳代:3.9%
80以上:0.4%
出所:金融庁「NISA利用状況調査」より抜粋
20年非課税で投資ができる制度であるつみたてNISAは若者の利用がかなり多いです。
買付金額は20歳〜40歳代で70%近くを占めています。
若年層など幅広い世代に資産形成を促すことを目的とした制度として機能していることが分かりますね。
この世代はそれほど富裕層がいませんから富裕層優遇とは言えませんから今後も制度が継続する可能性が高そうです。
私ならこうする。NISA制度の改革案
完全な私見ですが、私ならNISA制度の改革はこうします。
つみたてNISAでも株、海外ETFなどを買えるようにする
こうすれば現在のNISA口座を利用している方からの不満もそれほど出ないでしょうし、株価に悪影響も少なく済むのではないでしょうか?
ただし、つみたてNISAのメリットの一つである対象となっている投資信託は金融庁が選別したものだけという点がちょっと失われてしまいますけどね。
その対策として
してもよいかもしれませんね。
投資信託と同様に財務状況や規模などの条件を決めて選別すればよいでしょう。
個人的には海外ETFが買いたいんですよね・・・
まとめ
今回は「NISAは富裕層を優遇する制度なのか??恒久化見送りで制度設計見直しへ」と題してNISAは富裕層を優遇する制度なのかという点について考えてみました。
個人的にはNISAは富裕層優遇のルールでもなんでもないと思いますし、実際そうでない方も多く利用しています。しかし、統計資料なんかを見る限り富裕層を優遇する制度と捉えられてもおかしくないな・・・って感じてしまいましたね。
ただし、現行制度は富裕層への優遇だとの指摘してる人がどれだけいるのかは疑問ですね。NISA投資できるのは年に上限120万円ですしね・・・
本音は年金だけだと2000万円足りない問題で金融庁が株を売りたいだけだろうという批判なんかもありましたから、厳しい判断になってしまったのかもしれません。
こう判断されている以上、今後は制度改革なども考えれますね。
個人的には今から始めるならNISAよりもつみたてNISAの方がおすすめですね。
長期的に投資をするならばこちらのほうが税制優遇期間も長いですからね。
iDeCoと合わせて老後への対策として有効です。
つみたてNISAはまだ統計資料が出ていませんのわかりませんが、iDeCoの加入者は年金だけだと2000万円足りない問題で大幅に増えていますね。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//37952]
つみたてNISAに加入するならこのSBI証券が有力
つみたてNISAは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)ほど証券会社の差はありません。
選ぶ際のポイントは取扱商品と注文の仕方です。その点を加味するとSBI証券が有力となります。
SBI証券はクレジットカードでの購入等は今の所できませんが、商品ラインナップや注文の仕方などは一番優れていますので楽天カードを使っていない、使わない方には筆頭候補となるでしょう
SBI証券はなにより注文の自由度がかなり高いのがいいですね。
資料請求等はこちらから
[afTag id=46620]
最後まで読んでいただきありがとうございました。
フェイスブックページ、ツイッターはじめました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです