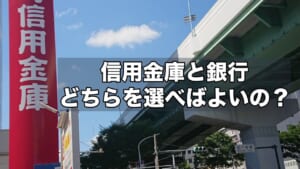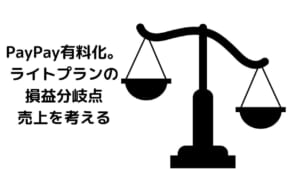日本にはいろいろな税金があります。
消費税、所得税、法人税、住民税、固定資産税などは知っている方も多いでしょう。
他にも酒税、たばこ税、ガソリン税、入湯税、出国税などいろいろなところで税金が掛かっているのです。
また、あまり知られていませんが、「個人事業税」という税金があります。
今回はそんな個人事業税のお得な支払い方法を解説します。
キャッシュレス決済が台頭したこともあり昨年までとかなり違ったお得な支払い方法となってきているんですよ。
なお、本記事のYou Tube版はこちらからご覧いただけます。
個人事業税とは
個人事業税とは地方税の一つで事業を行う場合に様々な行政サービスを受けていることから、その行政経費の一部を個人で事業を行う人に負担していただくという趣旨から課税されるものです。
つまり、個人で事業を行う人に課せられる税金ということです。
ただし、変なルールがあり対象外の事業も多いという不公平さ・・・
個人事業税の対象
個人事業税は確定申告をした人全てが対象となるものではありません。いくつか条件があります。
逆に言えばその条件を満たしてしまったら個人事業税を払う必要があるのです。
個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業および第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
出所:地方税法 第72条の2
個人事業税は上記のように個人で第一種事業、第二種事業、第三種事業を行っている場合に課せられます。
具体的には以下の業種です。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
| 区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
| 保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
| 金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
| 物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
| 不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
| 製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
| 電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
| 土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業 (むし風呂等) |
- | ||
| 電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
| 運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
| 第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
| 第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
| 歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
| 薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
| 獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
| 弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
| 司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
| 行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
| 3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 | 装蹄師業 | |||
| その他の医業に類する事業 | |||||
全部で70業種が指定されています。かなり幅広いのでほとんどの方がどこかしらかの対象となってしまうのです。
ただし、これ作られたのはかなり古いものです。
そのため新しい業種などは反映されていないんですよ。
例えばYouTuberやアフィリエイター、請負SEなどですね。
それら新しい業種の場合には自治体毎の判断によって無理やり上記と判断しているケースも多くあります。
逆に上記リストにないからと個人事業税が掛からないケースもあります。
ですから新しい業種の場合には、地域によって同じ仕事をしていても個人事業税が掛かるかどうかが異なるのです。
個人事業税の金額
個人事業税は以下の計算方法で算出されます。
290万円を引いているのは事業主控除です。
それを超えた分に課税されるということですね。
逆に言えば290万円以上の所得がない場合は個人事業税を納める必要はありません。
税率は前述のとおり業種により3%〜5%となっています。
申告方法等、その他個人事業税について詳しくはこちらの記事で解説しておりますので合わせてご覧ください。
個人事業税のお得な支払い方法
それでは個人事業税のお得な支払い方法を見ていきましょう。
なお、個人事業税は県の税金ですから、県ごとに利用できる支払い方法が異なります。
今回ご紹介する中で自分の住んでいる自治体で使える支払い方法はどれで、どれがお得なのかを確認して利用するとよいでしょう。
au Pay請求書払い
まずは現在、本命に近い方法です。
au Payの請求書払いです。
こちらは200円につき1ポイント付与となっています。
さらに「au PAY ゴールドカード」ならau Payへのチャージ時に2%付与されますので、実質2.5%還元となります。(通常のau Payカードはチャージ時1%で実質還元率1.5%)
実質1.5%還元(au Payカードの場合)
かなり高い還元率となっています。
ただし、納付書1枚の合計金額が30万円以下という条件がついています。
それを超える場合は納付書を分けてもらうのを交渉すると自治体によっては受けてもらえるケースもあります。
また、auPayの請求書払はまだまだ利用できる自治体はあまり多くないんですよ。
まずは自分の住んでいる自治体で使えるのかを確認してみましょう。
nanaco+セブンイレブン
次はセブンイレブンで利用できるnanacoです。
nanaco自体は個人事業税を支払ってもポイントが付きませんが、チャージするときにポイントが付きますので少しお得に利用できるのです。
例えばリクルートカードならば1.2%のポイントが付きます。
ただし、nanacoは個人事業税の支払いに使うにはnanacoはチャージの上限が5万円(1回目3万)と低いのが厳しいです。
それを超える場合は、納付書を分けてもらうのを交渉すると自治体によっては受けてもらえるケースもあります。
LINEPay
次はLINEPayです。
LINE Pay残高での支払いではポイントは付きませんが、チャージ&Payという機能を使うと対応クレジットカードを連携してチャージ不要で利用でき、ポイント還元を受けることができます。
対象となるクレジットカードは三井住友カードが発行するVisaブランドのクレジットカードに限定されますが、0.5%の還元となります。
auPayほどではありませんが、少しでも還元がつくのはありがたいですね。
ただし、税金/保険において、1回あたりの支払につき5万円を超える分はポイント還元の対象外となの注意書きがあります。
また、こちらもまだまだ利用できる自治体はあまり多くはありません。少しずつは増えていますが・・・
クレジットカードでの納付
自治体によってはクレジットカードでの納付用サイトを設けており、そちらで納付することも可能です。
クレジットカードによっては税金を支払ってもポイントが付きますのでその分お得ですね。
ただし、ほとんどの自治体サイトはクレジットカードで支払うと手数料が発生します。
その手数料とポイント還元額を勘案して本当にお得なのかは考える必要がありそうです。
還元率が低いクレジットカードや、税金の支払いは還元がないクレジットカードを使うと逆に損な支払い方法となってしまいます。
ちなみに利用者の多い楽天カードは通常1.0%の還元ですが、税金については0.2%還元しかもらえないように2021年6月から改悪されていますのでご注意ください。
個人事業税の利便性の高い支払い方法
次はお得さはありませんが、利便性が高い支払い方法をご紹介しましょう。
PayPay
まずはPayPayです。
やり方は簡単。
これだけで支払いが完了します。
コンビニや銀行などに出向かなくても納付書のバーコードをスマホで読み取って手続きすれば支払いが完了してしまうのです。
かなり便利ですね。
ただし、お得度はなくなってしまっています。
もともとPayPayは請求書払いでお得度がかなり高かったのですが、2022年4月からポイント還元がなくなってしまったのです。
利便性は良いのでポイントは要らない。利便性だけあれば・・・って方は利用しても良いかもしれません。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
PayB(ペイビー)
もう一つがPayB(ペイビー)というサービスを使う方法です。
PayBはPayPayなどと同じくバーコードから読み込んで連携した銀行からお金を引き落としができるサービスです。
ポイントは付きませんが、利便性は高いサービスですね。
また、対応している自治体も多いのが魅力となっています。
・お金が管理しやすい
ペイジー
PayBと似た名前のペイジーというのもあります。
こちらはバーコードを読み取るわけではありませんが、納付書に記載されている「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」という4つの番号を入力することでインターネットバンキングやATMから支払うことができる仕組みです。
ペイジーもポイントは付きませんが、手数料等は掛からず簡単に払えますから利便性は高いサービスですね
こちらも対応している自治体は多いですね。
地方税共通納税システム(eLTAX)
次は地方税共通納税システム(eLTAX)です。
これは自宅やオフィスから、地方税の納税手続きを電子的に行える仕組みです。
少し手間はかかりますが、コンビニや銀行に支払いにいくよりは楽ですね。
口座振替
最後は口座振替です。
事前に金融機関の窓口での手続きは必要ですが、それ以後は自動的に引き落としされますから支払う手間はかかりませんね。
なお、振替日は原則納期限の日となりますので払い忘れや早く払いすぎてしまうってことはありません。
まとめ
今回は「個人事業税のお得な支払い方法を解説【2022年版】」と題して個人事業税のお得な支払い方法についてみてきました。
2022年10月からはインボイス制度も始まりますし、売上300万円以下は雑所得扱いとなるなど個人事業主にとっては向かい風となる制度変更が続いています。
すこしでもお得に個人事業税を支払いましょう。
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。