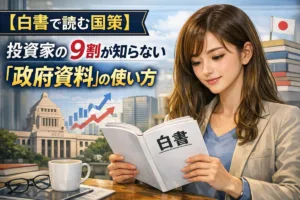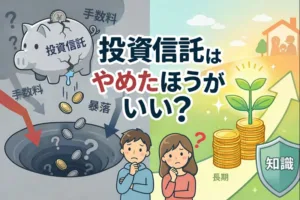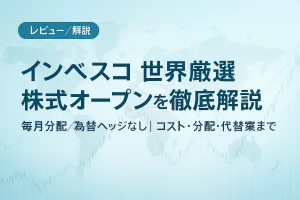2025年4月現在、金融庁は高齢者向けの新たなNISA制度「プラチナNISA(仮称)」の創設を検討しています。
金融庁は高齢者向けの少額投資非課税制度(NISA)を創設する検討に入った。2026年度の税制改正要望に盛り込む方向だ。運用益などを分配金として毎月払い出す「毎月分配型」の投資信託を高齢者に限定して対象に加える案が浮上している。プラチナNISAと銘打ち、高齢者が運用資産を計画的に活用できるようにする。
出典:日経新聞 「プラチナNISA」創設へ 金融庁、高齢者向けに毎月分配型追加
この制度は、毎月分配型の投資信託をNISAの対象に含めることを主な目的としており、2026年度の税制改正要望に盛り込まれる見込みです。
まだ、詳細は不明な点が多いですが、高齢者が運用資産を計画的に活用できるようにするための制度設計が進めらるようです。
今回はプラチナNISAについて考えてみたいと思います。
プラチナNISAとは?
プラチナNISAは、高齢者が運用資産を計画的に活用できるようにするための新たなNISA制度です。
具体的には、これまでNISAの対象外であった毎月分配型の投資信託を、高齢者に限定して対象に加えることが検討されています。
この制度は、年金を主な収入源とする高齢者が、毎月の生活費の下支えとして運用益を活用できるようにすることを目的としているのでしょう。
プラチナNISAのメリット
毎月分配型投信のNISA対象化
これまでNISAの対象外であった毎月分配型の投資信託が、高齢者に限定してNISAの対象に加えられることで、毎月の生活費の補填として運用益を活用しやすくなります。
元々金融庁は効率の悪い毎月分配型を敵視し狙い打つようにNISAやつみたてNISAでは排除してきましたが、最近は4ヶ月に一回の分配ですが、楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)やSBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)が大人気となっているのもこの話に大きな影響を与えていそうです。(NISAの成長枠では買えます)


プラチナNISAの注意点
まだプラチナNISAの詳細がわかっていませんのでなんとも言えない部分がありますが、注意点もいくつかあると思われます。
タコ足分配に注意
毎月分配型の投資信託には、信託報酬が高い商品や、元本を取り崩して分配金を支払う「タコ足分配」と呼ばれるものも存在します。
これらの商品は、資産の減少ペースを早めてしまう可能性があるため、注意が必要です。
高コストな商品に注意
また、毎月分配型の投資信託は成績のわりに高コストな商品も多いことから、インデックスファンドや株を直接買う場合と比較したときをしっかりチェックする必要があります。
元々金融庁がつみたてNISAから締め出したり、注意喚起を行っていた商品ですしね。

金額の自由度が低い
毎月分配型の投資信託は、分配金額が運用会社の裁量で決定されるため、投資家自身が取り崩しの間隔や金額を自由に設定することができません。
前述したようにタコ足だと徐々に分配を出すのがきつくなっていきますしね。
高齢者がプラチナNISAを活用する際のポイント
プラチナNISAを始める際に考えたいことをみていきましょう。
金融ジェロントロジー(金融老年学)
シニア世代は若い人に比べて資判断も間違えてしまうことが多くなります。
また、リスク許容度が低いとされており、大きな損失が運用意欲を失わせる可能性があります。
そのあたりも含めて始める前に家族に相談するのがおすすめです。
高齢者の投資判断については金融ジェロントロジーとして問題になっているんですよ。

また、認知症についても考えておく必要がでてきそうです。

リスクの高い商品を避ける
シニア世代は、株式だけの投資信託のようなリスクが高めの商品を選ばないほうが無難です。
引き出しまでの期間も短くなります。
そのあたりを考えると大きな波がある金融商品は少しリスキーなんですよ。
少し前にでていた相続税免除の話と今回出てきたプラチナNISAを絡めてくるのでしょうか・・・

投信定期売却サービスと比較して
毎月分配型の投資信託ではなく、「投信定期売却サービス」などを利用すれば、取り崩しの間隔や金額を投資家自身が自由に設定できるため、より柔軟な資産運用が可能です。
個人的には毎月分配型の投資信託を選択するよりも一般的なインデックス型の投資信託を選んで、「投信定期売却サービス」で必要な金額を取り崩していくほうがおすすめです。
まとめ
今回は「プラチナNISA(高齢者向けNISA)が創設??毎月分配型投信には注意してください・・・」と題してプラチナNISAについてみてきました。
プラチナNISAは、高齢者が運用資産を計画的に活用できるようにするための新たなNISA制度として検討されています。
毎月分配型の投資信託がNISAの対象に加えられることで、毎月の生活費の補填として運用益を活用しやすくなります
しかし、高コストな商品や柔軟性の欠如などの注意点も存在するため、制度の詳細を理解し、慎重に活用することが重要です。
今後、金融庁からの正式な発表や制度の詳細が明らかになることが期待されます。
最新の情報を常に確認し、自身のライフプランに合った資産運用を心がけましょう。
投資を始めるならSBI証券がおすすめです。