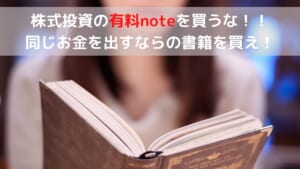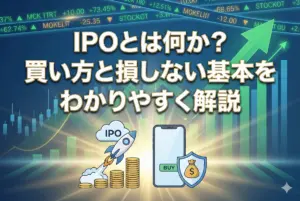国内の推計では、1億〜5億円の「富裕層」と5億円以上の「超富裕層」は合計約165.3万世帯(2023年時点推計)で、過去最多水準となりました。
それでも富裕層・超富裕層のボリュームは全体の約3%。
SNSで見ていると億り人が多発していますが、まだまだ少数派なんですよ。
今回は普通の会社員(サラリーマン)が億り人になるまでのロードマップを考えてみましょう。
なお、億り人という言葉にきっちり定義があるわけではありませんが、今回は純金融資産1億円以上(現金・株式・投信・債券等の合計から負債を差し引いた額)としてみていきます。
現実感のある「億り人」ルート:3本柱で考える
それでは億り人になるためのルートを考えてみましょう。
柱①:フロー(稼ぐ力)— 年収×昇給×副収入
まず重要なのが稼ぐ力です。
- 本業の昇給・昇格で可処分所得の逓増を狙う。
- 転職・資格・社内評価の可視化で年収レンジの上方シフト。
- 副業(月3〜10万円)は投資余力を底上げ。
とりあえず、本業や副業でいかに稼ぐかを考えましょう。
今流行りのリスキリングとかも有効です。

柱②:ストック(貯蓄率)— 固定費ミニマム化
次は節約し、貯蓄にいかに回すかってこと。
ムダ遣いをしかいことがなにより重要です。
- 住居・車・通信・保険の固定費4大項目の見直しで貯蓄率20〜30%を標準化。
- 「家計の余白=投資可能額」。投資の再現性はここで決まります。
柱3の投資に回す金額がここまでの部分で決まってきます。
節約して投資に回すって考え方ですね。
節約のポイントはこちらの記事でまとめております。
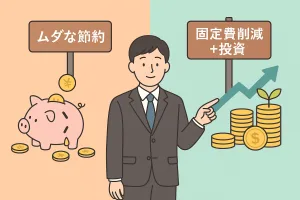
柱③:運用(リスク資産×非課税)— 新NISA・iDeCoの徹底活用
最後は投資です。
まずは新NISAやiDeCoの税制優遇がある制度を優先して使いましょう。
- 新NISA:生涯非課税1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)。年間360万円(つみたて120万+成長240万)が上限。売却で翌年枠復活。制度は恒久化。
- iDeCo:掛金は全額所得控除で手取り増効果。※上限は職制・企業年金有無で異なる(2027年から変更予定。詳しくは下記記事を御覧ください。)

「億り人 何年?」積立額×利回りで到達年数を概算
それでは実際に投資をした場合に何年で億り人になれるかを考えてみましょう。
前提:初期資金0、毎月末積立、年率は長期の仮定(物価調整なし/税引き考慮なし)、計算は月次複利。
| 月額積立 | 想定利率 | 1億円到達 目安年数 |
|---|---|---|
| 5万円 | 3% | 約60.3年 |
| 5万円 | 5% | 約45.4年 |
| 5万円 | 7% | 約37.2年 |
| 10万円 | 3% | 約42.1年 |
| 10万円 | 5% | 約33.3年 |
| 10万円 | 7% | 約28.1年 |
読み方:たとえば「毎月5万円×年5%」で約45年。「毎月10万円×年7%」で約28年となります。
例えば大学卒業した23歳で始めたとすると前者で68歳で億り人、後者で51歳で億り人になる計算となりますね。
想定利率7%とか無理だろって思われるかたもみえるかもしれませんが、アメリカの株価指数のS&P500は過去65年の平均が年率10%くらいなんですよ。(ここ10年でみても年率10%程度)
また、日本の年金などを運用するGPIFも債券を半分いれた固い投資ながら年率4%を超えています。
ですから年率3%〜7%はそこまで無理な数字ではないんですよ。(あくまで過去はそうだったというだけですが)
ちなみにNISAやiDeCoでS&P500に投資をすることも、GPIFの運用を真似をすることも容易です。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

※下記の本の作者のように短期で大きく狙う投資手法も世にありますが、再現性・ドローダウン耐性の観点から本稿は長期積立を主軸とします。
年代別億り人ロードマップ(20代/30代/40代/50代)
それでは年代別に考えてみましょう。
20代:時間が最大の味方
20代は時間が最大の武器です。
複利は時間があればあるほど有利なんですよ。
- 目標:貯蓄率20〜30%→月5〜10万円積立を死守。
- 新NISAはつみたて枠を満額→余力で成長枠。iDeCoで節税+長期複利。
- スキル投資:30代で年収レンジを1段上げる準備。
ちなみに子どものうちからNISAをやればかなり早い段階で億り人になることが可能だったりします。
複利と時間の関係性がよくわかりますね。

30代:年収のカーブを上げる
30代は一番脂が乗っている時期です。
できるだけ投資、本業を頑張りましょう。
- 目標:貯蓄率25〜35%。月10〜15万円に積増し。
- 住宅購入は「学区・通勤・資産性」の三点で判断。過大ローンは複利を殺す。
- 新NISAの成長枠も計画的に活用。
40代:ピーク給与×教育費の攻防
40代はお金がかかる時期です。
そこで投資をやめないというのも重要ですね。
- 教育費ピークでも積立は止めない(最低ライン死守)。
- 社内ポジション・転職で年収の天井を引き上げ。
- リスク資産は分散(国内外株式・債券・REIT等)と非課税枠回転で効率化。
50代:守りを固めつつ最終コーナー
50代まで投資を続けてこればそれなりの金額になっているはずです。
そろそろ出口戦略も考える時期かも
- ポートフォリオのボラ抑制(比率調整・リバランス)。
- 相続・贈与・退職給付・持株会売却計画など出口設計も同時に。
- 富裕層に近づいたらリスク管理と分散を再確認(NRI指摘の“いつの間にか富裕層”は金融知識の空白に注意)。
ケース別シミュレーション(ざっくり版)
次はケース別でみてみましょう。
ケースA:世帯年収700万円
固定費最適化で貯蓄率30%→月17.5万円投資。
年5%なら約24年で1億円到達目安。
ケースB:年収500万円(単身)+副業3万円
固定費圧縮で月10万円投資。
年5%なら約33年。
ケースC:初期資金300万円+月12万円
年5%なら約29年。
初期資金は「複利の助走距離」を短縮。
上記は単純化した計算です。税・物価・手数料・実際のボラを考慮し、安全マージンを確保してください。
「攻めすぎない」ための5ルール(失敗回避)
なお、億り人を目指すために無理しすぎないというのも重要です。
生活防衛資金
まず生活防衛資金は必ず確保しましょう。
6〜12か月分が理想。
できれば別口座で厳守すると確実です。
積立の自動化
積立は自動化するのが理想です。
自分で投資をする形式だと心理が働いてしまいマイナスとなりかねません。
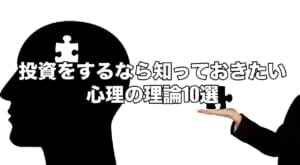
分散とリバランス
なにか1つの株に積み立てるというのは、当たれば大きいですがリスクも大きいです。
安全に投資をするなら分散投資が理想。
できれば年に1回程度リバランスもすると良いでしょう。
レバレッジ・集中投資は上限ルール
ここだ!って場面ではレバレッジを掛けたり、集中投資をするのもありですが、当然ハイリスク・ハイリターンです。
総資産の○%まで等の上限ルールを設けると安心です。
情報源の一次化
億り人を目指そうとすると様々な誘惑、詐欺などがよってきます。
制度・統計は必ず公式資料で再確認しましょう。
また、インフルエンサーなどの煽りを信じるのはやめましょう


よくある質問(FAQ)
よくいただく質問もみていきましょう。
いくら年収があれば億り人になれますか?
年収より貯蓄率と継続が決定要因。
本業の年収はフロー、投資余力=貯蓄率×年収。
日本人の平均給与460万円でも、支出最適化+副収入+非課税活用で十分到達圏です
富裕層(億り人)の“割合”は?
推計上の純資産1億円超の富裕層・超富裕層は約165.3万世帯(2023)。
株高や円安、相続移行、首都圏マンションの高騰などの要因もあり過去最多水準となっています。
世帯総数約5,445万からみると概ね数%(約3%)規模です。
まだまだ少数派ではあるんですよ。
重要ポイント
「誰でもすぐ1億円」ではありません。ただし長期×積立×分散に非課税のてこを組み合わせると、会社員でも十分現実的な到達圏です
インフレや円安はどう見る?
名目リターンが伸びても実質(インフレ控除後)で管理を。
一部を外国株や債券など外貨資産にしておくのは為替分散の一手
まとめ
今回は「普通の会社員が億り人になるには?:富裕層の割合・必要資産・到達何年でわかるロードマップ」と題して普通の人が億り人になるための話をみてきました。
再現性の高い「億り人」は、①稼ぐ力の上振れ、②貯蓄率の固定、③非課税×長期分散の面で積む、の三位一体。
何年かかるかは「月いくら投資に積めるか」で決まります。
5万円×年5%で約45年、10万円×年7%で約28年が一つの目安。
無理のない速度で続ければ、普通の会社員でも十分到達圏です。
頑張りましょう。
NISAやiDeCoならSBI証券がおすすめですよ。