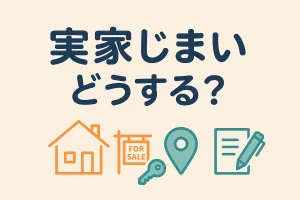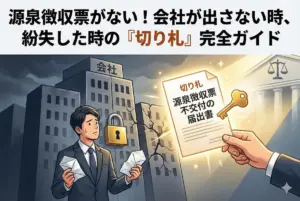先日、確定拠出年金について新聞各紙で報道がありました。厚生労働省が確定拠出年金の60歳までの加入期間を65歳まで延長する検討に入ったという記事です。具体的に年明けから議論し、2020年の通常国会で改正案を提出する予定とまでなっていますのでその方向で動くのは高い確率な感じですね。
実はそれと合わせて出ている情報として確定拠出年金の掛金の限度額引き上げについても議論すると報道がされています。どこの新聞も65歳までに延長するという報道が中心となっていますが、こちらもかなり大きな影響があります。
今回は確定拠出年金の掛金の限度額引き上げされた際の影響や対策を考えてみます。
確定拠出年金の掛け金には限度額がある。現在は個人型では最高で自営業者など国民年金加入者の月6万8000円、企業型で月5万5000円だが、この引き上げも併せて議論する。ただ、加入期間を延長したり限度額を引き上げたりすると税制優遇の幅が広がるため、財務省との調整が焦点となりそうだ。
出所:毎日新聞 10月28日
65歳までの納付期間延長について詳しくは下記記事を御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//17596]
確定拠出年金の掛金限度額が引き上げられるとどうなる
現在、確定拠出年金(個人型、企業型とも)の掛金限度額はその人の国民年金保険の加入状況とお勤めの会社のその他の年金の有無で変わって来ています。
もし掛金の限度額が変わればメリットもデメリットなど様々な影響が考えられます。対策も含めてそれぞれみていきましょう。
現状の掛金限度額
具体的には以下のとおりです。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の掛金限度額
まずは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)です。
| 国民年金の加入状況 | その他年金の有無等 | 掛金限度額 |
| 第一号被保険者 | 自営業者等 | 月額6万8千円(付加年金なし)
月額6万7千円(付加年金加入) |
| 第二号被保険者 | 企業型DCのない会社の会社員 | 月額2万3千円 |
| 企業型DCに加入している会社員 | 月額2万0千円 | |
| DB加入者、公務員 | 月額1万2千円 | |
| 第三号被保険者 | 専業主婦等 | 月額2万3千円 |
企業型確定拠出年金の掛金限度額
次に企業確定拠出年金です。
| 併用している制度 | 掛金限度額 |
| なし | 月額5万5千円 |
| 退職一時金 | 月額5万5千円 |
| 中小企業退職金共済(中退共) | 月額5万5千円 |
| 確定給付企業年金 | 月額2万7千5百円 |
| 厚生年金基金 | 月額2万7千5百円 |
掛金限度額が引き上げられる場合のメリット
まず、メリットから見ていきましょう。いくつか考えられます。
所得控除が増え、所得税・住民税の節税効果大
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合には引き上げられて掛金を増やせばそれで所得控除も増えることになります。そうなれば所得税や住民税の節税に繋がります。
とくに会社員の場合には掛金の金額がかなり少ないのでこの効果をより実感できるでしょう。これはかなり大きいメリットになりますね。後述する懸念材料に問題がなければお金に余裕があれば限度額まで掛金を引き上げたいところですね。
老後資金が増える可能性
掛金限度額が増え掛金を増やせばそれだけ運用に回せるお金が増えることになります。運用に回せるお金が増えればそれだけ資金が増える可能性が高くなりますので老後資金に余裕が出てくる可能性が高いです。
こちらも大きいですね。
掛金限度額が引き上げられる場合の懸念材料
税金の減収による影響
記事にも税制優遇の幅が広がるため、財務省との調整が焦点とありましたが、メリットにあるように掛けられる金額が増えればそれだけ所得税・住民税が減ることになります。そうなれば財務省もそうですし、地方も減収することになります。
その場合に他でその部分をカバーするという話になればほぼプラス面しかない掛金限度額の引き上げとなります。
しかしそうでない場合が怖いですね。
例えば減った税収を調整するため退職金控除の削減や公的年金控除の削減なんて話がでてくる可能性もあります。
さらに最悪の事態としては税収確保のために特別法人税を復活なんてことになったら目も当てられません・・・これが個人的に最大の懸念かな。
特別法人税についてはこちらの記事を御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//12138]
退職金控除で内で収まるのか
また、前述の退職金控除の削減が起こらなくても掛金が増えれば将来もらえる金額も増えます。そうなれば退職金控除内で収まるのかを考えておく必要もあるでしょう。現在、公的年金控除は削減方向にありますのでできれば退職金控除内でもらえる範囲内で収めることも大きなポイントなりますので、掛金を増やせばよいというわけではなく退職金控除ないで収まるのかも検討して決めたいところですね。
退職金控除が途中で削減されたりすれば計算が狂ってしまうので怖いところではありますが・・・
国民年金基金とのバランス
また、ちょっと気になるのが自営業者についてです。記事では自営業者の上限について触れていますが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と同じ枠で国民年金基金という制度もありますが、こちらとのバランスをどうするかという問題があります。国民年金基金の上限も増やすとなれば同じく減収の可能性がありますしね。。。このあたりの舵取りは難しそう気もします。
掛金限度額が引き上げられた場合の対策
前述の用に掛金限度額が引き上げられ税収減を確定拠出年金関連でカバーしない場合は、余裕があれば掛金を増やすことがおすすめです。
問題は掛金限度額が引き上げられ税収減を確定拠出年金関連で補おうとする場合です。この場合は制度をしっかり確認して検討する必要があるでしょう。最悪の事態となれば掛金を減らすなどの策が必要となる可能性もあります。このあたりはまだなにも決まってないのでなんともいえませんが、制度の改正を注視しておく必要があるでしょうね。
まとめ
今回は「確定拠出年金の掛金の限度額引き上げ?引き上げされた際の影響や対策を考えてみる」と題して個人型確定拠出年金(iDeCo)や企業型確定拠出年金の掛金の限度額が引き上げられるかもという話を見てきました。
引き上げられることで様々な影響が考えられます。もちろん良い面もありますが、マイナス面になる可能性もあります。制度が変われば対策も変わってきますので注視しておく必要がありそうですね。
また、本サイト「お金に生きる」では確定拠出年金制度の変更などがあれば順次対策などを考えて行きたいと思います。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの5社から選ぼう
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。
しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。
簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。
私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券、大和証券、楽天証券の5択の中から決めます。
(※私が加入しているのはSBI証券です)
この5つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。
また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。
順番に見ていきましょう。
SBI証券
まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。
SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式、ひふみ年金、NYダウ、グローバル中小株、ジェイリバイブといった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。
選択の楽しさがありますよね。
また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。
[afTag id=36558]
マネックス証券
次点はマネックス証券 iDeCoです。
こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。
iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。
[afTag id=36661]
松井証券
松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。
その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。
こちらも有力候補の一つですね。
[afTag id=36658]
大和証券
大和証券 iDeCoは大手証券会社でありながら、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)にもかなり力を入れています。
他のネット証券と違い店舗が全国各地にたくさんあります。そこに魅力を感じる方にはおすすめできますね。
また、取扱商品もダイワつみたてインデックスシリーズなど信託報酬が安めの商品を取り揃えています。
[afTag id=36554]
楽天証券
楽天証券は楽天・全世界株式インデックス・ファンドや楽天・全米株式インデックス・ファンドといった自社の人気商品の取扱が大きなポイントとなっています。
この2つのファンドは人気ですね。
[afTag id=36651]
総合して考えるとこの5つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。
他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです