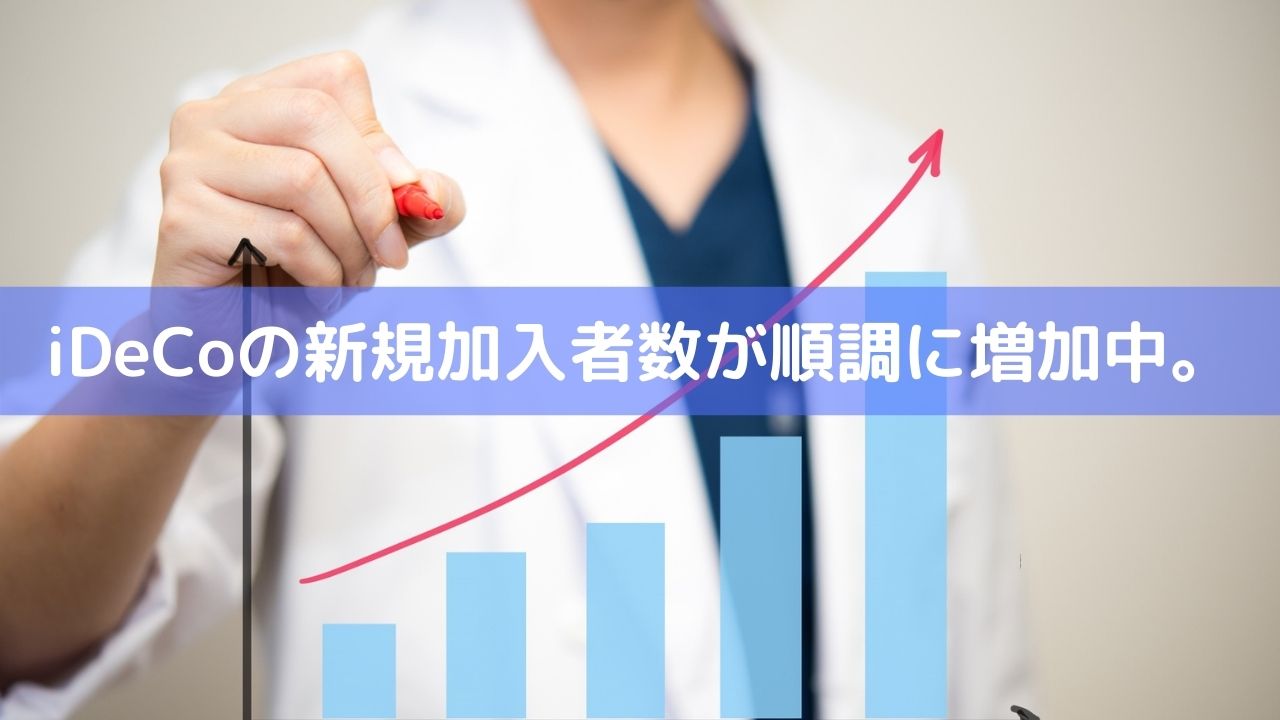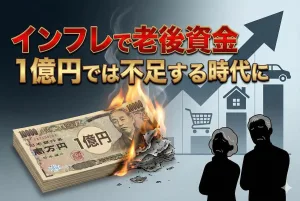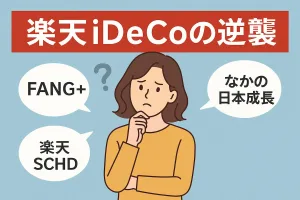本サイトでもおすすめさせていただいているかなりお得な個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入者数が順調に増加しています。
とうとう加入者が300万人を突破しました。
今回はiDeCoの加入者数等について見ていきましょう。
iDeCo(イデコ)の加入者数は順調に増加中
それでは実際のiDeCo加入者の推移を確認してみましょう。
2023年7月時点で300万人を突破
最新発表されている2023年7月までで実際にどれだけの方がiDeCoに新規加入しているのかを見てみましょう。
なお、第1号加入者とは国民年金の第1号被保険者のことで主に自営業者、フリーランス、無職の人が該当します。
第2号加入者数は国民年金の第2号被保険者で会社員の方
第3号加入者数は国民年金の第3号被保険者で会社員の妻(専業主婦)
第4号加入者は国民年金に任意で加入している任意加入被保険者である方となっています。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
| 2023年7月末 | |
| 第一号加入者 | 323,327人 |
| 第二号加入者 | 2,563,787人 |
| 第三号加入者 | 132,637人 |
| 第四号加入者 | 6,386人 |
| 合計 | 3,026,137人 |
出所:国民年金基金 iDeCo公式サイト 最新iDeCo加入者数を元に「お金に生きる」で作成
イデコの加入者はかなり順調に増えていますね。
とうとう300万人を突破しています。
1年間の新規加入者数も増加傾向
ちなみに2022年(2022年4月〜2023年3月)1年間の新規加入者は568,843人
2022年(2021年4月〜2022年3月)1年間の新規加入者は526,311人
2021年(2020年4月〜2021年3月)1年間の新規加入者は437,509人
2020年(2019年4月〜2020年3月)1年間の新規加入者は404,984人
2019年(2018年4月〜2019年3月)392,438人でした。
少しずつ1年間の加入者も増えていっています。
加入条件がかなり緩和されたことも大きいのでしょう。
個人型確定拠出年金(イデコ/iDeCo)とは
イデコをよくわからない方向けに解説もいれておきましょう。
確定拠出年金(iDeCo)は簡単に言えば自分の老後生活のために老後資金を自分で作るための制度です。
具体的にはこんな感じの流れです。
そしてそのお金を投資信託や定期預金、保険などの商品を選択して運用します。
そして60歳以降にその運用した資産を受け取ることができる仕組みになっています。
下記の図のように国民年金や厚生年金と合わせた年金制度の上乗せとして考えると良いでしょう。
掛け金として掛けられる金額ははその人の厚生年金等の状況により変わってきます。
例えば国民年金のみに加入ししている第一号被保険者でしたら国民年金基金と合わせて6万8千円まで加入することができます。
(付加年金入っている場合には6万7千円)
また、サラリーマンで年金制度がない会社にお勤めの方ならば月額2万3千円まで掛けることができます。
確定給付型年金などの年金制度がある会社にお勤めの場合には月額1万2千円まで掛けられます。
公務員の方も同様に月額1万2千円が上限となります。

出所:厚生労働省 iDeCo説明ページ
個人型確定拠出年金(イデコ/iDeCo)のメリット
確定拠出年金(iDeCo)のメリットとして大きなモノは3つあります。
所得税と住民税の節税効果
まず1つ目のメリットが所得税と住民税の節税が見込めることです。
確定拠出年金(イデコ/iDeCo)の掛け金は全額が所得控除となります。(小規模企業共済等掛金控除)
所得控除とは税金計算するときにその金額を控除して税金計算できるようになるってことです。
つまり、所得を減らしたことと同じ効果が得られます。
その結果、所得税及び住民税が減るのです。
毎月満額の6万8千円を確定拠出年金(iDeCo)に積み立てたとします。
すると年間で81万6千円の掛け金です。
それがそのまま全額所得控除となり24万4千8百円もの節税となります。
(81万6千円✕30%)所得税率20%、住民税10%で計算
自分の将来の年金を作るために積み立てているだけなんですが、税金までやすくなってかなりオトクであると言えます。
つまり、毎年3割(所得税率20%、住民税10%の方の場合)の運用ができる投資をしたようなものなのです。
正直このためだけに掛けてもよいくらい有利になっていますね。
確定拠出年金内の運用益の利益が非課税
もう一つのメリットは個人型確定拠出年金(イデコ/iDeCo)の中での運用について売却益や配当などを得た場合も全額非課税となります。
普通に投資信託や株などに投資をして売却益や配当が出た場合や定期預金の利息をもらった場合には税金が20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)が掛かります。
それが個人型確定拠出年金(イデコ/iDeCo)の中で運用すれば税金が掛からないのですからこちらもかなりオトクです。
受け取る際も税制優遇
確定拠出年金の給付を受取るときも一時金として受け取れば「退職所得控除」が受けられます。
また、年金として受け取る場合も「公的年金控除」がうけられます。
受け取る際は自身の他の退職金や年金の金額と合わせて検討しより有利な方法で受け取るといいでしょう。
自己破産時、離婚時に・・・
他にもメリットがあります。
それは自己破産時に没収されなかったり、離婚時に年金分割の対象とならない点です。
詳しくは下記記事をご覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//5572]
個人型確定拠出年金(イデコ/iDeCo)のデメリット
とても有利な制度となっている個人型確定拠出年金(iDeCo)ですが考えなければならないデメリットもあります。
後々後悔しないためにも始める前にデメリットも理解してはじめたいところです。
原則として60歳まで引き出せないこと
個人型確定拠出年金(iDeCo)最大のデメリットといえるかもしれないのが原則として60歳まで積み立てた資産を引き出すことができないことです。
また、途中で解約もできません。
逆に言えば「老後資金」を貯めるためにはそのくらい強い覚悟が必要ですから、強制的に貯める手段として個人型確定拠出年金(iDeCo)を使うと考えると良いかもしれませんね。
もし、自由に引出したいのならつみたてNISAやNISAがおすすめです。
損益通算できないこと
個人型確定拠出年金(iDeCo)のもう一つのデメリットは個人型確定拠出年金(iDeCo)内で損失が発生しても他の株等の利益との損益通算はできないことです。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は積極的に売買する仕組みではないです。
長期的な目を考えて取引するならこの点はそこまで問題ないかもしれませんけどね。
運用次第であること
もう一つが当たり前といえば当たり前ですが運用次第によっては損失がでたり、思ったように増えない可能性もあることもデメリットといえるかもしれません。
ただし、長期的な投資ですから期待値はかなり高いのは事実です。
まとめ
今回は「まだはじめてないの?iDeCoの加入者数が300万人を突破」と題してここ半年のiDeCo加入者数についてみてきました。
順調に増えていますが、iDeCoのお得度を考えるとまだまだ認知度が低いな・・・って感じがします。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの4社から選ぼう<PR>
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。
しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。
簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。
私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券、楽天証券の4択の中から決めます。
(※私が加入しているのはSBI証券です)
この4つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。
また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。
順番に見ていきましょう。
SBI証券
まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。
SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式、ひふみ年金、NYダウ、グローバル中小株、ジェイリバイブといった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。
選択の楽しさがありますよね。
また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。
[afTag id=36558]
マネックス証券
次点はマネックス証券 iDeCoです。
こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。
iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。
[afTag id=36661]
松井証券
松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。
その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。
こちらも有力候補の一つですね。
[afTag id=36658]
楽天証券
楽天証券は楽天・全世界株式インデックス・ファンドや楽天・全米株式インデックス・ファンドといった自社の人気商品の取扱が大きなポイントとなっています。
この2つのファンドは人気ですね。
[afTag id=36651]
総合して考えるとこの4つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。
他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
ブログランキング参加中です。
![]()
にほんブログ村