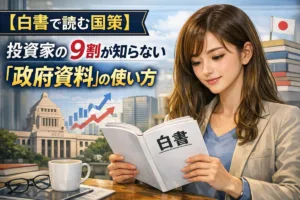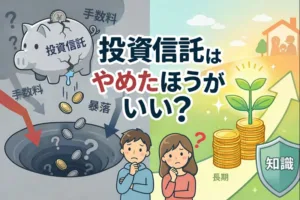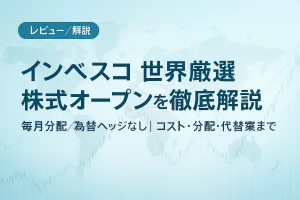証券会社や銀行で株式投資や投資信託を始めようとした時、始めのハードルとなるのがどの種類の口座を選択するのかということです。
「NISA口座」といった非課税制度もありますし、自分で1年間の譲渡損益・譲渡所得等の金額の計算書を作って確定申告が必要な「一般口座」、計算書の作成不要な「特定口座」があります。
さらに特定口座には所得税や住民税が控除される「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
非常にややこしいですね。
先に結論を言っておくと基本的には後述する特殊な事情がある場合を除いて
余裕があれば特定口座の源泉徴収あり
そこで今回は特定口座の源泉徴収あり、なしの話しを中心にそれぞれの口座のメリット・デメリットを考えてみましょう。
株式投資を始めるための口座の種類
それではまず、株式投資を始めるための口座の種類から見ておきましょう。
ちなみにこれは株式投資だけに限らず、投資信託でも最近手数料が下がったこともあり人気が上がっている米国株式など海外株式でも基本的に同じです。
NISA口座
まずは「NISA口座」です。NISAとは少額投資非課税制度のことです。
簡単に言えば一定の金額、一定の期間、利益が非課税で投資ができる制度です。
つまり、利益がでても税金が掛かりませんってことですね。
投資信託や株を売買して利益がでれば(配当や分配金も同じ)税金が20.315%(所得税15.315%+住民税5%)発生します。
それが無料ですからかなり大きいですよね。
NISA口座は少しずつルールが改定されてきていますが、今の時点では毎年360万円、生涯1,800万円が非課税枠となっています。
ただし、利益が非課税である代わり、マイナスがでても繰越ができなかったり、他の証券会社でマイナスが出てても損益通算はできないというデメリットもあります。
なお、NISA口座は原則的に確定申告は不要です。
つみたてNISAと違い、株式、海外株、海外ETFなども買うことができます。
また、買う投資信託もつみたてNISAのように制限はありません。
ですから使いみちはNISAの方がつみたてNISAより自由度がかなり高いですね。
個人的なおすすめは海外ETFですね。これが買えるのがNISAの強みであると思います。

一般口座
次は一般口座です。
上場株式等(投資信託や公社債なども含む)の譲渡による所得は、申告分離課税の対象となっています。
そのため、原則として、自身によりその年1年間の譲渡損益・譲渡所得等の金額の計算や確定申告などの手続きが必要です。
それを自分でやることになる口座です。
ちなみに非上場の未公開株などは一般口座でしか利用できませんね。
昔はみなし取得費の特例という制度があったため一般口座を利用するメリットもありました。
しかし、今はその特例もなくなったため一般口座にほとんどメリットがなく面倒なだけの口座ですからおすすめしません。
ただし、一部海外の証券会社だと特定口座やNISA口座は作れませんので自ずと一般口座となりますのでご注意ください。
なお、一般口座は原則的に確定申告が必要です。計算書類等も自分で用意が必要ですからちょっと面倒ですね。。。
特定口座
最後は特定口座です。
特定口座は譲渡損益・譲渡所得等の金額の計算や確定申告の手続きが不要になったり軽減されたりするための制度です。
特定口座には2種類あり、所得税や住民税が譲渡益が出た都度控除される「源泉徴収あり」と控除されない「源泉徴収なし」の2種類があります。
ちょっと扱いが違いますので区分して考える必要があります。
特定口座源泉徴収あり
特定口座の源泉徴収あり(正式名称:源泉徴収選択口座)は証券会社などが売却損益、配当等の計算を自動で行ってくれます。
入金されるのは所得税・住民税が引かれた金額となります。
つまり、税金は自動で納める形となります。
ですから、源泉徴収あり口座は原則的に確定申告が不要です。
特定口座源泉徴収なし
特定口座の源泉徴収なし(正式名称:簡易申告口座)は証券会社などが売却損益、配当等の計算を自動で行ってくれます。
しかし、所得税・住民税は自動的には引かれません。
証券会社から発行される特定口座年間取引報告書などをつかってご自身で確定申告が必要です。
なお、譲渡益が出ている場合には確定申告が必要ですが、マイナスの場合には確定申告はしなくても大丈夫です。(したほうが得なケースもあり)
口座種類まとめ
現状の制度ですと一般口座を作るメリットはほぼありませんので選択しないことをおすすめします。
基本的にはNISA、つみたてNISA口座の非課税制度が利益に対して税金が掛かりませんからかなり有利です。
ですからまずそちらを活用しましょう。
ただし、双方とも金額に上限がありますからそれで物足りないならば特定口座を開くのがよいでしょう。
特定口座の源泉ありとなしのどちらが良いのかは条件次第のところがありますので次章で解説していきます。
源泉徴収ありと源泉徴収なしのメリット・デメリット
特定口座源泉徴収ありのメリット
まず、特定口座の源泉徴収ありのメリットから見ていきましょう。
譲渡所得が他の制度に影響を与えない
特に大きいメリットが上記の2つです。
確定申告が不要
特定口座の源泉徴収ありの場合にはすでに所得税・住民税が控除されていますので確定申告が原則不要です。
確定申告は慣れていない方だと結構面倒ですからその手間暇から開放されるのは大きなメリットでしょう。
ただし、その年の売買で損失が出ている場合やいくつかの証券口座を持っていて一部の口座でマイナスが出ている場合などは確定申告をしたほうが有利となるケースが多いですから確定申告をすることを検討しましょう。
その場合でも「特定口座年間取引報告書」が証券会社等からもらえますからそこまで大変ではありません。
譲渡所得が他の制度に影響を与えない
もう一つが隠れたメリットの譲渡所得が他の制度に影響を与えない点です。
これ地味に大きいんですよ。
特定口座、源泉徴収ありの場合には原則として確定申告が不要です。
確定申告をしなければ譲渡所得が他の制度に影響を与えないのです。
例えば専業主婦の方などで配偶者控除の対象となるかどうかの所得の判定基準は譲渡所得でも判定に合算されます。
つまり、株等で儲かっていると扶養になれなかったりするんですよ。
しかし、特定口座、源泉徴収ありの場合で確定申告をしなければこの部分が判定に利用されることはありませんから有利に働きます。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

また、住民税非課税の扱いを受けられるかどうかも変わってきます。
住民税非課税制度の対象となるかどうかで様々な違いが出ますのでこちらも大きいですね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

さらに自営業者などの国民健康保険の計算には譲渡所得も含まれてきてしまいます。
国民健康保険はかなり高いですからこの辺りも大きな違いとなるでしょう。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

特定口座源泉徴収ありのデメリット
次に特定口座の源泉徴収ありのデメリットも見ていきましょう
資金効率が悪くなる
特に大きいデメリットが上記の2つです。
年間20万円以下の問題
本来、年末調整で所得税の納付が確定している給料所得者や公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者の方の場合には給料等以外の所得(株等の譲渡益を含む)が年間20万円以下である場合には申告・納税は原則として不要となっています。(住民税は要申告)
しかし、特定口座の源泉徴収ありの場合には自動的に所得税と住民税が引かれてしまいます。
この辺りはデメリットですね。
資金効率が悪くなる
源泉徴収ありの場合には売買で利益が出る都度、所得税や住民税が徴収されます。
自分で源泉徴収なしの場合にはその都度は税金が徴収されず納税は確定申告をする3月にまとめてとなります。
つまり、その都度引かれる場合には資金効率が悪くなるのです。
例えばちょっと極端な例ですが、月に資金の10%利益をあげられる人で考えてみましょう。
その方が100万円の投資資金で年初に投資を始めたとします。
なお、計算がわかりやすいように税金は20%、取引は1月に1回、利益はそのまま投資。投資額計算時に千円未満四捨五入とします。
源泉徴収ありの場合
源泉徴収ありの場合は下記の通り190万円の利益となりました。
| 利益 | 税金 | 投資額 | |
| 1月 | 10万円 | 2万円 | 108万円 |
| 2月 | 10.8万円 | 2.16万円 | 117万円 |
| 3月 | 11.7万円 | 2.34万円 | 126万円 |
| 4月 | 12.6万円 | 2.52万円 | 136万円 |
| 5月 | 13.6万円 | 2.72万円 | 147万円 |
| 6月 | 14.7万円 | 2.94万円 | 159万円 |
| 7月 | 15.9万円 | 3.18万円 | 172万円 |
| 8月 | 17.2万円 | 3.44万円 | 186万円 |
| 9月 | 18.6万円 | 3.72万円 | 200万円 |
| 10月 | 20万円 | 4万円 | 216万円 |
| 11月 | 21.6万円 | 4.32万円 | 233万円 |
| 12月 | 23.3万円 | 4.66万円 | 252万円 |
| 合計 | 190万円 | - | - |
源泉徴収なしの場合
源泉徴収ありの場合は下記の通り214.3万円の利益となりました。
| 利益 | 税金 | 投資額 | |
| 1月 | 10万円 | - | 110万円 |
| 2月 | 11万円 | - | 121万円 |
| 3月 | 12.1万円 | - | 133万円 |
| 4月 | 13.3万円 | - | 146万円 |
| 5月 | 14.6万円 | - | 161万円 |
| 6月 | 16.1万円 | - | 177万円 |
| 7月 | 17.7万円 | - | 195万円 |
| 8月 | 19.5万円 | - | 215万円 |
| 9月 | 21.5万円 | - | 237万円 |
| 10月 | 23.7万円 | - | 261万円 |
| 11月 | 26.1万円 | - | 287万円 |
| 12月 | 28.7万円 | - | 316万円 |
| 合計 | 214.3万円 | 42.86万円 | - |
前述の源泉徴収ありと比較すると24万円ほど利益が増えています。
これは源泉徴収ありで取引の都度引かれる税金分を投資に利用した複利効果による差です。
これだけ利益を上げられる方はそうはいないでしょうから極端な例ですが、結構大きな差となることがわかっていただけたと思います。
特定口座源泉徴収なしのメリット
特定口座の源泉徴収なしのメリットは前述の特定口座、源泉徴収ありのデメリットの裏返しですね。
資金効率がよい
特定口座源泉徴収なしのデメリット
特定口座の源泉徴収なしのデメリットは前述の特定口座、源泉徴収ありのメリットのの裏返しです。
譲渡所得が他の制度に影響を与えてしまう
特に2つ目の他の制度に影響を与えてしまうデメリットはかなり大きいですから慎重に検討をする必要があります。
源泉徴収あり、なしのどちらを選択すればよいのか
源泉徴収あり、源泉徴収なしのどちらを選べばよいのでしょうか?
これはその人の状況によってかなり異なってきます。
多くの方は特定口座の源泉徴収ありの方が確定申告不要のメリットを享受できますのでおすすめです。
ただし、たくさんの取引をするデイトレーダーなどは資金効率を考え源泉徴収なしを選択するのがよいでしょう。
その場合でも国民健康保険や扶養など他の制度に影響を与えてしまうデメリットについても加味した上で検討してみてくださいね。
まとめ
今回は「特定口座は源泉ありと源泉なしのどちらが良いのか?それぞれメリット・デメリットあり」と題して特定口座の源泉徴収あり、なしの話しを中心にそれぞれの口座のメリット・デメリットについてみてきました。
結論としては以下のとおりです。
金額に物足りなさを感じるなら特定口座を使う。
特定口座は基本的には確定申告が不要の源泉徴収ありがおすすめ。
たくさん取引をする投資家は資金効率を考えて源泉徴収なしも検討
なお、これから証券口座を開くなら下記記事のようなこともありますからネット証券一択ですよ。

証券口座開くならネット証券がおすすめ
今、株式投資を始めようと考えているならば以下の2社がおすすめですね。特定口座はもちろんつみたてNISAやNISAでもSBI証券、楽天証券がおすすめですね。
SBI証券
SBI証券は商品ラインナップや注文の仕方などは一番優れています。
手数料なども常に業界最安値水準ですし、なによりネット証券の老舗の安定感ですね。
利便性で考えるならSBI証券でしょう。
また、取り扱いの分野、商品の種類もかなり多いですから選択の楽しさもありますね。
資料請求等はこちらから
楽天証券
楽天証券のなによりのメリットは楽天カードで投資信託などが買える点でしょう。
楽天カードはポイントも貯まりますし、そのポイントで株や投資信託が買えるという仕組みは本当にありがたいですね。
楽天カードを使っている方は楽天証券がおすすめです。
資料請求等はこちらから
最後まで読んでいただきありがとうございました。