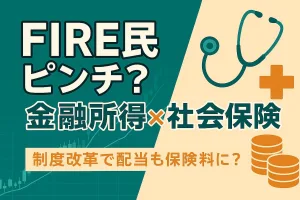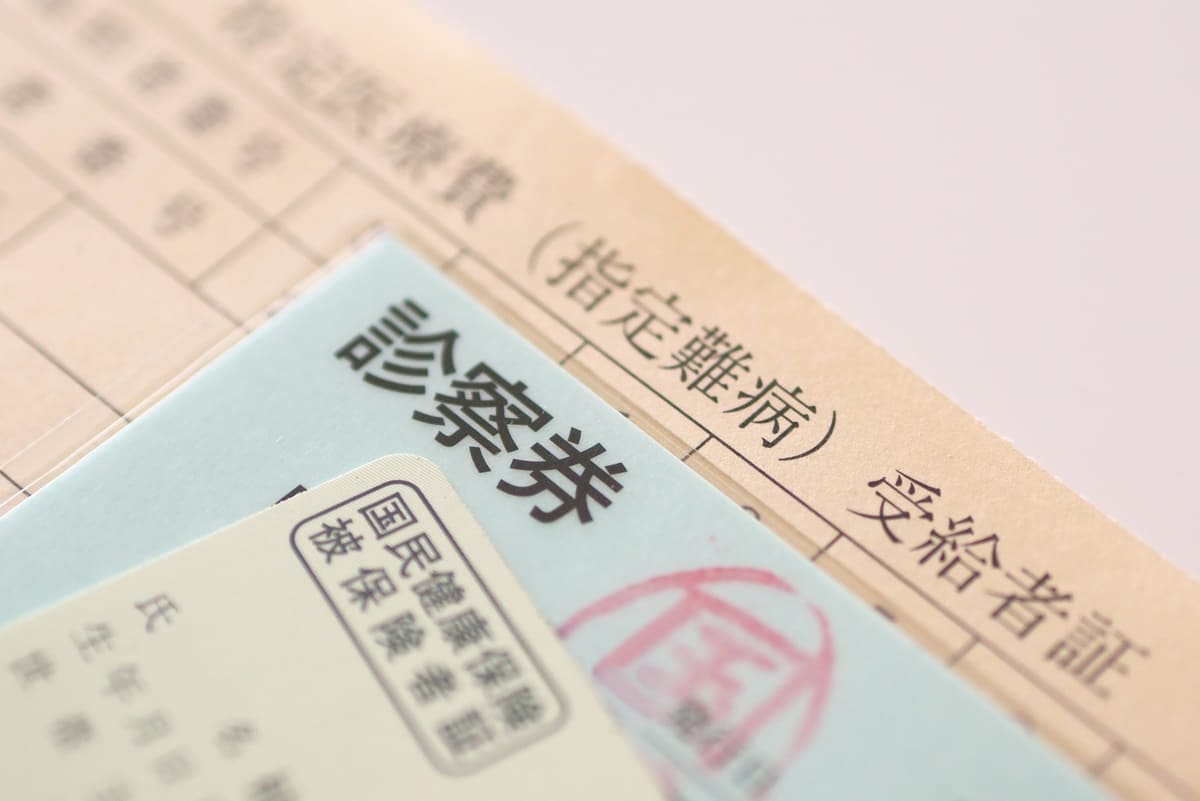またもや国民健康保険が引き上げられそうです。
2023年も2万円上限が上がったばかりですから毎年のように上がっていますね・
国民健康保険引き上げの内容
それではまずは引き上げの内容から確認していきましょう。
高齢化の進展で医療費の増加が続く中、厚生労働省は、自営業者などが加入する国民健康保険について、年間の保険料の上限を来年度、2万円引き上げて89万円とする方針を固めました。引き上げられれば3年連続となります。
出典:NHK国民健康保険 年間保険料の上限額2万円引き上げて89万円の方針
つまり、年間上限額が今まで87万円だったのが年間89万円と2万円引き上げになるってことですね。
介護分も含めれば106万円となります。

出典:厚生労働省 社会保障審議会 第 169 回社会保障審議会医療保険部会 議事次第 より
引き上げの対象者は国民健康保険加入者
ツイッターなどでも自分が影響を受けると思っている方が多かったようですが、実は対象となる方はあまり多くありません。
まず今回の引き上げの対象となるのは国民健康保険の加入者です。
国民健康保険とは自営業、フリーランスの方や社会保険に加入していない会社に勤める労働者、無職の方などが加入する健康保険です。
サラリーマンの方やその扶養の方が加入している健康保険は、会社により組合健保だったり協会けんぽ(全国健康保険協会)だったりしますがそれとはすこし扱いが違います。
国民健康保険は会社負担もなく、加入者に無職の方などが多数含まれている性質もありかなり高いんですよ。
それが今回さらに引き上げされるという・・・
健康保険の種類やその違いにについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
引き上げ対象はそれほど多くはない

出典:厚生労働省 社会保障審議会 第 169 回社会保障審議会医療保険部会 議事次第 より
なお、引き上げの対象となる限度額に該当している世帯の割合は国民健康保険加入者の1.42%とそれほど多くはありません。
この引き上げ圧倒的に条件を超過している方にはそれほどですが、ギリギリ超過してしまう人にとってはかなりの痛手です。
例えば今回の引き上げギリギリに該当する年収1,150万円の人なら106万円の健康保険です。
つまり、年収の9%近くが健康保険として持っていかれてしまうという・・・
さらに税金や年金などは別途ですからね・・・
年々その負担割合が増えているという・・・
なぜ引き上げられるのか?
それではなぜ今回国民健康保険の上限が引き上げられるのでしょう。
これには大きく2つの理由がります。
被用者保険とのバランス
まず、1つ目が被用者保険とのバランスです。
被用者保険※では最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が0.5%~1.5%の間となるように 法定されており、賦課限度額超過世帯割合が1.5%に近づくように段階的に引き上げるとしているようです。
つまり、上限にいってる世帯が多くなると引き上げってことですね。引き上げ前で1.42%と少し1.5%は超過していませんが・・※被用者保険とはサラリーマンの方などが加入する健康保険のこと。
中間所得層の負担軽減
もう一つが中間所得層の負担軽減です。
上限を引き上げることで中間所得層の負担を減らすことに繋がるんですよ。

出典:厚生労働省 社会保障審議会 第 169 回社会保障審議会医療保険部会 議事次第 より
そのままの制度だと中間層(年収400万円)の健康保険料の負担割合は前年比で3.2%増加となっていたようです。
それを限度額をあげることで2.7%の増加に抑えることができるとのこと。
20年で倍近く。。。国民健康保険料の上限の歴史
それではここからは国民健康保険料の上限改定の歴史を振り返ってみましょう

出典:厚生労働省 社会保障審議会 第 1569回社会保障審議会医療保険部会 議事次第 より
実は毎年のように限度額は増えており、平成12年度では60万円だった上限は令和6年に106万円と倍近くまで増えているのです。
少子高齢化や医療費の高騰もあり健康保険制度はかなり限界に近いところに来ているのは事実でしょうね。
ちなみに今回見たのは自営業者などが加入する国民健康保険料の話ですが、サラリーマンの方が加入する健康保険もかなり厳しい状況に変わりはありません。
2025年問題+新型コロナでかなり厳しい健康保険組合
サラリーマンの方の多くが加入する健康保険組合は大企業もしくはそのグループ企業、業界団体などが共同して保険者となって設立された組合が母体となっています。
しかし、かなり厳しい状況にあるんですよ。
もともと2025年問題といって戦後のいわゆるベビーブームで生まれた世代(約800万人)が75歳の後期高齢者に達するという少子高齢化で、人材派遣健保組合(人材派遣の健康保険組合)や日生協健保組合(生協の健康保険組合)が解散するなど厳しい環境にあった健康保険組合。
そこに新型コロナの蔓延による影響でさらに厳しくなったところが多いのです。

出典:健康保険組合連合会 「新型コロナウイルス感染拡大による 健保組合の財政影響に関する調査報告」より
当然そうなれば保険料を上げざる得ないでしょうし、中には負担増に耐えかねて解散する健康保険組合が出てくる可能性もあるでしょう。
まとめ
今回は「国民健康保険の上限が2万円引き上げ。年々あがる国民健康保険の引き上げの歴史を振り返ってみた」と題して国民健康保険料の上限引き上げの話をみてきました。
税金、年金、健康保険は少子高齢化で全面的に見直す時期に来ていますね。
しかし、年金にしても健康保険にしても抜本改革をしようとすると票を多くもっている高齢者が反対をするからなかなか進まないという現状・・・・
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
ブログランキング参加中です。
![]()
にほんブログ村
最後まで読んでいただきありがとうございました。