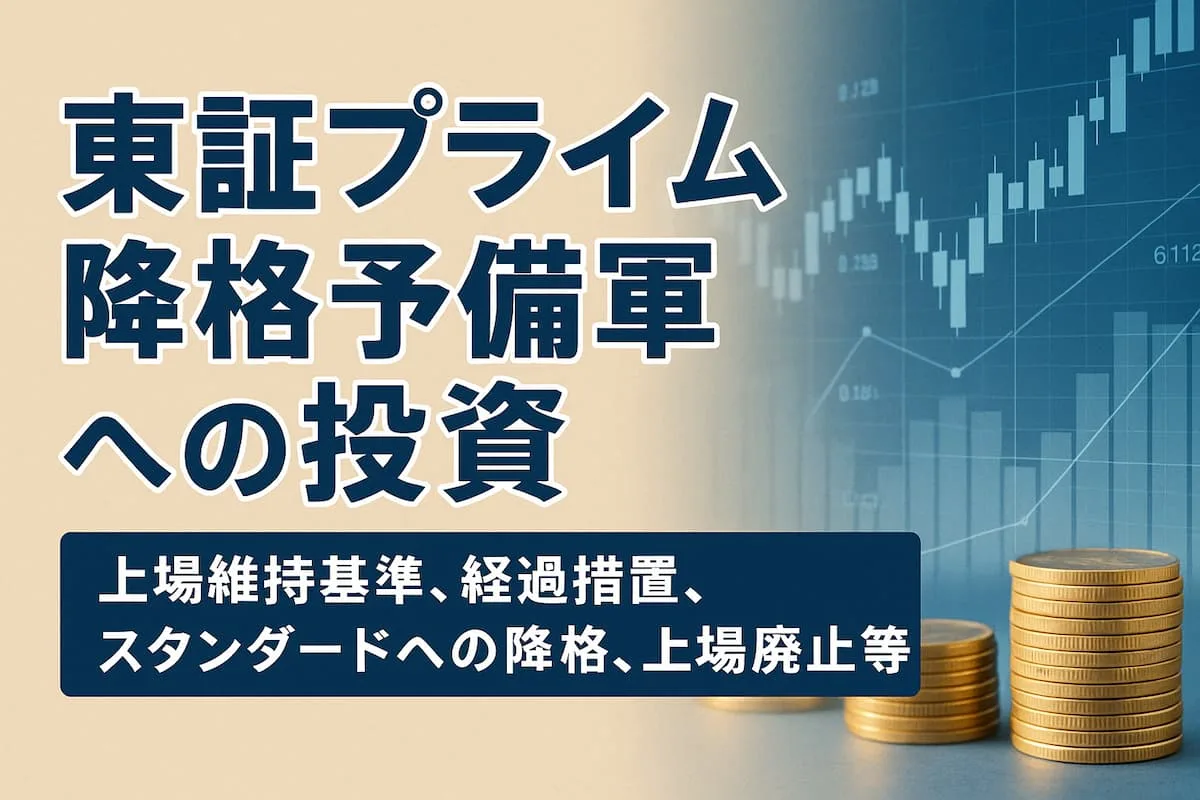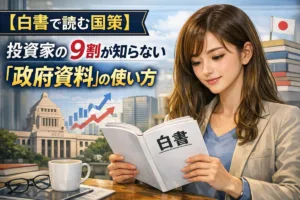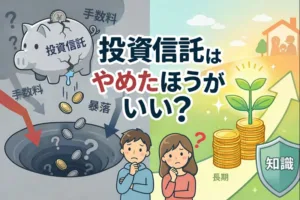2025 年3月に東京証券取引所が設けていた上場維持基準の経過措置が順次終了しました。
これにより、緩和されたハードルのもとで “猶予” を受けていた銘柄の行き先がいよいよ決まります。
東証によれば、直近で経過措置の対象となっている企業は 267 社(プライム 69 社を含む)です。
今回は「東証プライム降格予備軍」への投資について考えてみます。
各市場区分におけるの上場維持基準をおさらい
まずは今回の話の前提となる各市場における上場維持基準から見ていきましょう。
| プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 | ||||
| 本来の基準 | 経過措置 | 本来の基準 | 経過措置 | 本来の基準 | 経過措置 | |
| 株主数 | 800人以上 | 経過措置なし | 400人以上 | 150人以上 | 150人以上 | 経過措置なし |
| 流通株式数 | 2万単位以上 | 1万単位以上 | 2,000単位以上 | 500単位以上 | 1,000単位以上 | 500単位以上 |
| 流通株式時価総額 | 100億円以上 | 10億円以上 | 10億円以上 | 2.5億円以上 | 5億円以上 | 2.5億円以上 |
| 流通株式比率 | 35%以上 | 5%以上 | 25%以上 | 5%以上 | 25%以上 | 5%以上 |
| 売買代金/売買高 | 1日平均売買代金 0.2億円以上 | 月平均売買高 40単位以上 | 月平均売買高 10単位以上 | 経過措置なし | 月平均売買高 10単位以上 | 経過措置なし |
| 時価総額 | - | - | - | - | 40億円以上(上場10年経過後から適用) | 5億円以上(上場10年経過後から適用) |
経過措置は 2025 年3月 1 日以降に到来する基準日から完全終了。
という流れです。
「東証プライム降格予備軍」に多いパターン
今回問題となっている降格、上場廃止予備軍には共通する点やパターンがあります。
浮動株不足(流通株式比率 35%未満)
親子上場や創業家色の強いオーナー企業が多く、それらの持ち株が多く市場に流れにくい。
浮動株がすくなく売らない株主が多いと株が上がりやすいんですけどね。
時価総額 100 億円未満
地方の老舗やニッチ BtoB 企業に散見されます。
業績横ばいでも PER が妙に高いケースも。
出来高薄(1日 0.2 億円未満)
出来高が薄く小口でも株価が振れやすく、指数連動型ファンドが離脱すると下値が真空に
こうした条件に複数ヒットする銘柄は「降格予備軍」の有力候補となります。
JPX が公表する 改善期間該当銘柄リスト(毎週更新) で“未達ポイント”を確認することもできます。
投資家にとってのチャンスとリスク
今回の上場維持基準の経過措置の終了は投資家にとって大きなチャンスともリスクともなる可能性があります。
条件をクリアするための手を打ってくる可能性
まず、上場を維持したい企業が多いことを念頭に置きましょう。
そうなればなにをするのか。
浮動株が不足しているなら経営刷新+浮動株対策(売出し・自社株処分) などが考えられるでしょう。
過去にはその手のIR を出しただけで株価が 30〜50%跳ねた例も。
また、出来高や時価総額が不足しているなら株価が上がったり注目を浴びるIRを出してくる可能性があります。
株主優待の新設や増配などですね。
失敗すれば株価暴落
逆に大きなリスクもあります。
改善期間でも基準を満たせないと、最速で 2026 年3月に整理銘柄指定 →上場廃止となります。
そうなれば上場廃止前に売る人が増えることから株価は大きく下がる可能性が高いです。
下記記事にも書いていますが、上場廃止後でも株は持ち続けることはできますが、基本的に損をするケースのほうが多いためおすすめできません。
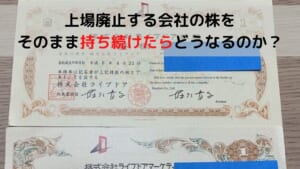
上場廃止を回避してスタンダード降格だけで終われば御の字ですが、プライムから外れると指数連動ファンドの売りが想像以上に重いため株価が下がる可能性は高いでしょう。
東証プライム降格予備軍をチェックするべきポイント
それではどのような点に注意しておけばよいのでしょう。
私が考えるチェックポイントを示しておきましょう。
チェックリスト
| チェック項目 | 目安 | 確認先 |
| 流通株式比率 | 35%未満なら警戒 | JPX「株券等の分布状況表」 |
| 流通株式時価総額 | 100 億円未満 | 各社 IR/QUICK端末 |
| 直近 3 か月平均出来高 | 20 万株未満 | Yahoo! ファイナンスなど |
| IR に改善計画の数値目標 | あり/なし | TDnet 適時開示 |
| 株主構成 | オーナーの割合、ファンドの存在 | 有価証券報告書 |
資本政策の透明度
IR等から今回の上場維持基準がどの程度意識されているのか?をみます。
「達成計画」のロジックが数字で示されているかという点が重要でしょう。
外部株主の存在
次に株主にファンドや外部の事業会社が入っているかです。
これらはTOB への布石になりやすいです。
NISAで買う場合
NISA で買う場合は 「改善計画の進捗を半年ごとに確認」 というセルフルールを設けると失敗が減ります
ダメそうなら翌年枠で乗り換えて節税メリットを確保しましょう。
まとめ
今回は「「東証プライム降格予備軍」への投資──制度変更が迫るいま、チャンスとリスクをどう見極める?」と題して東証プライムの降格予備軍の話をみてきました。
2025~26 年は「東証プライム降格予備軍」にとって正念場となります。
約 70 社 が基準未達のまま改善期間入りし、指数売りやスタンダード降格で株価の波乱要因に。
しかし、改善策の実行や MBO/TOB による“出口”が見えれば オーバーリアクションが戻るフェーズ を逆張りで狙える。
NISA を活用するなら「情報開示の量と質」「資本政策の一貫性」を2大評価軸に。
リスク管理を徹底すれば、“市場改革の副産物”を取り込むチャンスは十分あります。
これは値上がり保証ではなく、上場廃止リスクと背中合わせの戦略だという点をお忘れなく。少額で試し、半年ごとに IR と出来高を必ず点検。
それが「降格予備軍」投資の鉄則ですね。