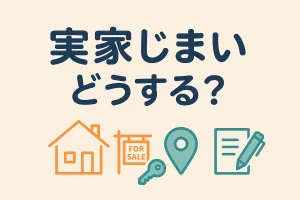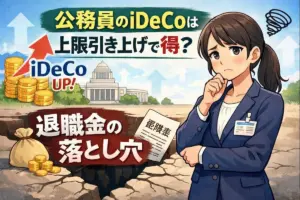楽天証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)が商品ラインナップの大幅見直しを発表しました。
iDeCoは35本制限という独特のルールがあるため、商品入れ替えがやりにくい中でかなり思いっきりましたね。
今回は楽天証券のラインナップ見直しについてみていきましょう。
何が起きている?楽天証券iDeCoの「入替え」全体像
楽天証券は2025年9月17日付でiDeCoの運用商品入替えを案内。
確定拠出年金における提示本数は「上限35本」と法令・監督方針で定められており(いわゆる35本ルール)、この枠内で商品を見直す流れです。
追加予定ファンド
現時点での追加予定ファンドは以下の通り。
アンケートでお客様のご要望を踏まえてとのことで人気のある尖った商品もラインナップされています。
- iFreeNEXT FANG+インデックス:米国大型グロースの濃縮バスケット
- なかの日本成長ファンド:厳選のクオリティ成長株アクティブ
- 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(資産成長型)(楽天・SCHD(資産成長型)):高配当×配当成長の米国クオリティ配当株
- 楽天・高配当株式・日本(資産成長型):国内高配当株
- 楽天・オールカントリー(除く日本)インデックス:オルカンの日本を除く
- 楽天・欧州株式/楽天・エマージング株式 インデックス
- ニッセイ・インデックスバランス(4資産均等・ノーロード)
- ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジなし)
特に注目なのは「iFreeNEXT FANG+インデックス」、「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(資産成長型)(楽天・SCHD(資産成長型))」でしょうね。
他の金融機関のiDeCoでは見かけない尖った人気商品となります。
なお、正式な取扱開始は2026年4月上旬予定とのこと。
除外されるファンドはこちらの記事を御覧ください。

除外ファンドは5月に発表され、除外される商品「セゾン資産形成の達人ファンド」を扱っていたセゾン投信が反論するなど物議を醸していたんですよ。
なぜ、入替えなのか?――「35本制限」と金融庁の考え方
単なる追加でなくて入れ替えなのかに疑問を持つ方も多いでしょう。
これはiDeCoの運営管理機関(ここでは楽天証券)には3〜35本の範囲で商品提供を行うルールがあるためです。

出所:厚生労働省 確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要(平成30年5月1日施行)
多すぎる選択肢は加入者の選択負担や不適切選好を招くとして、35本までしかラインナップを用意できないようになっているんですよ。
楽天証券のiDeCoはこの35本制限ギリギリでしたので、新しい運用商品をいれるために稼働が悪い商品を除外せざる得なかったということでしょう。
個人的にはこの35本制限があるために、新しい魅力的な投資信託がなかなかiDeCoで採用されないケースが多いのが逆に問題だと思うんですよね・・・
廃止を希望します。
いつ何をすればいい?――スケジュール
除外と新規採用の主なスケジュールは以下の様になっています。
除外が発表されたときのスケジュールより、セゾン投信の反論などがあった
| 時期(予定) | ご案内方法 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025年10月下旬 | メール | 除外に関する回答依頼メール(対象:2025年9月30日時点で保有/積立指定のある加入者) |
| 2025年12月末 | WEB | 回答期限(無回答は同意みなし) |
| 2026年2月上旬 | メール | 除外決定の個別通知 |
| 2026年4月上旬 | WEB | 除外商品の新規買付停止/追加商品の新規売買開始 |
掛金配分(スイッチング含む)の締切に注意。
除外されるファンドが指定してあり、それを放置すると「未指定扱い」→指定運用方法の商品を購入へと流れる形となります。
なお、楽天証券の指定運用方法は「楽天・インデックス・バランス(DC年金)」です。
代表的な追加候補の「使いどころ」
それでは今回の入れ替えの目玉となりそうな商品の使いどころを考えてみましょう。
iFreeNEXT FANG+インデックス
まずは今回の一番注目FANG+です。
iDeCoで採用されるのは初となります。
FANG+とはFacebook、Amazon、Netflix、Googleなど米国企業10銘柄で構成された株価指数。
それに連動するファンドってことですね。
- 狙い:米大型グロース(FANMG+α)の成長を濃縮で取りに行く。
- 向き不向き:長期の成長期待は高いがドローダウンが大きい局面も。掛金100%集中は非推奨、NISAや他資産との役割分担を。

楽天・SCHD(資産成長型)
次は楽天SCHD(楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド)です。
こちらもiDeCoで採用されるのは初ですね。
- 狙い:「配当の質」に絞った米国クオリティ配当株エクスポージャー。配当を受け取らず再投資で複利を狙う設計。
- 向き不向き:高配当だがセクターバランスがS&P500と異なる。広範インデックスのサテライトとしての使い方が現実的。シリーズ拡充は公式で確認可

なかの日本成長ファンド
次はなかの日本成長ファンドです。セゾン資産形成の達人ファンドが除外されてこちらが採用されるのが意外でした。(もともとセゾン資産形成の達人ファンドの運用会社の会長だった中野晴啓さんが独立してつくったのがなかの日本成長ファンド)
- 狙い:日本株のクオリティ・グロースをボトムアップで厳選。長期目線での企業成長に賭ける。
- 向き不向き:短期相場色が強い時は逆風も。コアは低コスト指数、サテライトにアクティブという王道で位置付けたい。

楽天・オルカン(除く日本)ほか
次は楽天オルカン(除く日本)です。
- 狙い:地域別の粒度で全世界・先進国・新興国を組み合わせたい方向け。
- 使い方:S&P500やオルカンと重複比率に注意しつつ、為替・地域の分散を微調整。
日本株はiDeCo外でかなり投資しているという方で、リスクを分散したい方には日本を除外したこちらの方が通常のオルカンよりむいているでしょう。
金/バランス(4資産均等)
金やバランス(4資産)も今までの楽天証券にないラインナップとなります。
- 狙い:景気循環の分散やインフレヘッジ。
- 使い方:株式偏重ポートのボラティリティ緩和役。掛金配分の10〜30%枠で検討しやすい。
最近は金の上がり方がすごいですしね。
よくある誤解と注意点(Q&A)
それではよくある注意点をみておきましょう
FANG+をiDeCoで積むのはアリ?
ポイント:高ボラ前提。
過去の成績は良いですが、かなり値動きは激しくなります。
ですからコア×サテライトでの役割分担が基本となるでしょう。
年齢・リスク許容度・他口座との全体最適で判断するのがよいでしょう。
回答し忘れるとどうなる?
無回答は同意みなし。
また、除外ファンドのまま放置すると未指定扱い→楽天・インデックス・バランス(DC年金)の買付
必ず配分の再設定を。
楽天・SCHDが分配するとどうなる?
iDeCoは運用時の分配金などは「非課税」での受取です。
老後にiDeCoの残高を受け取るときに課税されるのが基本ですが、退職金控除など優遇もあります。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

FANG+に投資したいけど楽天証券に乗り換えた方がよい?
現状、iDeCoでFANG+を採用しているのは楽天証券のみとなります。(2026年4月から)
現状で考えれば乗り換えも選択肢になるでしょう。
しかし、今回のFANG+が楽天iDeCoで人気となれば、35本制限まで余裕のある金融機関は新たに採用してくる可能性もあります。
また、35本制限まで余裕のない証券会社も楽天証券のように除外→新規採用をしてくる可能性もあります。
ですから様子を見るのも手です。
また、iDeCo外で投資をするのも選択肢です。
iDeCoの乗り換えは時間がかかりますし、結構大変なんですよ。
私もSBI証券でオリジナルプランからセレクトプランに乗り換えをしたことがあります。(他の証券会社へ乗り換えと同じ手続き)
この時は3ヶ月近くかかりましたね。詳しくはこちらの記事を御覧ください。

まとめ
今回は「楽天証券iDeCoの逆襲が始まる:FANG+/楽天SCHD/なかの日本成長が追加へ」と題して楽天証券iDeCoの新商品追加の話を見てきました。
利用者のアンケートで新商品を導入するというのは良いアイデアですね。
今までお金に生きるのiDeCoのおすすめはSBI証券、松井証券、マネックス証券でしたが、今回の商品ラインナップ拡充で4月以降は楽天証券も有力候補となりそうです。
iDeCoでトップのSBI証券などの他社が追随するのか注目したいところ。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの3社から選ぼう
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。
しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。
簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。
私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券の3択の中から決めます。
(※私が加入しているのはSBI証券です)
この3つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。
また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。
順番に見ていきましょう。
SBI証券
まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。
SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式といった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。
選択の楽しさがありますよね。
また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。
マネックス証券
次点はマネックス証券 iDeCoです。
こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。
iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。
松井証券
松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。
その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。
こちらも有力候補の一つですね。
さらに2024年8月1日(木)より投資信託の保有でポイントが貯まるようになり、現在の条件なら本命といっても良いでしょう。
総合して考えるとこの3つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。
他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・
最後まで読んでいただきありがとうございました。