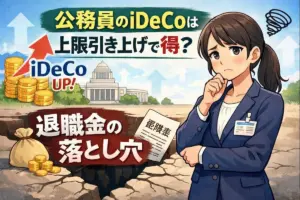このサイトでも何度か紹介しています個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)。
とてもお得な制度ですが、手続きが面倒なこともあり、なかなか重い腰を上げきれない方も多いようです。
しかし、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)についてはできるだけ早く始めた方がよいという部分があるんですよ。
今回はidecoはできるだけ早くから始めた方がよいという話を見ていきます。
iDeCoはできるだけ早くから始めた方がよい理由1:退職所得控除
なぜiDeCOはできるだけはやく始めた方がよいのでしょう?
まずひとつ目は退職所得控除の存在です。
退職所得控除は少額でも少しでも早く掛けたほうが大きくなるんですよ。
詳しく見ていきましょう。
イデコは税金を先に繰り延べる仕組みだが・・・
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は掛け金を拠出したときに節税効果があります。
控除が増えるため所得税と住民税を減らすことができるのです。
また、運用で利益がでても非課税。
しかし、受け取る時に税金が掛かるという仕組みになっているんですね。
つまり、仕組み的には税金の支払いを先に繰り延べる形となっています。
それじゃあ結局得じゃないじゃんと思われるかもしれません。
たしかにそうなのですが、イデコには受け取るときにも優遇措置があるのです。
それが「退職所得控除」と「公的年金控除」です。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)はこの2つの控除が受け取るときに対象となりますのでうまく受け取れば税金が掛からなかったり、かなり少なくすることが可能なのです。
特に「退職所得控除」は控除額も大きいため、これをうまく活用することがイデコの大きなポイントなのです。
なお、iDeCoの受け取るときは一時金、年金、一時金と年金の併用という方法があります。詳しくは下記記事を御覧ください。
退職所得控除が早く始めたほうが増える
退職所得控除は以下のルールで算定されます。
20年を超える場合: 退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合の、勤続年数は個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を掛けていた期間です。
つまり、長い期間かければかけていたほど退職所得控除の額が大きくなるのです。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は月に5,000円から掛けることができますので余裕がなければ最低金額からでも始めておいたほうが、退職所得控除の金額が増えるので将来の税金の心配が少なくて済むんですね。
iDeCoはできるだけ早くから始めた方がよい理由2:節税をより受けられる
もう一つ理由があります。
それは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)最大のメリットである節税効果です。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の掛け金は払えば払っただけ所得控除の対象となります。
つまり、将来の年金を積立てると税金(所得税・住民税)が安くなるってことなのです。
ただし、払えば払っただけと言っても掛け金にはお勤めの会社や仕事により上限があります。
そのため後から掛けようと思っても上限があるため出来ないのです。
つまり、早く始めればそれだけ節税効果の恩恵にあずかれるということですね。
節税効果の例
節税の効果はかなり大きいです。
例えば課税所得が500万のサラリーマン(企業年金のない会社に勤務)の方が上限まで加入した場合でみてみましょう。
企業年金のない会社員の場合の上限は月額 2万3000円。年額 27万6000円となります。
上限まで入れば年額 27万6000円がそのまま全額所得控除となります。
節税効果は所得税率10%、住民税10%として
年額 27万6000円積み立てると所得税と住民税で55,200円の節税効果が生まれるんですね。
率にすると20%もの利回りが節税効果だけで得られるのです。
この掛け金の27万6000円はなくなるわけではありません。
自分で運用して老後に受け取るお金です。
それを掛けるだけで55,200円もの節税ってこれだけでも個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に入る価値はあるでしょう。
イデコの掛け金上限
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の掛け金の上限は属性によって変わってきます。
具体的には以下のとおりです。
ちなみに最低掛けられる金額は月額5,000円となります。
| 属性 | 掛け金上限 |
| 自営業者等(第一号被保険者) | 月額68,000円 年額816,000円 ※ |
| 専業主婦(主夫)(第三号被保険者) | 月額23,000円 年額276,000円 |
| 公務員 | 月額12,000円 年額144,000円 |
| 会社員(企業年金がない会社にお勤め) | 月額23,000円 年額276,000円 |
| 会社員(企業型確定拠出年金のみ加入) | 月額20,000円 年額240,000円 |
| 会社員(確定給付企業年金に加入、もしくは確定給付企業年金と企業型確定拠出年金の両方に加入) | 月額12,000円 年額144,000円 |
つまり、自営業者の場合は最低掛金5,000円、上限68,000円となります。
企業年金がない会社にお勤めの会社員なら最低掛金5,000円、上限23,000円ですね。
※付加年金に加入している場合の上限は月額67,000円、年額804,000円
イデコと国民年金基金を併用している場合は2つ合わせて月額68,000円 年額816,000円まで
2022年10月から改正も
なお、会社員の方の上限は2022年10月から以下のように改正となります。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
| 現行 | 改正後 | |
| 企業型DCのみ加入 | 月額2万円(ただし、DCと事業主掛金合計額が月額5.5万円) | 企業型DC事業主掛金額、仮想DB相当額との合計が月額5.5万円(ただし上限2万円) |
| DBと企業型DCに加入 | 月額1.2万円(ただし、DCと事業主掛金合計額が月額2.75万円) | |
| DBのみ加入 | 月額1.2万円 |
今までは確定給付企業年金(DB)にはいっている会社にいる場合には企業型確定拠出年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)があまり多くかけられなかったのが、確定給付企業年金(DB)の金額によっては掛けられる金額が増えるということですね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
iDeCoはできるだけ早くから始めた方がよい理由3:運用は長いほうが良い
最後の理由はイデコを始める時期が早ければ早いほど運用が長く期間が取れるということです。
運用は絶対はありませんが、期待値が高いものならば運用期間を長く取れば取るほど大きなリターンが期待できるのです。
期待収益が大きくなる
投資の期待収益は以下の計算式で決まります。
運用益の例
例えば30歳から月5,000円積み立て、かなり固く運用して平均年3%の運用をしたとしましょう。
するとこれだけの運用益を得る計算となります。
運用益1,113,684円
合計金額2,913,684円
最低限の月5,000円でも1,113,684円もの利益が得られるんですね。(節税効果はまた別で得られる)
イデコは運用段階は非課税ですからこの部分の運用益に税金は掛かりません。
預金しかしらない方からすると年平均3%が多すぎると感じるかもしれません。
しかし、これはかなり固い現実的な数字なんですよ。
例えば国民年金などを運用している日本最大の運営機関であるGPIFの過去からの年あたりの平均収益率が3%くらいです。
ちなみにGPIFはかなり堅実なインデックス投資をしており、アセットアロケーションを公開していますので真似も容易なんですよ。
それを真似していればこれくらいの収益率が得られたことになります。
つまり、早く始めれば始めるほどこの恩恵にあずかれる可能性が高いってことですね。
まとめ
今回は「個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)はできるだけ早くから始めた方がよい理由」と題してイデコはできるだけ早く始めたほうがよいよって話をみてきました。
イデコはできるだけ早くはじめたほうが得です。
ただし、イデコにはデメリットもありますし、加入しないほうが良い方も見えます。
なお、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)ってなに?って方はこちらの記事も御覧ください。
この記事をみれば「iDeCo(個人型確定拠出年金)制度」から「つみたてNISAとの違い」、「おすすめ金融機関」、「おすすめ商品」、「いくら積み立てればよいのか」などを網羅的に確認することができますよ。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの5社から選ぼう
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。
しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。
簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。
私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券、大和証券、楽天証券の5択の中から決めます。
(※私が加入しているのはSBI証券です)
この5つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。
また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。
順番に見ていきましょう。
SBI証券
まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。
SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式、ひふみ年金、NYダウ、グローバル中小株、ジェイリバイブといった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。
選択の楽しさがありますよね。
また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。
[afTag id=36558]
マネックス証券
次点はマネックス証券 iDeCoです。
こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。
iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。
[afTag id=36661]
松井証券
松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。
その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。
こちらも有力候補の一つですね。
[afTag id=36658]
大和証券
大和証券 iDeCoは大手証券会社でありながら、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)にもかなり力を入れています。
他のネット証券と違い店舗が全国各地にたくさんあります。そこに魅力を感じる方にはおすすめできますね。
また、取扱商品もダイワつみたてインデックスシリーズなど信託報酬が安めの商品を取り揃えています。
[afTag id=36554]
楽天証券
楽天証券は楽天・全世界株式インデックス・ファンドや楽天・全米株式インデックス・ファンドといった自社の人気商品の取扱が大きなポイントとなっています。
この2つのファンドは人気ですね。
[afTag id=36651]
総合して考えるとこの5つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。
他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです