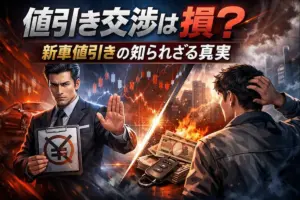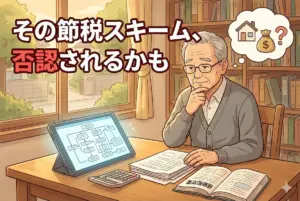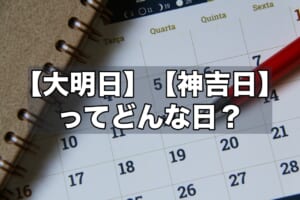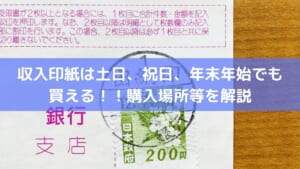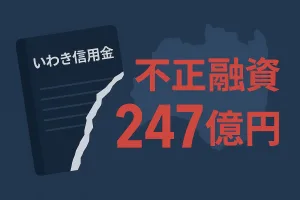固定資産税は家や土地などの不動産を所有している方が毎年支払わなければならない税金です。
多くの方は忘れないように口座振替にしているそうですが、実はもっとお得に支払う方法もあります。
今回は固定資産税のお得な支払い方法を解説していきましょう。
なお、住民税、自動車税、健康保険も基本的な考え方は固定資産税と同じです。
固定資産税の概要
固定資産税は毎年1月1日時点で保有する土地や家屋、減価償却資産などの固定資産に対して課税される税金のことです。
これら資産を保有していれば毎年発生してきます。
毎年1月1日時点で判定されますのでそれ以降に売却などをしていても発生してしまうんですよ。
なお、固定資産税は市町村に納める税金となりますので、地区により多少相違があります。
固定資産税の納付期限
固定資産税の支払いは基本的に年4回の分割払いとなります。
2024年は納期限は以下の通りとなっていると思います。(市町村により多少違う場合あり)
- 第1期 令和6年 4月30日
- 第2期 令和6年 7月 31日
- 第3期 令和6年12月26日
- 第4期 令和6年 2月28日
また、市町村によっては一括での納付も可能です。
分割納付がおすすめ
資金効率なんかを考える方は一括納付が可能であっても分割がよいでしょうね。
国民年金などと違い固定資産税は早く納めたからといって割引があるわけではないですから。
また、月ごとの利用実績により翌月の還元ポイントが変わるケースだと4回に分けて払ったほうが利用実績に反映されますのでお得です。
なお、納期限までに納めないと延滞税や延滞処分が課せられますので忘れないようにしておきましょう。
払い忘れが心配な方は一括でもよいかもしれません。
よく使われる固定資産税の支払い方法
固定資産税の支払い方法は市町村によって異なりますが、多くの場合複数のやり方が用意されています。
多くの方が使っているのが下記の2つの支払い方法です。
口座振替
まずは市町村が一番推しているのが口座振替です。
納期限が来たときに自動で引き落とされるやり方ですね。
口座振替のメリットは納付忘れがないことでしょう。
前述したように納付を忘れてしまうと延滞税などが掛かりますからね・・・
なお、口座振替をするには事前に口座振替依頼書への記入、提出が必要となります。
口座振替依頼書は最寄りの金融機関もしくは市町村で入手可能です。
一度申込みをしておけばその後は止めるまで毎年自動で口座引き落としされるようになります。
現金払い
もう一つが市町村の窓口、金融機関、コンビニなどに納付書を持っていった現金払いです。
自分の好きなタイミングで払えますからあえて現金払いを選択している方も多いです。
また、現金払いで支払えば領収書がもらえるというメリットもあります。
なにかの用途で固定資産税を納めた証明をしたい際に、わざわざ市町村で納税証明をもらわなくてもよいですからそれを狙って現金払いとしている方も見えますね。
2024年の固定資産税お得な支払い方法
少し前までは上記2つの支払い方法しか用意されていない自治体もありましたから多くの方は口座振替もしくは現金払いで支払っています。
しかし、他の支払い方法を使ったほうがお得なケースが多いんですよ。
2024年の固定資産税の支払いで使えるお得な支払い方法をご紹介しましょう。
なお、PayPayやauPay、nanacoなど固定資産税などの支払いでポイントがつかなくなるなど改悪が相次いでいますのでお気をつけください。
※市町村によっては下記支払に対応できないケースもあります。
本命は楽天Pay(請求書払い)
最近改悪続きだった楽天経済圏でしたが、最近はクレカ積立の還元率を少し戻したり、少し改善の方向も見てきています。
そんな楽天の改善で大きいのが、楽天Payが地方税統一QRコード(eL-QR)に対応して税金や公共料金の支払い(請求書払い)ができるようになりました。
楽天ペイ(請求書払い)とは税金や公共料金などの請求書から、バーコードやQRコードを読み込むことで、支払いができるサービスです。
利用者は公共料金などを自宅にいながら24時間いつでも支払いができ、支払いのためにコンビニや銀行などへ外出したり、現金を引き出したりする時間や手間を省くことができますので大きなメリットがあります。
PayPayやauPayは改悪してポイントが付かなくなってしまいましたが、楽天Payは「楽天カード」から「楽天キャッシュ」へチャージをすると0.5%の「楽天ポイント」が還元されるため、現金で支払うより0.5%お得になります。
LINEPay
LINEpayも楽天Payなどと同様に請求書払いが利用できます。
LINE Pay残高での支払いではポイントは付きませんが、チャージ&Payという機能を使うと対応クレジットカードを連携してチャージ不要で利用でき、ポイント還元を受けることができます。
対象となるクレジットカードは三井住友カードが発行するVisaブランドのクレジットカードに限定されますが、0.5%の還元となります。
ただし、税金/保険において、1回あたりの支払につき5万円を超える分はポイント還元の対象外となります。
私もSBI証券のクレカ積立用に三井住友カード ゴールド(NL)の修行をしていましたのでありがたい話です。
ただし、こちらもまだまだ利用できる自治体はあまり多くはありません。少しずつは増えていますが・・・
クレジットカード払い
次はクレジットカード払いです。
最近は多くの自治体が対応するようになってきましたね。
なお、やり方は市町村により異なります。
自治体がクレジットカード専用支払いサイトを用意しているケースもありますし、ポータルサイトなどを利用するケースもあります。(2022年4月以降YAHOO公金払いは使えなくなっている自治体が多いです)
どちらも基本的に同じですが、税金等の支払いはクレジットカードで支払うと決済手数料が取られます。
それでもクレジットカードを利用すればポイントの付きますので、固定資産税の金額やクレジットカードのポイント還元率によっては多少お得に支払うことが可能となっています。
つまり、手数料とクレジットカードでもらえるポイントを天秤に掛けて考える必要があるのです。
なお、決済手数料は自治体によって異なります。
例えば北海道札幌市の場合の手数料は以下の通りです。(2021年4月10日現在)
| 納付金額 | 納税者手数料 |
| ~5,000円 | 40円(税込み) |
| 5,001~10,000円 | 82円(税込み) |
| 10,001~15,000円 | 123円(税込み) |
| 15,001~20,000円 | 165円(税込み) |
| 20,001~25,000円 | 205円(税込み) |
※以降、納付金額が5,000円増えるごとに、手数料が加算。
このケースだと例えば20,000円の固定資産税なら165円の手数料となります。
もし1%のポイントがつくクレジットカードなら200円分のポイントが付きますので多少得となります。
税金はポイント対象外のクレジットカードに気をつけて
ただし、クレジットカードの種類によっては税金や健康保険、国民年金などの支払いはポイント対象外のケースもありますので利用しているクレジットカードのポイントルールなどは予め確認しておくのをおすすめします。
ちなみに日本で一番利用者が多いと言われる楽天カードは税金等の支払いについて2021年6月1日から改悪していますよ。
なお、主なクレジットカードの公共料金、税金、国民年金などをクレジットカードで払った場合のポイントの扱いはこちらの記事を御覧ください。
PayPayの請求書払い
次はPayPayです。
やり方は簡単。
これだけで支払いが完了します。
コンビニや銀行などに出向かなくても納付書のバーコードをスマホで読み取って手続きすれば支払いが完了してしまうのです。
かなり便利ですね。
ただし、お得度はありません。
2022年4月からポイント還元がなくなってしまったのです。
利便性は良いのでポイントは要らない。利便性だけあれば・・・って方は利用しても良いかもしれません。
au Pay請求書払い
次はau Payの請求書払い。
ほぼ仕組みはPayPayやLINE Payの請求書払いと同じですね。
こちらも還元がなくなってしまいました。
普段、au Payを使っている方で他の支払い方法がない方は検討してみてもよいかもしれません。
PayB(ペイビー)
もう一つがPayB(ペイビー)というサービスを使う方法です。
PayBはPayPayなどと同じくバーコードから読み込んで連携した銀行からお金を引き落としができるサービスです。
PayPayのようにポイントは付きませんが、手数料等は掛からず家から簡単に払えますから利便性は高いサービスですね
また、対応している自治体も多いのが魅力となっています。
ペイジー
PayBと似た名前のペイジーというのもあります。
こちらはバーコードを読み取るわけではありませんが、納付書に記載されている「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」という4つの番号を入力することでインターネットバンキングやATMから支払うことができる仕組みです。
ペイジーもポイントは付きませんが、手数料等は掛からず簡単に払えますから利便性は高いサービスですね
こちらも対応している自治体は多いですね。
まとめ
今回は「【2024年版】固定資産税のお得な支払い方法を解説」と題して固定資産税のお得な支払い方法について解説してきました。
基本的には以下に通りの流れで考えればよいでしょう。
- 楽天PayやLINEPayが使える自治体はそちらを優先
- そうでもない方はクレジットカード
- どれも使えないなら利便性のPayPay、ペイジー、PayB
劇的にお得になる方法ではありませんが、どうせ支払わなければならないものですから少しでもお得にご利用くださいね。
ポイント還元は「塵も積もれば山となる」で馬鹿にできませんよ。
なお、自治体によっては固定資産税、自動車税、住民税、健康保険の納税猶予の特例があったり、住民税の減免制度、健康保険の減免制度があったりするので所得が大きく減った方はそれらもうまく使いたいところですね。
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。