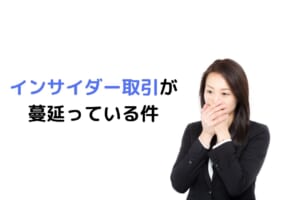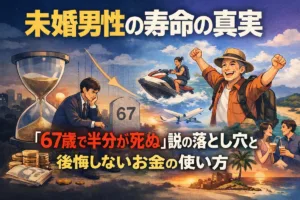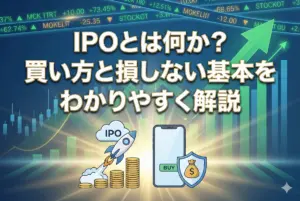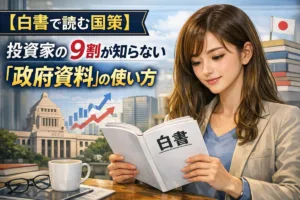知り合いから以下のような質問がありました。
同じような悩みをお持ちの方もお見えでしょうから、今回は財形貯蓄と個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)のどちらが良いのか?について考えてみましょう。
財形貯蓄とは
まずは今回の話の前提となる財形貯蓄とは何かについてから見ていきましょう。
財形貯蓄は従業員の財産づくりを事業主と国が⽀援する制度です。
給料から貯める金額を天引きされますので確実にお金を貯めることができます。
また、⽼後資⾦や住宅取得を⽬的とした貯蓄の場合、その利⼦が⾮課税となる税制上の優遇措置も⾏われています。
なお、財形貯蓄は「勤労者財産形成促進制度(財形制度)」の中の一つの制度となります。
勤労者財産形成促進制度には「財形貯蓄制度」、「財形持家融資制度」、「財形給付金・基金制度」などの制度があります。このうち「財形貯蓄制度」が俗に財形貯蓄と呼ばれています。
ちょっとややこしい制度ですが、簡単に言えば財形貯蓄とは従業員がお金を貯めやすくする制度と考えればよいでしょう。
財形貯蓄に加入できる人
財形貯蓄は誰でも加入できる制度ではありません。
個人では加入できませんから、勤め先の会社がこの制度を導入していないと利用することができないのです。
自社が財形貯蓄を利用できるのかは会社の総務や人事などにお尋ねください。大手企業では多くが採用していますが、中小企業では1/4くらいしか採用されていないようですね。
なお、財形貯蓄は勤め先の会社に制度があっても加入は任意です。
ちなみに私がいた会社も制度はありましたが、加入していませんでしたね。
給料天引き
財形貯蓄のポイントの一つが給料天引きであることが上げられます。
どうしても一度自分の財布に入ってしまうと貯められない方がいます。
しかし、給料天引きで自動で貯めることができればお金は貯めやすくなります。
非課税
もう一つ財形貯蓄のポイントがあります。
それは金利部分が非課税であるということが挙げられます。
通常、預金の金利等には税金がかかります。
しかし、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄に関しては金利部分が非課税となるメリットがあります。(一般財形貯蓄には税制面のメリットはありません)
非課税の条件は以下の通りです。
利回りは?
財形貯蓄の運用は会社が決めます。
会社により投資先は預金、投資信託、国債、保険など様々です。
利回りはその運用方法、運用方針によって大きく異なります。
つまり会社によって異なるんですね。
また、投資先によっては元本割れの可能性があります。
運用を失敗して財形も元本割れしていたケースを何件かみてますね。
ちなみに前述の方の会社の運用利回りは1%とのこと。
運用方針や運用先は知らないとのことでした。
これが固定ならば預金などと比べてかなり良いのですが・・・
目的外の利用に制限
また、目的外の利用に制限がかかってしまうことも知っておくべきでしょう。
一般財形貯蓄は払出しの制限はありませんので、理由によらず払出しをすることが可能です。
しかし、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合は基本的に目的外での払出しは利子等課税の対象となり、遡って5年分までの利子分が「利子所得」として課税対象となってしまいます。
ただし、以下の条件を税務署から確認を受けることができれば非課税で払出しをすることが可能です。
・本人または生計を一にする親族に対して支払った医療費の年間合計額が200万円を超えた場合
・本人が所得税法上の一定の寡婦又は寡夫に該当することとなった場合
・本人が所得税法上の特別障害者に該当することとなった場合
・本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当することとなった場合
商品変更が困難
一般財形貯蓄は3年以上財形貯蓄を保有していれば、任意に別の金融機関の財形商品に預け替えることができます。
しかし、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合には保有期間に関わらず、任意に別の金融機関の財形商品に預け替えることはできません。
この辺りはかなりのデメリットとなりますね。
始めの時点でしっかり選択をしておく必要があるのです。
退職時
また、財形貯蓄は退職時にちょっと面倒となります。
退職や、役員になるなど、勤労者でなくなった場合は、新たな積立はできなくなります。
また、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄においては、退職後一定期間が経過すると、課税扱いとなります。メリットがなくなってしまうってことですね。
この場合には目的外の利用と同じく遡って5年分までの利子分が「利子所得」として課税対象となります。
ただし、再就職先にも財形貯蓄制度があれば手続きをすれば持ち運ぶことも可能です。
財形貯蓄はかなりややこしい制度です。しっかりメリット・デメリットを理解して加入を検討しましょう。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)とは
次にイデコについても何かについてから見ていきましょう。
個人型確定拠出年金(イデコ/iDeCo)とは、毎月決まった金額を積み立てることで老後の生活に備えるための公的な制度です。
この制度最大の特徴は税金面で様々な優遇措置が取られていることです。
具体的にはこんな感じの流れです。
そしてそのお金を投資信託や定期預金、保険などの商品を選択して運用します。
そして60歳以降にその運用した資産を受け取ることができる仕組みになっています。
下記の図のように国民年金や厚生年金と合わせた年金制度の上乗せとして考えると良いでしょう。
掛け金として掛けられる金額ははその人の厚生年金等の状況により変わってきます。
例えば国民年金のみに加入ししている第一号被保険者でしたら国民年金基金と合わせて6万8千円まで加入することができます。
(付加年金入っている場合には6万7千円)
また、サラリーマンで年金制度がない会社にお勤めの方ならば月額2万3千円まで掛けることができます。
確定給付型年金などの年金制度がある会社にお勤めの場合には月額1万2千円まで掛けられます。
公務員の方も同様に月額1万2千円が上限となります。

出所:厚生労働省 iDeCo説明ページ
個人型確定拠出年金(イデコ/iDeCo)に加入できる人
イデコは2017年の法改正から基本的にほとんどの方が加入できるようになっています。
ただし、以下の一部の方は加入ができません。
- 国民年金の未納のある方
- 海外勤務、海外中学中の方(例があり)
- 企業型確定拠出年金に加入している方(例外あり)
基本は自分の口座から引き落とし
イデコもお勤めの会社によっては給料天引きが可能となっています。
ただし、多くの場合は自分の銀行口座からの引きと落としとなります。
節税効果
イデコの最大の特徴は節税効果です。
所得税と住民税の節税が見込めるのです。
まず、イデコの掛け金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)となります。
所得控除とは税金計算するときにその金額を控除して税金計算できるようになるってことです。
つまり、所得を減らしたことと同じ効果が得られます。
そのため、掛けた年の所得税、住民税が節税できるのです。
さらに運用時は非課税。
受け取り時に税金がかかるわけですが、受け取るときも「退職所得控除」、「公的年金控除」が利用できます。
特に退職所得控除はかなり大きいですからうまく受け取ればかなり税金は少なくなるのです。
つまり、掛けたときの節税効果分お得なんですよ。
所得税率が20%の方なら住民税とあわせて約30%の節税効果をはじめから約束されているようなものなのです。
財形貯蓄とはこの部分が大きく違いますね。
利回りは?
イデコの運用方法や運用商品は自分が決めます。
投資先はどこの証券会社などの金融機関で始めるかによって異なりますが、日本株、アメリカ株、世界株、先進国株、債券、預金などいろいろな中から選択が可能です。
自分で運用先を決められますから途中で路線変更なんかも簡単にできるのは嬉しいですね。
そのため、利回りはその人の運用によって異なってきます。
参考までに利回りを統計データからみると下記の様になっていますね。
ほとんどの方はご相談者の財形貯蓄の1%を超えているのがわかります。
60歳まで引き出せない
財形貯蓄は目的外の利用が難しかったり、しましたが、イデコはそもそも60歳まで基本的に引き出せません。
年金制度ですから当然なのかもしれませんが。
そのため、ある程度余裕資金でやる必要があるでしょう。
子供の学費とか結婚資金とかそういった用途には使えません。
商品変更は簡単
イデコはどこの金融機関で始めるのかも選択できます。
また、自分で運用する商品も決めらます。
途中で商品の変更、金融機関の変更も可能となっています、
このあたりの自由度は財形貯蓄よりもイデコの方がありますね。
退職時
イデコは財形貯蓄と違い勤務先に紐付いているものではありません。
そのためイデコは手続きさえふんでおけば退職後もそのまま利用が可能となっています。(一部例外を除く)
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
イデコと財形貯蓄のどちらが良いのか?
それではイデコと財形貯蓄どちらが良いのでしょう?
どちらもお金を貯めるという意味では同じです。
ですが、制度上の仕組みを考えれば基本的には財形貯蓄よりも個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)をおすすめしますね。
イデコは財形貯蓄と違って所得税と住民税の節税効果があることが大きいですね。
財形年金貯蓄も利益部分については非課税(上限あり)となりますが、所得税と住民税の節税効果がありませんのでその点が大きな違いとなります。
ただし、イデコは掛けられる上限があまり高くありませんので上限まで掛けて余裕がある方は財形貯蓄も併用しても良いでしょう。
イデコと財形の比較まとめ
イデコと財形の今まで見てきた比較をまとめてみると以下のとおりです、
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
| 財形貯蓄 | イデコ | |
| 加入できる人 | 財形貯蓄のある会社に勤務 | 一部例外を除いてほとんどの方が加入可能 |
| 税制優遇 | 利子等が非課税(上限あり) | ・掛け金が所得控除所得税、住民税の節税効果 ・運用益非課税 ・受け取るときは退職所得控除、公的年金控除が利用可能 |
| 運用商品、金融機関 | 会社が選択 | 自分が選択 |
| 受け取り方法 | 一般財形:いつでも払い出し可能 財形年金貯蓄:60歳以降に年金で受け取る 財形住宅貯蓄:家の新築等で引き出し可能 |
60歳以降に一時金、年金、併用で選択可能 |
基本的に多くの面でイデコの方が有利であることがわかりますね。
イデコの掛け金上限
ちなみにイデコの上限は以下の通り。勤務先等によって異なるんですよ。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
| 国民年金の種別 | その他条件 | 掛け金の拠出額上限 |
| 第一号被保険者(自営業者、無職等) | ー | 月額68,000円(年額816,000円) |
| 第一号被保険者(自営業者、無職等) | 付加年金加入者 | 月額67,000円(年額804,000円) |
| 第二号被保険者(会社員等) | 企業型確定拠出年金がない会社勤務 | 月額23,000円(年額276,000円) |
| 第二号被保険者(会社員等) | 企業型確定拠出年金がある会社勤務 | 月額20,000円(年額240,000円) |
| 第二号被保険者(会社員等) | 公務員、企業年金加入者 | 月額12,000円(年額144,000円) |
| 第三号被保険者(専業主婦) | ー | 月額23,000円(年額276,000円) |
なお、下限は5,000円となります。
5,000円から各属性の拠出額上限までの間で掛け金を決める形ですね。
ちなみに掛け金の平均は以下の記事を御覧ください。
満額かける人と最低限かける人の二極化している感じですね。
まとめ
今回は「財形貯蓄と個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)のどちらが良いのか?」と題して財形貯蓄とイデコを比較してみました。
私の意見をまとめると以下のとおりです。
- イデコの方が節税効果がある分だけ有利なので優先しよう
- イデコを満額掛けても余裕があれば財形貯蓄も
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの5社から選ぼう
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。
しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。
簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。
私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券、大和証券、楽天証券の5択の中から決めます。
(※私が加入しているのはSBI証券です)
この5つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。
また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。
順番に見ていきましょう。
SBI証券
まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。
SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式、ひふみ年金、NYダウ、グローバル中小株、ジェイリバイブといった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。
選択の楽しさがありますよね。
また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。
[afTag id=36558]
マネックス証券
次点はマネックス証券 iDeCoです。
こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。
iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。
[afTag id=36661]
松井証券
松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。
その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。
こちらも有力候補の一つですね。
[afTag id=36658]
大和証券
大和証券 iDeCoは大手証券会社でありながら、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)にもかなり力を入れています。
他のネット証券と違い店舗が全国各地にたくさんあります。そこに魅力を感じる方にはおすすめできますね。
また、取扱商品もダイワつみたてインデックスシリーズなど信託報酬が安めの商品を取り揃えています。
[afTag id=36554]
楽天証券
楽天証券は楽天・全世界株式インデックス・ファンドや楽天・全米株式インデックス・ファンドといった自社の人気商品の取扱が大きなポイントとなっています。
この2つのファンドは人気ですね。
[afTag id=36651]
総合して考えるとこの5つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。
他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです